現在では「終活」という言葉が一般的になりましたが、具体的に何をやるべきか、何から始めればよいか、悩む方も多いのではないでしょうか。
終活のやることリストは、以下の通りです。
|
本記事では、終活カウンセラーが終活でやっておくべきことを紹介します。
終活のやることリスト【全10項目】

この章では、終活のやることリストを順に解説します。
1.資産整理をする
第三者への情報漏えいを防ぐため、家族に確実に資産を渡すためにも、資産整理は必ず行うようにしましょう。
具体的には以下のようなものがあります。
|
これらは自分が亡くなった後に、残された家族が解約・資格喪失届・名義変更などの手続きをする必要があるものです。
そのため、必要な情報や書類が見つからなければ、残された家族が困ることになります。
不要なものは解約手続きなどを済ませ、必要なものは一箇所にまとめるなどして家族に保管場所を知らせておきましょう。
また、パソコンやスマートフォンなどに保存された個人情報やデータを整理する「デジタル終活」も忘れてはいけません。
写真や動画など家族に残しておきたいものは明確にし、人に見られたくないものは自ら処分するか、処分して欲しい旨を家族に伝えておきましょう。
2.身辺整理をする
身辺整理も大切な終活です。
不要品を整理しないまま亡くなってしまった場合、残された家族が処分しなければなりません。
家族の負担を減らすためにも、以下の方法で不用品を処分しておきましょう。
|
3.葬式やお墓を決める
どのような葬儀をして欲しいか、どのお墓に入りたいかなどの希望を家族に伝えておくことも大切です。
あらかじめ決めておけば、残された家族の負担を減らすことができます。
葬儀にも直葬・一日葬・家族葬などさまざまな形がありますので、希望を伝えておくようにしましょう。
お墓に関しても、永代供養墓・共同墓・樹木葬などなどの種類があり、散骨や手元供養といったお墓以外の選択肢もあります。
亡くなる直前に希望を伝えると家族も困惑しますので、あらかじめ伝えておくようにしましょう。
また、遺影も用意しておけば家族が準備する手間も省けるでしょう。
4.相続の準備をする
終活では相続の準備、相続税の把握も大切です。
相続人が複数いる場合は、誰に何を相続するのか明確にしておかなければ家族間でトラブルになる可能性があります。
家族が相続で争わないためには、遺言を書いておくことが有効です。
まず自分の財産がどれくらいあるのか正確に把握し、配分を決めて遺言書を作成しておきましょう。
5.今後の住居を考える
現在の住まいに住み続けるのか、高齢者住宅・施設などに移るのか、子どもと同居や近居するのかなどを決めておきましょう。
住まいを家族の誰かに相続する場合は、相続トラブルを防ぐためにあらかじめ相続人に知らせておくことも忘れてはいけません。
また、自分の死後に住まいが空き家になってしまう場合は、終活の段階で解体方法や管理方法について家族と話し合っておく必要があります。
解体する場合は、解体費用を確保しておく方が残された家族も安心でしょう。
6.終末医療を考える
大きな病気や認知症を患ったときのために、どのような医療を受けたいか、延命治療を望むかなどについて家族に意思表示しておきましょう。
深刻な病状になったとき、重要な決断を迫られる家族の心の負担は大きいものです。
本人の希望が分かっていれば家族も心理的な負担が減り、スムーズに手配を進めることができます。
7.老後資金を確認する
預貯金などの十分な老後資金があれば安心ですが、十分でない場合は確保する必要があります。
老後の資金を確保におすすめなのが、リースバックとリバースモーゲージと呼ばれる方法です。
老後の生活費などで子どもに負担をかけたくない場合は、検討してみるのも一つでしょう。
リースバック
リースバックとは「持ち家を売却し、売却した相手からその家を貸してもらう」という住宅売却手段のことで、現在の生活環境を変えることなく老後資金を増やしたい方におすすめの方法です。
まとまった現金が手に入るうえに、同じ家に賃貸で住み続けられるため引っ越す必要もありません。
現金化までの時間が短いのもメリットです。
ただし、売却金額が一般相場よりも安くなる可能性がある、売却金額がローンの残債を下回る場合は利用できない、などのデメリットもあります。
リバースモーゲージ
リバースモーゲージとは、「持ち家を担保に金融機関や自治体からお金を借り、亡くなった後に家を売却して清算する」という方法です。
担保にした持ち家の限度額まで、小額ずつ定期的に借りられるのがポイントです。
「まとまった現金が欲しい」というよりは、「必要なときに少しずつ借りたい」という人におすすめの方法といえるでしょう。
ただし、長生きすればするほど融資限度額まで使い切ってしまうリスクや、土地や建物の価値が下落すると融資限度額を見直されるリスクもあります。
8.サービスを検討する
終活の一つとして、老後の生活を支えてくれるさまざまな契約の利用も検討してみましょう。
財産管理委任契約
財産管理委任契約とは、「自分の財産の管理や生活上の事務を代行してくれる人を選んで委任する契約」のことです。
例えば、受任者が委任者からキャッシュカードを預かって銀行口座からお金を引き出し、各種の支払いを行うなども可能になります。
どのような管理を委任するかは自由に決められますが、銀行窓口での手続きや不動産の売却など委任が難しいものもあります。
委任が可能なもの、不可能なものについて契約前にしっかり確認することが大切です。
任意後見契約
認知症などが原因で判断能力を失ってしまった場合、自分の代わりに財産を管理したり、生活に関する手続きを行ったりする後見人を指定しておく契約です。
判断力が低下すると、詐欺や悪徳商法などで財産を奪われる心配もあります。
任意後見契約を結んでおくことは、自分の財産を守ることに繋がります。
見守り契約
見守り契約とは、支援者に「任意後見をスタートする時期」を判断してもらうための契約です。
支援者は契約者と面談したり連絡を取ったりしながら、定期的に生活状況や健康状態を確認します。
定期的なコミュニケーションによって変化をいち早く察知してもらえるため、任意後見開始のタイミングを正確に見極めてもらうことが可能です。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは「葬儀・納骨・埋葬」などの死後事務手続きを第三者に委任する契約」のことです。
他にも「役所への行政手続き」「病院代などの清算」「年金手続き」「クレジットカードの解約」など、さまざまな事務手続きを委任することができます。
これらの死後事務手続きは基本的に家族や親族が行うものですが、身寄りがない方の場合は死後事務委任契約が大いに役立ちます。
民事信託
民事信託とは「家族間、親族間で行われる営利を目的としない信託」のことです。
「高齢になった親の財産の名義を子どもに移転し、管理を子どもに託す」と言い換えれば分かりやすいかもしれません。
例えば、親が認知症になってしまった場合、親の自宅を売却して専門の施設に入れることも考えなければなりませんが、自宅の名義が親のままであれば子どもは売却することができません。
民事信託をしておけば、認知症などで親の判断力が低下した場合に子どもの判断で自宅を売却することなども可能になります。
生前契約
生前契約とは、主に一人暮らしの高齢者に向けた身元保証、日常生活支援、生前事務、死後事務などに関するサービスの名称です。
一般社団法人やNPO法人、公益法人等の民間団体によって提供されています。
パートナーや子どもがいない場合、生前契約を結んでおくことで以下のような事務手続きの問題も解消できます。
【生前事務】
|
【死後事務】
|
ペットに関する信託契約等
ペット信託とは、財産の一部を信頼できる人物や団体に託し、ペットの世話ができなくなったときはその財産から飼育費を支払ってもらう仕組みのことです。
日本ではペットに財産を相続させることはできないため、代わりにペットが余生を安心して過ごせるような施設や、新たな飼い主を探してくれるNPO法人などがあります。
これらのペット信託先に早い段階で見当をつけ、どれだけの財産を準備するか決めておくことが大切です。
ペット信託の大きなメリットは、ペットの飼育に強制力と監視力を持たせられる点です。
ペット信託では、信託先に「忠実に飼育を行い、信託されたペット用の財産を適切に管理する義務」が発生します。
義務に違反している場合は監督人が指摘して改善させることができるため、飼い主も安心してペットを任せることができます。
9.エンディングノートを作成する
エンディングノートとは、自分の死に備えて「生きている間にしたいこと」「自分の死後にして欲しいこと」などを書き記しておくノートのことです。
遺言書のような法的効力はありませんが、残された家族に自分の希望を伝える大切な役割を持っています。
エンディングノートの書き方
エンディングノートに決まった内容や書式は存在しません。
自分が必要だと思ったことを自由に書けば問題ありませんが、「他人が読むもの」であることを忘れないようにしましょう。
誰が読むか分からないため、他人が読んで分かりやすいように書くことはもちろん、誰に読まれても差し支えない内容を書くことが大切です。
一般的に、エンディングノートには以下の内容を記載します。
|
▼エンディングノートについて詳しくはこちらの記事をお読みください
エンディングノートに記載する内容などを解説
10.遺言書を作成する
遺言書には以下の3種類があります。
|
いずれの遺言書も記載項目・形式などが法律で定められており、条件を満たさないものは法的効力を持ちません。
遺言書を作成する前に書式などを確認し、それぞれのメリット・デメリットも把握しておくことが大切です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、全文を遺言者が自筆で書き、日付と氏名を記入・押印する遺言書です。
代筆やパソコンでタイピングしたもの、具体的な日付が記載されていないものなどは無効になるため注意が必要です。
自筆証書遺言のメリット・デメリットには以下のようなものがあります。
| メリット | デメリット |
|
|
ただし、2019年・2020年の相続法改正で下記の変更があったため、自筆証書遺言を選ぶデメリットは少なくなっています。
|
公正証書遺言
公正証書遺言とは「遺言の内容を公証人に伝え、公証人が作成する遺言書」のことで、完成した遺言書は公証役場で保管してもらうことができます。
公正証書遺言のメリット・デメリットは以下です。
| メリット | デメリット |
|
|
公正証書遺言が、法的に最も確実性の高い遺言作成手段といえるでしょう。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは「内容を秘密にできる遺言書」です。
まず、遺言書に自筆の署名・押印をして、封筒には遺言書の押印と同じ印鑑で封をします。
証人2人とともに封筒を公証人のもとへ持参し、公証人が「遺言者」「遺言書の提出日」を封筒に記載すれば完成です。
秘密証書遺言のメリット・デメリットには以下のようなものがあります。
| メリット | デメリット |
|
|
秘密証書遺言は誰にも遺言の内容を知られたくない場合に有効な手段ではありますが、現在ではほとんど利用されていません。
終活を始める際の注意点
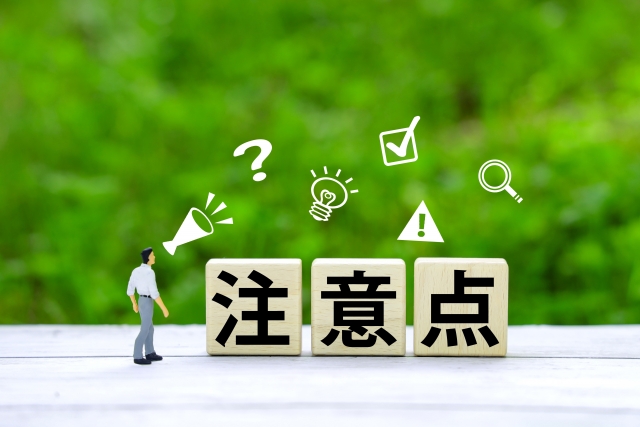
ここからは、終活を始める際の注意点を紹介します。
できることから始める
終活にルールは存在しないため、やることリストをすべて行う必要はありません。
終活の目的は家族の負担を軽減しつつ、今後の人生を充実させるために行うものです。
終活が負担にならないよう、できることから自分のペースで進めましょう。
家族の理解を得る
終活では、自分の希望を伝えるだけでなく、家族の理解を得ることも大切です。
相続に関してはトラブルが起こることも少なくないため、家族の意見や希望も聞きましょう。
例えば、「献身的に介護してくれた長女の相続分を多くする」など、子どもによって相続分が異なる場合は家族を説得する必要があります。
弁護士などの専門家からのアドバイスをもとに家族の理解を得ることも、終活の一つです。
時間をかけて進める
終活は一気にやりきろうとせず、時間をかけて進めましょう。
やることリストには、すぐに決められないことも含まれるため、自分の人生を振り返りながら余裕をもって考えることが大切です。
先述の通り自分のペースで、納得のいく終活を行いましょう。
デジタル終活を行う
デジタル終活とは、スマートフォンやパソコンに残るデータを整理することを指します。
死後、データが勝手に消えることはないため、定期的に整理し、データの処分方法や取り扱いに関する希望はエンディングノートに記載しておきましょう。
また、サブスクリプションサービスを利用している場合は、家族が知らないまま利用料金が発生し続けるケースもあるため、デジタル終活は忘れず行う必要があります。
専門家へ相談する
終活をスムーズに進められるよう、専門家へ相談するのも一つです。
やることリストの中でも葬式やお墓、相続などを検討する際は専門知識が求められるため、不安があれば専門家を頼ってプロのアドバイスを受けましょう。
終活カウンセラーは、財産管理や相続、葬式、お墓などの知識を幅広く習得しているので、一度相談してみるとよいかもしれません。
終活全般のサポートを行う「林商会」では、終活カウンセラーがお客様のお悩みやご不安を解消いたします。
些細なことでも丁寧にお答えいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
\お気軽LINE・電話相談OK/
Q&A:終活に関するよくある質問

この章では、終活に関するよくある質問にお答えします。
終活を始めるタイミングは?
終活を始めるタイミングは主に3つあります。
身近な人が亡くなったとき
配偶者や自分の両親などの身近な人が亡くなったときが、終活を始めるタイミングの一つです。
身近な人が亡くなると、「自身の死」にも向き合うことになります。
残された家族の辛さや大変さ、必要な手続きについても分かるため、自身の終活も始めやすくなるでしょう。
定年退職したとき
定年退職は生活環境や収支が変わる人生のターニングポイントになるため、終活を行うのに最適なタイミングといえます。
しがらみもなくなり、時間にも余裕が生まれるため、落ち着いてゆっくりと終活を進めることができるタイミングです。
病気になったとき
自分や家族が病気になったときも終活を始めやすいタイミングです。
終活には医療や介護、保険の手続きなども含まれます。
病気が「本当に必要な保険や医療」「理想の生き方や人生の終わらせ方」を見つめ直すきっかけになり、終活を始める人は多いようです。
終活は何歳から始めるべき?
終活は、元気なうちに始めるべきです。
年齢ではなく「終活を始めよう」と思ったときに始めるのがよいでしょう。
特に20代や30代ではまだ早いと思われがちですが、若いうちから終活を始めることで今後の人生をより豊かにできます。
年代別の終活を始めるメリットや始め方は、以下の記事で解説しています。
20代の終活/30代の終活/40代の終活/50代の終活/60代の終活
終活は何から始めればよい?
終活は一気に進めようとせず、体力が必要な終活から徐々に進めていくことがコツです。
特に体力の必要な終活は以下の3つです。
|
大型家具の処分にはもちろん体力が必要ですが、小さなものであっても「捨てる」という行為自体に精神的な負荷がかかります。
また、お墓や介護施設を選ぶ際は現地に行って見学する必要があるため、足腰が悪くなってからでは困難です。
いずれの終活も、心身ともに健康なうちから進めておくほうが無難でしょう。
終活に関するご相談は林商会へ

林商会には「終活カウンセラー」という終活の専門家が在籍しており、終活に関するお悩みやご不安を解消するサポートを行います。
遺言書・エンディングノートの作成や相続、お墓の相談など、お客様の気持ちに寄り添うことを第一に、終活のご相談を幅広くお受けしております。
どのようなご相談にも誠実かつ丁寧にお応えいたしますので、終活に関するご相談はぜひ林商会までお気軽にお問い合わせください。
\お気軽LINE・電話相談OK/
まとめ
終活はやることが多く想像以上に時間がかかるため、早い段階から少しずつ進めていくことが大切です。
自分の死と向き合わなければならないうえに、体力や気力が必要な作業も多いため、時には気が滅入ってしまうことがあるかもしれません。
しかし、終活とは「死後の準備」ではなく、「これからの人生をより充実させ、安心して豊かに過ごすための準備」です。
今後の人生をより良いものにするためにも、前向きな気持ちで取り組んでいきましょう。




















