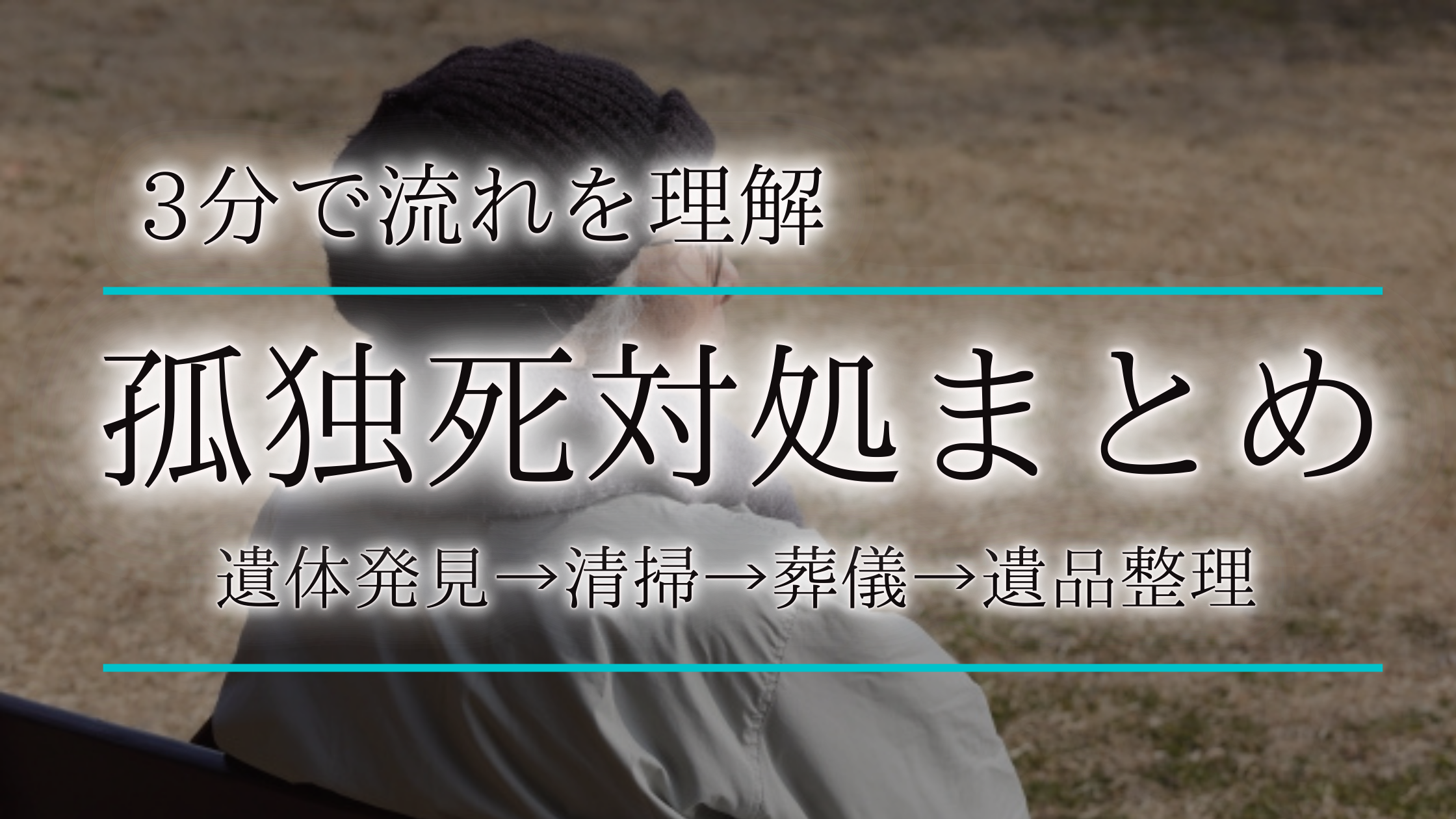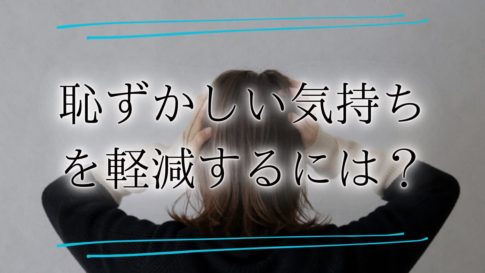近年増加している孤独死ですが、もしも身近で孤独死が起こってしまった場合どのように対処すべきなのでしょうか?
まずは、救急車あるいは警察に連絡します。
この記事では、遺体発見後通報~葬儀・特殊清掃・遺品整理など全ての流れをご紹介します。
突然現場に直面しても焦らないよう、大まかな流れを把握しておきたいですね。
孤独死について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
目次
孤独死発見からの対処していく流れ

孤独死が発見されるきっかけには、家族が訪れて気付くケースや、遺体の異臭で近所の人が気付くケースなど、色々なケースがあります。
孤独死を発見してしまった時は、以下のような流れとなります。
| ①遺体発見→救急車or警察へ連絡 ➁警察での検死・身元確認 ③葬儀・特殊清掃の手配 |
まずは大まかに、どういった対処をするべきか把握しておきましょう。
①遺体を発見!自分(家族)だった場合/他人(大家等)だった場合
自分(家族)が倒れているところを発見した場合、生死の判断が付かない場合は救急車に連絡しましょう。
なぜなら「本人は動かないけれど、亡くなっているとは言い切れないから」です。
まずは救急車を呼び、救急隊が倒れている人の生死を確認します。もし事件の可能性があれば、救急隊がそのまま警察へ通報を行います。
ただし、発見時に異臭がして明らかに亡くなっていることが分かる場合は、警察に連絡しましょう。
警察は到着後、事件や事故、病気など死亡原因を検証します。
他人(大家さん等)に発見された場合は、警察や大家さんの方から自分(家族)に電話が来ます。
②警察での検視・身元確認
警察の到着後、そのまま検視と身元確認がおこなわれます。
同時に「家宅捜査」も実施されるため、亡くなった人の自宅にある金品も一時的に没収されます。
このとき遺族は、身元確認のため、故人の居住する地域の警察署へ向かいましょう。
併せて印鑑と戸籍謄本の準備をしておきます。
身元が判明したら、亡くなった人の親子、兄弟、親戚など「血縁が近い順」に警察が連絡をします。
身元が判明しなかった場合、遺体は「保管庫」に安置されます。後日遺族が見つかった場合、安置費用として1泊2,000円程度の安置費用が請求されます。
③遺体引渡しまでに葬儀社・特殊清掃の手配を
遺体が引き渡された後は、葬儀をおこなうのかそれとも火葬だけなのか、複数の選択肢があります。
ただ、いずれにしても手配は必要になるため、遺体の引き渡し前に葬儀・火葬社を手配しておく必要があります。
葬儀の内容や費用面などを親族で相談しましょう。
特殊清掃も同様です。
孤独死は、発見時にすでに死体が腐敗しているケースが多く、室内が体液や死臭で汚染されています。
とても素人が片付けられるものではないため、自宅を清掃する特殊清掃業者へ依頼するのが一般的です。
また特殊清掃は、業者によってサービス内容や料金がさまざま。
料金だけを見て選ぶのではなく、「経験が豊富かどうか」「遺品整理を一緒にやってくれるかどうか」といった視点で選ぶことをおすすめします。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
④葬儀・火葬
孤独死の葬儀も、一般的な葬儀と同じような内容でおこなわれます。
ただし、遺体の状態によっては葬儀前に火葬がおこなわれることも。
遺体の腐敗状況によっては、葬儀をおこなう前に火葬をした方が良いケースもあります。
発見が遅かった孤独死の場合は、できるだけ早く火葬することが重要です。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
⑤遺品整理・特殊清掃
孤独死の場合、火葬同様に特殊清掃や遺品整理も早急に行われるケースが大変多いです。
というのも、孤独死が起こった現場は害虫や異臭が発生しすぐにでも対処しないと近隣からの苦情を受けてしまう可能性があるからです。
特殊清掃は、部屋に染み付いた体液や血液、臭いを清掃する作業です。
一方の遺品整理は、故人の身の回りのものや遺産などを仕分ける作業を指します。
遺品整理は葬儀や特殊清掃が済んでから最後におこなうのが一般的ですが、孤独死の場合は遺品にも体液や死臭が付着しており、同じく早めに対処する場合も多いのです。
業者選びに悩む方も多いですが、実は遺品整理と特殊清掃をどちらも請け負ってくれる業者も数多くあります。
費用面や手配の手間を考えても、経験のある一社にまとめて依頼するのが良いでしょう。
一般的な遺品整理は家族が行うことが多いのですが、孤独死の遺品整理は業者に依頼することをおすすめします。
林商会では、遺品整理・特殊清掃を一括で承っております。
詳しくは以下の記事でもご説明しているのでご覧ください。
今や孤独死が他人ごとではない原因

孤独死が年々増加している現代。
「自分とは関係のないこと」と思うかもしれませんが、今や他人ごとではありません。
意外にも孤独死は身近なところにあるのです。
孤独死が他人ごとではない理由として、以下の3つが挙げられます。
| 1.一人暮らしの高齢者が増加 2.高齢者の貧困化 3.地域で孤立し発見が遅れる |
1. 一人暮らしの高齢者が増加
1つ目は「一人暮らし高齢者の増加」です。
現代においては、男女ともに65歳以上の一人暮らしの高齢者が増加傾向にあります。
一人暮らし高齢者数の比較はこちらです。
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 1980年 | 約19万人 | 約69万人 |
| 1985年 | 約23万人 | 約95万人 |
| 1990年 | 約31万人 | 約131万人 |
| 1995年 | 約46万人 | 約174万人 |
| 2000年 | 約74万人 | 約229万人 |
| 2005年 | 約105万人 | 約281万人 |
| 2010年 | 約138万人 | 約340万人 |
| 2015年 | 約192万人 | 約400万人 |
| 2020年 | 約243万人 | 約459万人 |
一人暮らしの高齢者数は、40年前と比べて桁違いの数字となっています。
1980年では男性が約19万人、女性が約69万人だったところ、現在2020年では男性が約243万人、女性が約459万人にまで増えています。
高齢化や核家族の加速、熟年離婚などによって、単身で暮らす高齢者も増えているのです。
一人暮らし高齢者の増加に比例して、孤独死する人の数も増えているのが現状です。
2. 高齢者の貧困化
2つ目は「高齢者の貧困化」です。
高度経済成長期、いわゆるバブル崩壊から不況続きの日本。
昔と比べて今は、不景気によるリストラや退職金の減額、さらには年金受給開始年齢の引き上げなど、一人ひとりの経済的負担が大きくなっています。
経済的余裕がないため、人付き合いや趣味など楽しみを持てず、引きこもりがちな高齢者が増えているのが現状です。
また、経済的余裕がないため適切な医療を受けられず、最終的に自宅で亡くなってしまうといったケースも少なくありません。
貧困によって孤立感が強まり、孤独死を招いている現状もあるのです。
3. 地域で孤立し発見が遅れる
3つ目は、「地域で孤立し発見が遅れる」ということ。
地域での生活には、近所付き合いが付きものです。
しかし、近所の人との人間関係がうまくいかず、結果孤立してしまう人も少なくありません。
また高齢者の孤独死は、女性よりも男性の方が多い傾向にあります。
男性は女性よりもコミュニケーション頻度が少なく、家事ができない人も多いためです。
したがって、人間関係が希薄になったり、衛生管理や栄養状態が悪くなったりと、いわゆるセルフネグレクトのような状態になってしまいます。
生活の質が下がり、ますます引きこもりがちになってしまうのです。
スーパーに買い物へ行くのもおっくうになり、次第に自宅がゴミ屋敷に。
引きこもると隣近所との接点も生まれないため、いざ自分の容体が変化したときに誰も気づいてくれないのです。
孤独死を防ぐためにすべき対策

孤独死は、周りの意識次第で孤独死を防ぐことが可能です。
家族であれば、老人ホームへの入居を進めたり、こまめに電話をしたりと、本人が孤立しない環境を作ってあげることを意識してみてください。
たまに自宅へ様子を見に行ってみるのも良いでしょう。
そうすることで、本人にも安心感が生まれます。
近所に住んでいる人であれば、自宅の前を通りがかったときに「ポストがあふれていないか」を確認したり、すれ違ったときに挨拶や世間話をしたりするのも良いでしょう。
周りの人がサポートすることで、本人に対して「社会とつながっている」という認識を与えることが大切です。
もっと詳しく対策方法が知りたい方は以下の記事をご覧ください。
まとめ
本記事では、孤独死が起こってしまったときの対処法について解説しました。
万が一孤独死を発見した場合、焦らずに救急車や警察を呼びましょう。
その後、警察の指示に従って速やかに葬儀、特殊清掃の手配などをおこなうことが大切です。
孤独死は決して他人ごとではなく、意外と身近にあるものです。
気付いてからではもう遅いため、もし身近に孤立しそうな家族がいるのなら、電話をしてみたり、自宅に様子を見に行ってみたりと、早急に対策を打ちましょう。