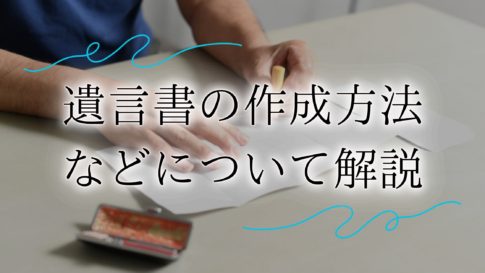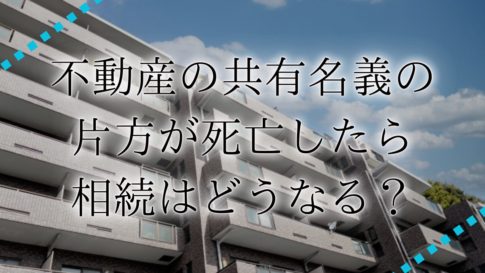「相続税対策として生前贈与をしたい」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
生前贈与には相続財産を減らす効果がありますが、贈与税は相続税より税率が高いなど、注意すべき点があります。
この記事では、贈与税の非課税制度や生前贈与のメリットとデメリット・注意点などについて解説していますので、ぜひ参考になさってください。
目次
生前贈与と相続、どちらがよい?

生前贈与とは、将来被相続人となり得る人物が存命中に、他者へと財産を譲り渡す行為です。
生前贈与では贈与する側を贈与者、受け取る側を受贈者と言い、死亡後に相続する財産を少なくできるため、相続税を節税できる点が魅力と言えます。
ただし贈与税の課税対象となるため、必ずしもお得に財産を承継できるわけではありません。
以下を参考に、相続をしたほうがよいケースもあることを理解しておきましょう。
生前贈与したほうがよいケース
継続した家賃収入や価値上昇が見込める物件、株式投資、投資信託などの財産がある場合は、生前贈与をしたほうがよいでしょう。
なぜなら相続税は相続開始時点の財産価値に基づいて決まるため、評価額の低い段階で贈与しておけば、より高い節税効果が得られるからです。
またアパートなどの賃貸物件は、所有年数分の収益が財産として蓄積されていくため、早いうちに贈与することで、相続税の課税対象となる財産を減らせます。
加えて、贈与者が会社や事業を経営している場合も生前贈与がおすすめです。
自社株や事業用の不動産を相続すると、複数人の相続人で分割されてしまい、場合によっては会社の存続に影響を及ぼす恐れがあります。
なかでも株式は会社の方針や意思決定に大きく関与するため、必ず後継者へと引き継がれるようにしておきましょう。
さらに詳しくは後述しますが、子どもや孫が複数人いるなど財産の承継先が多岐にわたるケースも、生前贈与は有効です。
相続したほうがよいケース
一方、財産の評価額が相続税の基礎控除額を超えないケースでは、そもそも相続税の申告・納税をする必要もないため、相続したほうがよいでしょう。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算され、たとえば法定相続人が2人の場合は4,200万円が控除されます。
また配偶者が相続する場合は申告は必要なものの、1億6,000万円以内または法定相続分相当額以下の財産は課税対象になりません。
このように相続税が課税されないケースでは、相続税対策を目的とする生前贈与を行うメリットがないため、どれくらいの財産があり、誰に分け与えるのか把握したうえで承継方法を決めるようにしましょう。
また贈与税の特例や控除を受けるには、受贈者が子や孫などの直系卑属、配偶者であることが原則です。
贈与税は税率が相続税よりも高めに設定されているため、これらの受贈者がいない場合、生前贈与はあまりおすすめできません。
生前贈与で相続税対策をするメリット

生前贈与には、先述のケースで活用できる以外にもさまざまなメリットがあります。
相続財産を減らせる
生前贈与で得られる最大のメリットは、冒頭でも述べた通り、相続財産を減らせることです。
生きているうちに財産を引き渡すことで相続時の財産が減れば、相続税の課税額も下がります。
たとえば現金1,000万円のうち200万円を生前贈与しておけば、残りの800万円に相続税が課せられるということです。
存命中の所有財産は少なくなるものの、次世代に可能な限り多くの財産を残し、税金の負担を軽減するために活用できるでしょう。
贈与する相手を自由に選べる
生前贈与では、贈与者が特定の人に対して自由に財産を与えることができます。
相続の場合は民法または遺言書、遺産分割協議によって相続人が決められますが、生前贈与なら確実に贈与したい相手に財産が渡ったことを確認できます。
また、親族以外の人物を受贈者に指定することも可能ですが、後述する遺留分の請求がされる可能性もある点には注意してください。
贈与者が贈与のタイミングを自由に決められる
財産の贈与時期を自由に決められることも、生前贈与を行うメリットの一つです。
相続ではいつ財産を承継するのかわからず、被相続人が亡くなるまで手続きはできませんが、生前贈与であれば進学や結婚、住宅購入などの好きなタイミングで贈与できます。
また土地や不動産など、将来価値が上がりそうな物件を受け継ぎたいときにも有効です。
相続トラブルを事前回避できる
生前贈与は存命中に誰にどの割合で財産を与えるか決められるため、相続時のトラブルを回避できます。
遺言書でも財産の分割方法を指定できますが、場合によっては内容を不服とする相続人が現れて意見がまとまらず、遺産分割が滞ったり調停に発展したりする可能性もあるでしょう。
特に相続人同士の仲がよくない場合は、あらかじめ自分がどのように財産を分割したいのか家族に話し、納得してもらうことが望まれます。
生前贈与のデメリットと注意点
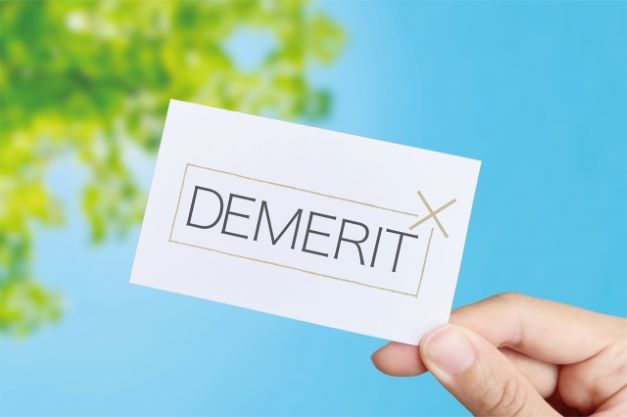
生前贈与には、デメリットも存在します。
税務署に否認される可能性がある
財産を承継する方法や状況によっては、税務署に生前贈与として認められない可能性があります。
そもそも生前贈与とは、贈与者と受贈者双方の合意のもとで成立するため、受け取った人が財産をもらったと認識し、自由に管理・使用できる状態になっている必要があります。
そのため、たとえば親が子ども名義の口座に入金していても、子どもがその事実を知らなかったり親が管理していたりする場合は、贈与とは認められません。
また口頭で生前贈与があったことを伝えても立証は難しいため、手続きの度に贈与契約書を作成して、記録に残しておくことが大切です。
定期贈与とみなされる可能性がある
生前贈与で相続税対策をする際は、数年にわたり財産を分割して贈与することが一般的です。
ただし毎年一定の額を贈与し続けていると定期贈与とみなされ、贈与税を支払わなければならない可能性があります。
具体的には100万円を10年間贈与した場合、贈与を開始した年に「定期金に関する権利」が与えられたとして、総額の1,000万円に対して贈与税が課せられます。
定期贈与とみなされないための対策としては、同じ金額を贈与し続けないこと、1回の贈与ごとに贈与契約書を作成することなどが有効です。
自分にどれくらいの財産があり、何年かけてどのような割合で承継するのか決めたうえで生前贈与をしましょう。
贈与者の生活を圧迫してしまう可能性がある
生前贈与は生きているうちに行うため、贈与を行えば行うほど贈与者の財産は減ります。
多くの財産を分け与えてしまうと、今後の生活を圧迫してしまう可能性があるため、あくまでも生活に影響のない範囲内で行うことが大切です。
死亡前3年以内の贈与には相続税が課せられる
生前贈与に関する税制には、被相続人の死亡前3年以内に行われた贈与には相続税が課せられる「生前贈与加算」という制度があります。
そのため、死期が迫っているとわかっている場合や高齢である場合、相続税対策として生前贈与をするのはおすすめできません。
ただし、加算されるのは法定相続人に対する贈与分のみのため、相続人ではない孫などへの贈与は対象外です。
また相続税の課税金額には贈与時の財産評価額が反映されることから、相続時に不動産や投資信託の価値が上昇していても、大きく損をすることはありません。
なお、生前贈与加算に関しては2023年度の税制改正により、2024年1月1日以降の贈与は加算期間が死亡前3年以内から「死亡前7年以内」に延長されます。
被相続人が亡くなる前3~7年以内に行われた贈与については、100万円を差し引いた額が相続財産に加算されるようになるため、注意してください。
知ってた!?贈与税の非課税制度

財産承継の推進を狙いとして、贈与税にはざまざまな特例や控除があります。
暦年贈与で年間110万円までは非課税枠
生前贈与には、受贈者が1月1日~12月31日までの1年間で受け取った財産額に応じ、贈与税が課せられる「暦年課税制度」があります。
暦年課税では110万円の基礎控除が受けられ、年間の贈与額が総額110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
たとえば孫5人に年間110万円ずつを10年にわたって与えた場合、合計5,500万円が非課税で贈与できるうえに、相続時の財産を大幅に減らせるという計算です。
この仕組みを利用した贈与方法を「暦年贈与」と言い、長期的に利用していくことで、より高い節税効果が期待できるでしょう。
相続時精算課税制度で2,500万円までは非課税
相続時精算課税制度とは、2,500万円までの生前贈与に対して非課税枠が利用できる制度で、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に財産を贈る際に選択可能です。
この制度を利用すると、非課税枠の2,500万円を超えた財産のみに20%の贈与税が課せられ、相続発生時に、すでに贈られた贈与財産と相続財産を合わせて税額を計算します。
相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。
居住用不動産を配偶者間で贈与した場合は2,000万円まで控除可能
贈与税には配偶者控除もあり、婚姻関係が20年以上の配偶者間で居住用不動産または居住用不動産の取得を目的とする資金の贈与が行われた場合、最大2,000万円まで控除されます。
配偶者控除の特例は、暦年課税と併用可能で相続税対策に有効ですが、同じ配偶者からの贈与は一生に一度しか適用を受けられない点には注意が必要です。
子どもや孫への教育資金の一括贈与なら1,500万円まで非課税
父母または祖父母から子どもや孫などの直系卑属へと教育資金の一括贈与があった場合、1,500万円までは非課税です。
ただし制度の適用には、受贈者が30歳未満、かつ贈与を受ける前年の所得が1,000万円以下でなければなりません。
また受贈者が30歳を迎えた時点で在学していなかったり、贈与者が死亡したりした場合、教育資金に使用されていない残額は、贈与税・相続税の課税対象となる可能性があります。
他にも学習塾などの学校以外に使われる資金は上限500万円、子や孫名義の口座に入金する、教育資金非課税申告書や領収書を発行するなどの点に注意しましょう。
父母や祖父母からの住宅取得資金贈与は一定要件で1,000万円まで非課税
父母や祖父母などの直系尊属から住宅資金の贈与を受ける際には、住宅取得等資金の非課税制度が活用できます。
この制度は、両親や祖父母などの直系尊属から住宅取得のための資金を贈与された場合、一定の要件を満たせば最大1,000万円が非課税となる制度です。
住宅や土地の生前贈与や相続時精算課税制度・住宅取得等資金の非課税制度の概要や要件などについて詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。
▼相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税制度の概要について紹介
贈与税はどうやって計算する?

先述の通り、生前贈与を行う際には、贈与税と相続税を試算して最善の節税方法を考える必要があります。
以下の解説を参考に試算してみましょう。
贈与税の計算方法
先ほども述べたように、特例を除き贈与税の基礎控除額は1人の受贈者につき年間110万円です。
よって贈与税の課税対象となる金額は、次の計算式で求められます。
| 年間の合計贈与額-基礎控除額110万円=贈与税の課税対象となる金額 |
続いて次の計算式を使い、贈与税額を出しましょう。
| (贈与税の課税対象となる金額×税率)-控除額=贈与税額 |
税率と控除額は、課税対象となる金額が上がるほど高くなる傾向にあります。
また受贈者の年齢や贈与者との関係性によって異なる点も、注意しましょう。
具体的な数値は次の表を参照してください。
<18歳以上の直系卑属に贈与した場合の税率と控除額(平成27年以降の贈与)>
| 贈与税の課税対象となる金額 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | ‐ |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
なお、成人年齢が引き下げられる前の令和4年3月31日以前の贈与については、「20歳以上」が対象です。
<上記以外の者に贈与した場合の税率と控除額(平成27年以降の贈与)>
| 贈与税の課税対象となる金額 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | ‐ |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
【相続税との違いは?】贈与税のほうが税率が高い
生前贈与による節税対策をしていくうえで、気になるのはやはり相続税との違いでしょう。
相続税の税率と控除額は、以下の通りです。
<相続税の税率と控除額(平成27年以降の相続)>
| 贈与税の課税対象となる金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ‐ |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
先に挙げた贈与税の表と比較すると、贈与税の税率のほうが高く設定されています。
節税のためとはいえ、安易に生前贈与を行なってしまうと、かえって支払う税金が多くなってしまうことに注意しましょう。
【必読】節税効果の高い贈与額について

生前贈与では、贈与税の基礎控除額である110万円以下で贈与するケースが一般的ですが、実は110万円以上を贈与したほうが節税できる可能性があることをご存じでしょうか?
ここからは、より高い節税効果が得られる贈与額について解説します。
贈与税と相続税の節税額の比較
以下の表は、年間の贈与額ごとに課せられる贈与税と相続税の節税額をまとめたものです。
なお、相続税の税率は20%とし、18歳以上の直系卑属に贈与した場合の贈与税で計算しています。
贈与税額については、前項の「贈与税の計算方法」を参照してください。
| 年間の贈与額 | 贈与税額 | 相続税の節税額 (年間の贈与額×0.2) |
節税効果 (相続税の節税額-贈与税額) |
| 110万円 | ‐ | 22万円 | 22万円 |
| 200万円 | 9万円 | 40万円 | 31万円 |
| 400万円 | 33万5,000円 | 80万円 | 46万5,000円 |
| 500万円 | 48万5,000円 | 100万円 | 51万5,000円 |
| 510万円 | 50万円 | 102万円 | 52万円 |
| 600万円 | 68万円 | 120万円 | 52万円 |
| 800万円 | 117万円 | 160万円 | 43万円 |
| 1,000万円 | 177万円 | 200万円 | 23万円 |
年間で110万円を贈与した場合、基礎控除額の範囲内であるため贈与税はかかりません。
さらに110万円の相続財産を削減する効果があるため、110万円×0.2=22万円の相続税を節税できます。
対して年間400万円の贈与を行なった場合は、基礎控除額110万円を差し引いた290万円に対して贈与税が課税されます。
課税対象となる金額が400万円以下であれば、贈与税の税率は15%、加えて10万円の控除が受けられるので、290万円×0.15-10万円=33万5,000円の贈与税がかかる計算です。
相続税は400万円×0.2=80万円減額でき、総合的に見れば80万円-33万5,000円=46万5,000円の節税効果が得られるでしょう。
2つのケースを比べてみると、年間110万円以上贈与したほうが節税につながる場合があることがわかります。
年間510万円の贈与が最も節税効果が高い!
年間510万円の贈与では、基礎控除を除いた400万円が贈与税の課税対象となり、15%の税率がかけられます。
10万円の控除額も差し引くと、400万円×0.15-10万円=50万円の贈与税が課税される計算です。
相続財産は510万円減るため、510万円×0.2=102万円の相続税が節税できます。
節税効果は102万円-50万円=52万円となり、その年だけでみれば、もっとも節税効果の高い贈与額であると言えるでしょう。
生前贈与以外にもさまざまな相続税対策がある
相続税対策には、生前贈与以外にも生命保険の非課税枠の活用や養子縁組の活用など、さまざまな方法があります。
幅広い知識を得たうえで、自身にとって最適な相続税対策を選択するとよいでしょう。
相続税対策についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。
相続特別受益に該当する生前贈与金は相続財産に含める

民法では、相続人間の公平を図る目的で「相続特別受益に該当する遺贈・贈与は相続財産に合算する」と定められています。
生前贈与も例外ではなく、相続税対策をするうえで押さえておかなければなりません。
【はじめに】相続特別受益とは
相続特別受益とは、相続人が被相続人から受けた特別な利益のことを言います。
相続発生時の財産だけで遺産分割をすると生前に財産を受け取った人が得をしてしまうため、場合によっては相続人同士のトラブルになりかねません。
そのため、遺贈などの特別な利益(相続特別受益)を合わせたうえで遺産分割を行うことが定められており、この規定を「特別受益の持ち戻し」と言います。
相続特別受益に該当する生前贈与は結婚に関する贈与と生計に関わる贈与ですが、時代背景や被相続人の経済状況などによって該当範囲が変化する点には注意が必要です。
相続特別受益について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。
相続特別受益で遺留分を侵害されたときの対処法
相続特別受益で遺留分を侵害されていると判明した場合は、遺留分侵害額請求ができます。
遺留分とは
遺留分とは、亡くなった被相続人の直系尊属または直系卑属、配偶者にあたる法定相続人が相続できる最低限の財産割合です。
直系尊属は父母や祖父母などの自分より前の世代、直系卑属は子どもや孫など後の世代を指し、兄弟姉妹や甥姪は含まれません。
遺留分侵害額請求を行う
遺留分侵害額請求とは、不平等な財産分割により遺留分が侵害された際、該当する財産を贈与された者に対し、現金での遺留分の返還を求めることです。
2019年7月の改正民法により「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へと名称変更され、それまで遺産そのものを返してもらう権利であったものが、「侵害分に相当する金銭で取り戻す権利」となりました。
遺留分侵害額請求をする場合、まずは当人同士の話し合いを行い、合意が得られない場合は調停、訴訟で解決します。
遺留分侵害額請求で得られる効果
遺留分侵害額請求をすることで、生前贈与や遺贈によって侵害された自分の遺留分を現金で取り戻すことができます。
また侵害者の受けた生前贈与が相続特別受益であった場合は、相続開始日からさかのぼって10年以内の贈与が請求の対象です。
相続の遺留分について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。
生前贈与で現金手渡しはOK?

生前贈与を行う際、現金手渡しで贈与したいと思う方もいらっしゃるでしょう。
ここからは、現金手渡しによる贈与は問題ないのか、リスクと注意点も含めて解説します。
現金手渡しの生前贈与は避けたほうがよい
年間の贈与額が110万円以下なら非課税だからといって、現金手渡しでの贈与はおすすめできません。
ケースによっては暦年贈与が認められず、贈与税が課される可能性があるからです。
先述したように、暦年贈与による相続税対策には、「定期金に関する権利」に触れてしまうリスクがあります。
税務署に定期贈与と判断されないためには、贈与契約書などに贈与の記録を残すのが望ましいですが、現金手渡しの贈与では証明することが困難です。
もし定期贈与とみなされた場合は、たとえ年間の贈与額が110万円以下であったとしても、贈与税が課税されることになるでしょう。
また、税務署には納税の義務を怠ったと疑われる人物に対し、銀行口座の記録を調査する権限があります。
贈与者、受贈者双方の口座から同額の出入金履歴があれば、さらに現金の使途なども含めた身辺調査が行うことも可能です。
脱税目的の生前贈与が明るみになった場合は、本来非課税だった贈与税の支払いが必要になるだけでなく、罰金や刑罰などのペナルティが科せられる可能性もあります。
生前贈与を現金手渡しで行なった場合の贈与税はどうなる?
生前贈与を現金手渡しで行なった場合も、暦年課税に基づいて贈与税が課税されます。
1月1日~12月31日の1年間での贈与金額が基礎控除額110万円以下の場合は、贈与税は発生しませんが、同期間で110万円以上の贈与があった場合は、贈与税の支払いが必要です。
ただし先述の通り、現金手渡しの贈与にはさまざまなリスクがあることを理解しておきましょう。
生前贈与に関する疑問やご相談は林商会にお任せください!
生前贈与は相続税対策の中でも比較的取り組みやすい方法ですが、メリットやデメリットをふまえて慎重に選択する必要があります。
曖昧な知識をもとに素人が判断してしまうと、適切な相続税対策を選択できず後悔する事態を招きかねません。
そのため、生前贈与に関する疑問や相続税対策に関するご相談は、正しい専門知識をもった専門家に依頼するのが安心です。
相続のプロ集団である林商会では、税理士・弁護士・司法書士・行政書士などが在籍して随時ご相談を承っており、きめ細やかな対応には定評があります。
まずは無料相談からお気軽にご連絡ください。
まとめ

生きているうちに相続財産を減らせる生前贈与は、相続税対策として有効です。
ただし生前贈与を行う際には、自分の所有する財産を把握したうえで非課税制度の活用を検討するなど、綿密な計画を立てていく必要があります。
場合によっては税理士や相続について詳しい専門家に相談し、適切な生前贈与を行なっていきましょう。