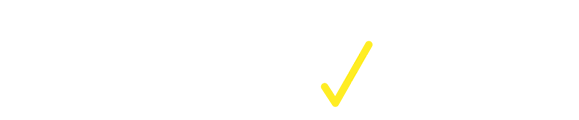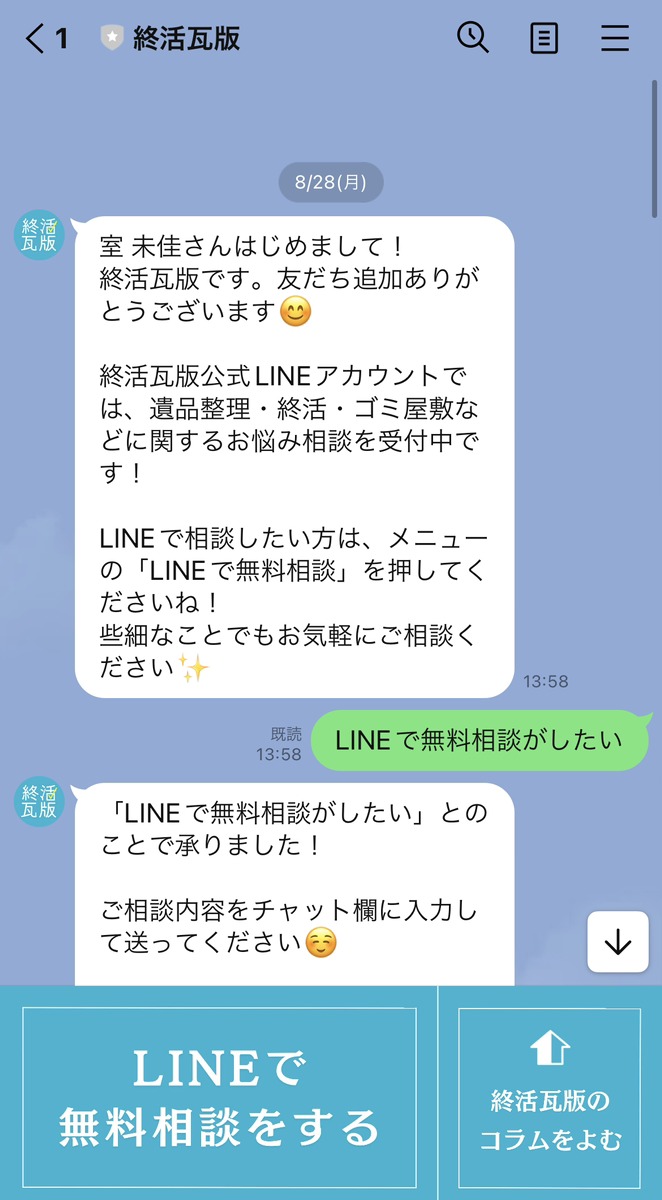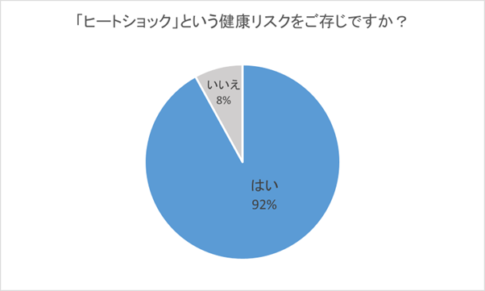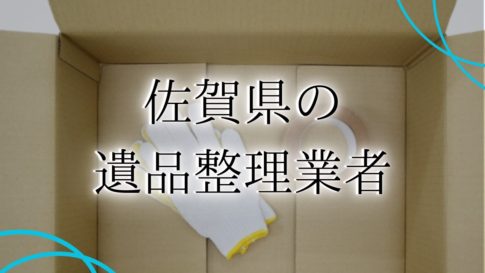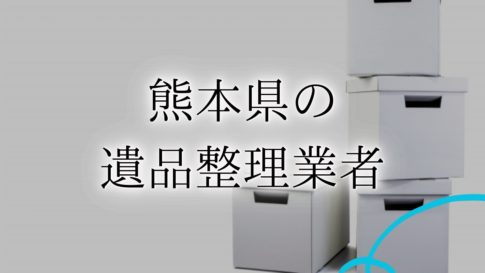相続が発生した際に最優先されるのは故人の意思、つまり遺言であるため、相続発生時にはまず遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書には、相続トラブルを防いだり相続税の申告をスムーズに行えるなどのメリットがありますが、作成の際には注意が必要です。
この記事では遺言書の作成方法や注意点のほか、遺言書がある場合の遺産相続について解説します。
目次
遺言書作成の方法は主に3つ

遺言書の主な作成方法は、次の3種類です。
|
まずは、上記の遺言書がどのようなものなのか、確認していきましょう。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書の内容を遺言者自身が手書きする方式の遺言です。
ここからは、自筆証書遺言の作成方法やメリット・デメリットを解説します。
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言は、次の要件に従って作成する必要があります。
|
自筆証書遺言を一人で作成するのが難しい場合は、弁護士などの専門家にサポートを依頼するとよいでしょう。
また、自筆証書遺言を作成する際は、次のポイントに注意が必要です。
|
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言を選ぶメリットは、次の通りです。
|
遺言書の保管場所を決められない場合は、法務局での保管が可能な自筆証書遺言書保管制度を利用するとよいでしょう。
ただし、自筆証書遺言には以下のようなデメリットもあるため、注意が必要です。
|
②公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が提示する遺言内容をもとに、公証人がパソコンで作成する方式の遺言です。
ここからは、公正証書遺言の作成方法やメリット・デメリットを解説します。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言を公証役場で作成する手順は、次の通りです。
|
公正証書遺言をスムーズに作成したい場合は、弁護士や司法書士などの専門家にサポートを依頼するとよいでしょう。
特に、弁護士に依頼すると相続トラブルにも対応してもらえるためおすすめです。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言のメリットは、次の通りです。
|
ただし、公正証書遺言を作成する際には、手数料や報酬を支払わなければなりません。
利用する際は、どの程度の費用が必要なのか、事前に調べておきましょう。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にした状態で、自身の遺言書の存在を公証役場に証明してもらう方式の遺言です。
ここからは、秘密証書遺言の作成方法やメリット・デメリットを解説します。
秘密証書遺言の作成方法
秘密証書遺言の作成手順は、次の通りです。
|
また、秘密証書遺言を作成する際は、遺言書の内容が曖昧にならないように注意しましょう。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
秘密証明遺言の主なメリットは、次の通りです。
|
ただし、秘密証書遺言には以下のようなデメリットもあるため、注意が必要です。
|
特別方式の遺言書もある
遺言書は、次のような特別方式で作成する場合もあります。
|
ここからは、上記の遺言書の作成方法を解説します。
一般危急時遺言
一般危急時遺言とは、病気や怪我などで遺言者の生命の存続が危ぶまれる場合に作成する遺言書です。
遺言者自身での記入が困難な場合は、口頭で伝えた内容を証人の1人に代筆してもらい、他の証人に署名してもらうことで作成可能です。
そのため、3人以上の証人が必要な点には注意しましょう。
また、作成日から20日以内に、遺言書を作成した人の居住地の家庭裁判所で確認手続きを行わねばなりません。
難船危急時遺言
難船危急時遺言は、飛行機や船などで生命に危機が迫っている場合に作成する遺言書を指します。
2人の証人が必要で、証人による代筆・署名も可能です。
一般危急時遺言と同様に、遺言書を作成した人の居住地の家庭裁判所で確認手続きが必要ですが、期限はありません。
一般隔絶地遺言
一般隔絶地遺言とは、伝染病などで隔離されている場合や災害などで交通手段が断たれている場合、服役中の場合に作成する遺言書を指します。
作成の際には、警察官と証人が1人ずつ立ち会う必要があり、遺言者が自筆しなければなりません。
また作成した遺言書には、遺言者と立会人の署名押印が必要ですが、家庭裁判所での確認は不要です。
船舶隔絶地遺言
船舶隔絶地遺言は、乗船中などで離陸している場合に作成する遺言書です。
搭乗時間が短い飛行機は、この遺言書には含まれません。
作成の際には、船長または事務員1人と2人以上の証人の立ち会いが必要で、遺言者が自筆しなければなりません。
また、作成した遺言書には、遺言者と立会人の署名押印が必要です。
遺言書がもつ効力とは?

ここからは、遺言書がもつ効力を解説します。
相続分の指定
遺言者は、遺言書で「誰にどのくらいの財産を相続させるのか」を決めたり、第三者に決定を委ねたりすることが可能です。
遺言書以外の方法での相続分の指定は認められておらず、遺言書がない場合は法定相続分に従わねばなりません。
また、相続分の指定には、遺言者の意思を自由に反映できるメリットがありますが、不公平な指定分割はトラブルになりかねないため注意が必要です。
相続分の指定について更に詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。
※内部リンク:指定相続
相続人の廃除
遺言者が特定の相続人への相続を望まない場合は、相続廃除制度を利用しましょう。
相続廃除制度を利用できるケースは、次の通りです。
|
ただし、相続廃除の対象は遺留分を請求できる相続人に限られており、被相続人の兄弟姉妹や甥姪には適用できない点には注意が必要です。
遺産分割方法の指定・分割の禁止
遺言者は遺言書で遺産の分割方法を指定できるほか、相続の開始から5年未満であれば、遺産分割を禁止できます。
遺産分割で相続トラブルに発展する可能性がある場合は、相続人同士が冷静に手続きを進めるためにも、遺産分割方法の指定や分割の禁止を遺言書に記載しておくとよいでしょう。
相続財産の遺贈
遺言者は、法定相続人以外の第三者や団体に相続財産を遺贈できます。
ただし、遺贈する財産が不動産の場合は登記手続きを行わねばならず、農地の場合は、農業委員会や都道府県知事の許可が必要です。
遺贈と相続の違いに関する情報を知りたい方は、以下の記事をお読みください。
内縁の妻との間に生まれた子どもの認知
婚姻関係にない女性との間に子どもがいる場合は、遺言書に親子だと正式に認める内容を記載すれば、当該の子どもに相続権が与えられます。
遺言書で子どもを認知する場合は、次のポイントに注意しましょう。
|
後見人の指定
遺言者の子どもが未成年で、遺言者の死亡によって親権者がいなくなる場合は、後見人を指定しておけば、残された子どもの養育や財産管理を任せられます。
ただし、次の条件に当てはまる場合は後見人として認められません。
|
また、後見人を指定する際は、次のポイントに注意しましょう。
|
相続人相互の担保責任の指定
遺産相続後に欠陥などの問題が発生した場合、相続人は他の相続人に担保責任(不適合責任)を問い、損害賠償請求が可能です。
遺言者は、この相続人相互の担保責任を指定することで、資力のない相続人の担保責任を軽減または免除できます。
遺産相続後に発生する問題の主な具体例は、次の通りです。
|
ただし、あまりにも不公平な担保責任の指定をすると遺留分侵害額請求が発生する恐れもあるため、注意しましょう。
遺言執行者の指定・指定の委託
遺言書には、遺言執行者の指定や指定を委託できる効力もあります。
遺言執行者が行う主な手続きは、次の通りです。
|
また、遺言執行者に指定したい人が身近にいない場合は、弁護士や司法書士など信頼できる専門家に依頼しておくと安心です。
「遺言執行者と相続人は同一でもよいの?」と気になる方は、以下の記事をお読みください。
※内部リンク:遺言執行者 相続人 同一
遺言書作成の注意点

ここからは、遺言書を作成する際の注意点を解説します。
相続財産を把握して相続税が発生するかを確認する
遺言書を作成する際は、相続財産を把握して、相続税が発生するのか事前に確認しておきましょう。
相続税の対象となる主な財産は、次の通りです。
|
また、相続税が発生するかどうかは、相続財産の相続税評価額に応じて判断されます。
相続税の基礎控除額の算出方法は、次の通りです。
| 相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の人数) |
相続財産の相続税評価額の合計が相続税の基礎控除額を下回る場合は、相続税が発生しません。
また、相続税の基礎控除額を上回る場合でも、生命保険の非課税枠が適用されて相続税が発生しないケースもあります。
自筆証書遺言は手軽だけど無効になる恐れも!
自筆証書遺言は遺言書を気軽に作成できる方式ですが、次のようなケースでは、遺言書が無効になる恐れもあります。
|
相続トラブルに発展させないためにも、自筆証書遺言を作成する場合は、細心の注意を払いましょう。
また、自筆証書遺言として認められるためには、次の要件をすべて満たさなければなりません。
|
自筆証書遺言は、必ず遺言者本人が手書きで作成しなければならないため、病気などで自筆が困難な場合は、公証人による代筆が可能な公正証書遺言を利用するのもおすすめです。
遺留分を考慮する
遺言書を作成する際は、相続人の遺留分も考慮しましょう。
遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保できる制度で、次の対象者に適用されます。
|
遺言書の内容は自らの意思に従って決定できますが、遺留分を侵害する内容で遺言書を作成してしまうと、相続トラブルに発展してしまう恐れがあります。
遺言書を作成する際は、すべての相続人が納得できる内容になるように配慮しましょう。
相続の遺留分に関する情報について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。
共同の遺言書は作成できない
遺言書を共同で作成することは法律で禁じられており、たとえば夫婦で同じ内容の遺言を残したい場合などは、個々に遺言書を作成する必要があります。
相続トラブルに発展させないためにも、同一内容の遺言書を作成する場合は、作成者同士でしっかりと話し合っておきましょう。
遺言書が無効になるケースもある!
ここからは、自筆証書遺言や公正証書遺言が無効になるケースを解説します。
自筆証書遺言が無効になるケース
次のようなケースでは、自筆証書遺言が無効になる可能性があります。
|
遺言能力がないと判断されるのは、認知症などの判断力が低下する疾患を発症している場合や、15歳未満の場合です。
ただし、症状が回復して正常な判断ができると診断された場合は、2名以上の医師が立ち会って作成されたものであれば、遺言書として認められます。
公正証書遺言が無効になるケース
次のようなケースでは、公正証書遺言が無効になる可能性があります。
|
加えて、次の条件に当てはまる場合は証人として認められないため、公正証書遺言が無効になる恐れがあります。
|
遺言書がある場合の遺産相続について

ここからは、遺言書がある場合の遺産相続で注意すべきポイントを解説します。
【勝手な開封はNG!】自筆証書遺言と秘密証書遺言書は検認が必要
自筆証書遺言や秘密証書遺言を利用する場合は、家庭裁判所の検認が必要です。
検認とは、相続人に遺言書の存在を示して内容を確認する手続きで、検認前に勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の罰金が科される可能性があります。
遺言書を開封する際は、家庭裁判所からの検認を受けているか事前に確認しておきましょう。
また、家庭裁判所の検認に必要な書類は、次の通りです。
|
公正証書遺言の開封方法
公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きをせずに開封できる方式で、遺言執行者であれば、原本の写しによる内容の確認が可能です。
遺言執行者は、弁護士や司法書士、信託業者などの専門家に依頼するケースが多い傾向にあります。
遺言執行者がいる場合は相続手続きを任せる
遺産相続には、相続に関する正しい知識が必要です。
弁護士や司法書士など相続に詳しい遺言執行者がいる場合は、相続手続きを任せましょう。
特に遺言執行者が弁護士の場合は、相続トラブルが発生した場合にも対応してもらえるため、安心です。
こんな場合の遺産相続はどうする?

遺産相続時に問題が発生した場合は、どのように対処すればよいのでしょうか。
ここからは、遺産相続に関するさまざまな問題の解決方法をご紹介します。
遺言書に記載されていない財産がある場合
遺言書に記載されていない財産は、遺言書の効力が及ばないため、相続人全員で遺産分割協議を行い、手続きを進める必要があります。
また協議中に相続トラブルに発展しそうな場合は、相続に詳しい専門家に遺産分割協議書の作成を依頼するのもおすすめです。
次のポイントを参考に、依頼先を検討しましょう。
|
遺言書の記載内容に納得できない場合
遺言書の記載内容に納得できない場合は、遺言内容とは異なる遺産分割が可能ですが、相続人全員での話し合いと遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議書には相続人全員の実印が必要で、その内容に納得できない場合は、遺産分割調停を申し立てて争わなければなりません。
遺留分を侵害されている場合
遺留分を侵害されている場合は、法的に保障されている一定の相続分を請求できる遺留分侵害額請求を行いましょう。
ただし、遺留分侵害額請求は、次の期限を過ぎると失効してしまうため注意が必要です。
|
遺言書が無効の場合
遺言書が無効の場合は、相続人同士で遺産分割協議を行う必要があります。
相続トラブルに発展させないためにも、相続人全員が納得できるまで話し合いましょう。
また、遺産分割協議によって取得する遺産や相続税が減る場合は、遺言書が無効と認められた日の翌日から4か月以内に、更正の請求を行う必要があります。
相続の遺言書に関する疑問やご相談・作成依頼は林商会にお任せください
遺言書は亡くなった人の意思を反映するため、相続の際に最優先されます。
子どもの認知などの効力をもつ一方で、遺言書の作成方法や遺言内容には、正しい知識が必要です。
誤った作成方法で遺言書が無効にならないようにするためにも、専門家への依頼や相談をおすすめします。
相続のプロ集団である林商会には弁護士・司法書士・行政書士・税理士などの専門家が在籍中で、お悩みや疑問に寄り添った真摯な対応が自慢です。
まずは無料相談から、お気軽にご連絡ください。
まとめ
遺言書の作成方法は、自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類で、それぞれにメリット・デメリットがあります。
なかでも、公証役場に原本が保管される公正証書遺言は、公証人が作成するため信用性が高く、遺言書の偽造や破棄、変造のリスクが少ない方式です。
相続トラブルを未然に防ぐためにも、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら、相続人全員が納得できるように配慮して、遺言書を作成しましょう。