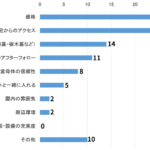死亡した人の口座は、原則として遺産分割が終わるまで凍結されます。
相続預金は凍結解除を行わなければ引き出せないため、遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用するのも一つです。
本記事では、相続預金を引き出す方法として、相続預金の払戻し制度や凍結解除の方法を中心に解説します。
目次
死亡した人の相続預金を引き出す方法

死亡した人の相続預金は、遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用すれば引き出せます。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは、遺産分割を終えていなくても相続人の生活費や葬儀費用の支払いが必要な場合に、死亡した人の相続預金から一定の金額を引き出せる制度です。
具体的には、家庭裁判所の判断が不要な制度と必要な制度の2つに分かれます。
家庭裁判所の判断が不要な制度
令和元年7月1日より、相続人の生活費や葬儀費用を確保するために「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が制定され、遺産分割協議の前でも死亡した人の相続預金を引き出せるようになりました。
引き出せるのは「死亡日現在の預貯金額×3分の1×各法定相続分」の金額です。
なお、同一の金融機関から引き出せる上限は「150万円」と定められています。
家庭裁判所の判断が必要な制度
仮払い制度を利用して引き出せる金額では必要金額に届かない場合は、裁判所に仮分割の仮処分の申し立てを行い、認められれば「相続預金の全部または一部」を引き出すことができます。
「預貯金債権の仮分割の仮処分」の申し立てが認められる要件は、以下の通りです。
|
凍結された預金の口座を解除する方法

死亡した人の凍結された口座を解除する際は、以下の手順で手続きを進めましょう。
1.銀行に凍結解除を依頼する
まずは死亡した人の口座がある銀行に凍結解除を依頼しましょう。
銀行から具体的な手続きや必要な書類などの案内があります。
2.手続きに必要な書類を準備する
口座の凍結解除をするために必要な書類を準備します。
必要な書類は遺産分割の状況によって異なるため、次章の内容を確認してください。
なお、銀行によって異なる場合もある点に注意が必要です。
3.銀行に各種書類を提出する
銀行に各種書類を提出すれば、凍結解除の手続きは完了します。
なお、提出時に相続人全員の実印の捺印が必要です。
手続きが完了してから2週間前後で凍結が解除され、相続預金を引き出せます。
凍結解除の手続きに必要な書類一覧

凍結されている相続預金の解除に必要な書類は、遺産分割の状況によって異なります。
遺言書がある場合
|
遺言執行者が選任されている場合ば、遺言執行者の選任審判書謄本も必要です。
遺言書がなく遺産分割協議書がある場合
|
遺産分割協議書には、すべての法定相続人の署名と捺印が必要です。
遺言書も遺産分割協議書もない場合
|
金融機関によっては、遺言書も遺産分割協議書もない場合は相続凍結ができない可能性がある点には注意が必要です。
死亡した人の預金をおろしても罪ではない

死亡した人の家族や親族は、死亡した人の預金をおろしても罪ではありません。
「親族相盗例」という刑法上の特例により、刑事上では家族間での窃盗等は罪に問われないためです。
ただし、他の相続人の相続分までおろしてしまうと民事上では罪になる可能性があります。
また、相続人の間でトラブルが起こりかねないため、注意が必要です。
相続預金に関するよくあるトラブル
相続預金に関するよくあるトラブルを紹介します。
遺産分割前に相続分以上の金額を引き出した
相続分の範囲内での引き出しであれば、他の相続人も納得できるかもしれませんが、遺産分割前に相続分以上の預金を引き出すと、トラブルになりがちです。
遺産分割前は実際に自分が相続する金額は明確になっていないため、引き出す際は必要最小限にとどめておきましょう。
使途を明確に説明できない
預金の使途がはっきりしない場合、「個人的に使ったのではないか」など他の相続人から疑いをかけられてしまうかもしれません。
遺産分割前に預金を引き出した際は、引き出した目的、使途を他の相続人に説明する必要があります。
|
など、被相続人のために使ったことがわかるように、領収書や明細などの記録を残しておきましょう。
引き出したことを隠していた
「引き出していたことを話すと批判されるのではないか」と考えて、凍結前の口座からお金を引き出したことを隠してしまうのは賢明ではありません。
遺産を黙って引き出したことが後から判明すると他の相続人からの心象が悪く、トラブルに発展してしまいかねません。
遺産分割前に預金を引き出した場合には、そのことを早めに他の相続人に報告しましょう。
生前からできる!口座の凍結に備えた事前対策

銀行預金を相続するためにはさまざまな手続きや書類が必要で、手間や時間がかかります。
そのときになって慌てることがないように、生前から準備を進めておきましょう。
銀行預金の一覧表を作る
預金を持っている銀行口座を一覧表にしておくと、遺された家族がスムーズに相続手続きを行うことができます。
以下のような口座情報をまとめておけば、家族が一つひとつ口座を探して確認する手間が省けるでしょう。
|
銀行口座をできるだけ統一しておく
複数の銀行に口座を持っていると、銀行ごとに口座の凍結・解除手続きを行わなければなりません。
最小限の銀行口座に統一しておけば、手間や時間を減らせます。
また、何十年も前に開設して存在を忘れている口座があるかもしれません。
高齢になると忘れやすくなったり認知症を患ったりする可能性が高いため、早めに銀行口座を整理しておくと安心です。
遺言書を作成する
遺言書がない場合は遺産分割協議が必要になり、協議がまとまるまでに時間がかかったり相続人同士のトラブルに発展したりする可能性もあるでしょう。
口座預金を含めた相続をスムーズに進めるためには、遺言書の作成をおすすめします。
亡くなった人の銀行口座を放置したらどうなる?

銀行口座の相続手続きは、提出書類が多いため面倒に感じる人も多いでしょう。
亡くなった人が持っていた銀行口座の凍結や解約の手続きをしないまま放置したら、どうなるのか、詳しく見ていきましょう。
預金を引き出されてしまう
口座が凍結されていない状態のままで放置していると、通帳やキャッシュカード、暗証番号があれば誰でも入出金できてしまいます。
そのため、相続の話し合いがまとまっていない段階でも、遺産を守るため早めに口座を凍結しておくと安心です。
相続関係が複雑になってしまう
遺言書があれば、銀行口座の相続手続きは相続する本人や遺言執行者が単独で行うことができます。
しかし、遺産分割協議で相続が決まった場合、銀行口座の相続にはすべての相続人の戸籍や実印が必要です。
また、相続手続きをしないまま長い期間放置してしまうと、相続人の中で亡くなる人も出てきます。
亡くなった人が持っていた相続権はその相続人へと移るため、時間が経過するほどに相続人が増えてしまい、手続きがどんどん複雑になってしまうのです。
休眠口座になってしまう可能性がある
2009年以降、入出金や振り込み、口座振替などが行われないまま10年以上経過した口座は「休眠口座」として「預金保険機構」が管理することになりました。
預金保険機構へと移った口座は、払い戻しの際に通常よりも煩雑な手続きが必要です。
また、最後の利用が2008年以前の口座は、預金保険機構に移されることがない代わりに、時効によって払い戻し請求権がなくなることもあります。
時効完成の時期は、以下の通りです。
| 銀行口座 | 最後に利用してから5年 |
| 信用金庫などの口座 | 最後に利用してから10年 |
相続預金の疑問や相談は林商会にお任せください!
死亡した人の相続預金を引き出す行為は必ずしも違法ではありませんが、相続人同士のトラブルにつながりやすいため、専門家に相談すると安心です。
相続のプロ集団である林商会には、税理士・弁護士・司法書士・行政書士・相続診断士など相続の専門家が在籍しています。
正しい知識と豊富な経験をもとに、お悩みに丁寧に寄り添って最善の解決策をご提案しますので、安心してご相談ください。
まずはお気軽に、無料相談からご連絡をお待ちしています。
まとめ
亡くなった人の預金を引き出すことは法律的には可能です。
しかし、他の相続人との間でのトラブルにつながる可能性があるため、ルールを守り他の相続人が納得できる形で引き出すことが重要です。
亡くなられた方のためにも、相続人同士がスムーズにに相続を進められるよう、適切な手順を踏んで預金引き出しを行いましょう。