親の土地や不動産を相続したらどのような税金がかかり、どのように対策できるのか、お悩みの方は多いのではないでしょうか。
土地や不動産を相続する際には相続税がかかりますが、正しく把握するためには評価額を計算する必要があります。
この記事では、相続税評価額の計算方法のほか、小規模宅地等の特例など節税対策に有効な特例や控除についても解説します。
目次
【はじめに】土地や不動産を相続したら、どんな税金がかかる?

土地や不動産に相続が発生した場合にかかる税金を、パターン別に解説します。
<相続したらかかる税金>登録免許税と相続税
土地や不動産を相続した場合は、登録免許税と相続税の2種類の税金がかかります。
登録免許税とは、土地や不動産の所有権移転登記をする際にかかる税金で、計算方法は「固定資産評価額×0.4%」です。
相続税は財産を相続した人に課される税金で、相続した財産の金額が一定額を超えた場合に課税されます。
<所有しているとかかる税金>固定資産税
土地や不動産を相続し、そのまま所有する場合は固定資産税が課税され、地域によっては都市計画税を支払う必要があります。
ただし、固定資産それぞれの課税標準額の合計が以下の金額に満たない場合に、固定資産税と都市計画税の2つは課税されません。
|
なお、固定資産税は基本的に「 課税標準額×税率1.4%」、都市計画税は「 課税標準額×税率0.3%」で計算できます。
<売却したらかかる税金>所得税と住民税
相続した土地や不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合は、所得税や住民税などがかかります。
譲渡所得は「譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除」で算出可能です。
土地(不動産)にかかる相続税の基礎知識
にかかる相続税.jpeg)
以下では、土地(不動産)を相続する手続きの流れや相続税がかからないケース、相続税の計算方法について詳しく解説します。
土地(不動産)を相続する手続きの流れ
土地(不動産)を相続する際は、さまざまな手続きを期限内に行う必要があります。
具体的な期限と手続きの内容は以下の通りです。
| 期限 | 手続きの内容 |
| 期限なし(ただし早めの手続きがおすすめ) |
|
| 10日以内(国民年金は14日以内) |
|
| 3か月以内 |
|
| 4か月以内 |
|
| 10か月以内 |
|
| 1年以内 |
|
| 2年以内 |
|
| 3年以内 |
|
| 5年以内 |
|
期限内に手続きを行わないとペナルティを課せられることもあるため、手続きは先延ばししないように注意しましょう。
相続に関する具体的な手続き方法は以下の記事をご覧ください。
遺産総額が基礎控除額内なら相続税はかからない!
遺産総額が基礎控除額内であれば、相続税を支払う必要はありません。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出可能です。
基礎控除額と遺産総額を比較し、相続財産が基礎控除額を上回っていない場合は、相続税の支払いと申告は必要ありません。
ただし、申告が不要だと思っていても、実際は財産の見落としや計算ミスで、遺産総額が基礎控除額を超えている場合もあります。
そのような場合は、相続税に加えて延滞税や加算税などが課せられてしまうことがあるため、相続税の申告が不要かどうかの判断は慎重に行いましょう。
相続税の基礎控除について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
相続税の計算方法と流れ
相続税の計算方法と流れについて、詳しく見ていきましょう。
遺産総額の計算
遺産総額の計算方法は、「課税対象になる財産-借入金・葬儀費用-基礎控除額-非課税枠」です。
故人が所有していた現金預貯金や株式、不動産などすべての財産を足し合わせ、そこから借入金や基礎控除額などを引いていきます。
なお、生命保険金と退職金も相続税の課税対象となるため、遺産に含めるのを忘れないように注意しましょう。
ただし、生命保険金と退職金には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」で算出した額は非課税です。
相続税の総額を計算
相続税の総額は、相続人全員の算出税額を合算した額です。
各相続人の算出税額は、「課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分×税率-控除額」で求められます。
実際の取得割合に応じて税額を計算
相続税の総額を各相続人が実際に取得する財産の割合に応じて分けます。
各相続人にかかる相続税の具体的な計算式は、「相続税の総額×按分(あんぶん)割合(各相続人が実際にそれぞれ負担する割合)」です。
【相続税を正しく把握するために】土地(不動産)の相続税評価額を計算しよう
の相続税評価額を計算.jpeg)
以下では、土地(不動産)の相続税評価額の概要と計算方法について解説します。
土地(不動産)の相続税評価額とは
土地(不動産)の相続税評価額とは、相続税や贈与税などを計算する際に基準となる課税価格のことです。
土地(不動産)の評価方法には、「倍率方式」「路線価方式」「簡便法」があります。
土地の評価方法
以下では、土地の評価方法について詳しく解説します。
倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域で用いられる評価方法です。
その土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけると、土地の評価額が求まります。
なお、倍率は地域によって異なり、国税庁のホームページに掲載されている「路線価図・評価倍率表」で確認可能です。
路線価方式
国税庁によって路線価が定められている地域(市街地や住宅地など)は、路線価方式で土地の評価額を求めます。
路線価は道路ごとに定められており、その道路に面した土地は「路線価×面積(m²)×補正率」で評価額を算出可能です。
簡便法
簡便法は、市町村から送られてくる「固定資産税納税通知書(課税明細書)」を使用して、土地の相続税評価額の概算を算出する方法です。
「固定資産税評価額÷0.7×0.8」で相続税評価額を概算できます。
ただし、あくまでも目安にすぎないため、参考程度にとどめておくようにしましょう。
土地の形状がいびつな場合
形状がいびつな土地を「不整形地」と呼び、正方形や長方形で平坦に整えられている整形地よりも需要が少ないため、最大4割まで相続税評価額の減額が認められています。
不整形地の相続税評価額の具体的な計算方法は以下の通りです。
<手順>
|
整形地とした場合の1m²あたりの単価は、「路線価×奥行価格補正率」で算出可能です。
路線価と奥行価格補正率は、どちらも国税庁のホームページで確認できます。
地積区分は、地区区分と面積を、国税庁のホームページに載っている地積区分表に当てはめることで判断可能です。
かげ地割合は、対象となる不整形地を整形地だと想定して、その地積を「(想定整形地の面積−不整形地の面積)/想定整形地の面積」で計算します。
不整形地補正率は、ここまで算出した地積区分とかげ地割合を、国税庁の不整形地補正率表に当てはめることで算出可能です。
最後に、整形地であるとした場合の1m²あたりの価額に不整形地補正率をかけると、評価額が算出できます。
他人に貸している土地の場合
相続した土地が他人に貸している「貸宅地」である場合、借地権の評価額の分だけ安くなります。
なお、貸宅地の評価額は「自用地の評価額×(1-借地権の評価割合)」で算出可能です。
借地権の評価割合は、国税庁のホームページに掲載されている路線価図や評価倍率表で確認できます。
建物・家屋の評価方法
以下では、建物・家屋の評価方法について詳しく見ていきましょう。
建築後の建物
建築後の建物の相続税評価額は「固定資産税評価額×1.0」で算出できます。
つまり、建物の固定資産税評価額が相続税評価額です。
建築途中の建物
建物・家屋の建築途中に被相続人が亡くなってしまった場合、「費用現価(建築代金の総額 × 工事進捗率)× 70%」で計算した額が評価額です。
なお、建築代金の総額は、建物・家屋の建築が始まったときから相続開始日までにかかった建築費を指します。
建物をリフォームしていた場合
建物をリフォームしていた場合、相続税評価額は「リフォーム前の固定資産税評価額+リフォーム費用の相続税評価額」で求めます。
リフォーム費用の相続税評価額は、近隣の住宅を参考に個別に評価するのが原則です。
しかし、リフォーム費用の相続税評価額を個別で判断することは現実的に困難であるため、「(再建築費用-償却費相当額)×70%」で評価することが認められています。
なお、再建築費用はリフォームにかかった費用で、償却費相当額は「再建築費用×90%×経過年数÷耐用年数」で算出した額です。
貸家として使用している場合
貸家として使用している場合の評価額は、「固定資産税評価額×(1-借家権割合30%×賃貸割合)」で求めます。
なお、賃貸割合は「課税時期に賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷貸家の各独立部分の床面積の合計」で算出可能です。
【ここまでの復習!】2,000万円の土地にかかる相続税はいくら?

相続財産が2,000万円の土地・不動産のみの場合、基礎控除額に満たないことから、相続税は原則として非課税です。
ただし、相続税は土地や建物の不動産だけではなく、現金や預貯金、株式などを含めた遺産総額をもとに計算するため、遺産総額が基礎控除額を超える場合は相続税が発生します。
また、土地の評価額が変動している可能性もあり、上記で紹介した土地の評価方法を用いて算出しましょう。
土地(不動産)の相続税対策にマスト!小規模宅地等の特例

土地(不動産)の相続税対策になる小規模宅地等の特例や、適用できる宅地の種類について解説します。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた土地(不動産)を相続した場合に、最大80%評価額が減額される制度です。
この特例を適用するためには、以下3つの要件を満たしている必要があります。
|
適用時の評価額の計算式
小規模宅地等の特例が適用された場合、評価額は「土地の評価額×50%もしくは80%」で算出できます。
ちなみに、小規模宅地等の特例が適用できる限度面積と減額割合は以下の通りです。
| 宅地の種類 | 限度面積 | 減額割合 |
| 特定居住用宅地等 | 330m² | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 400m² | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 400m² | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200m² | 50% |
適用限度面積を超えた場合の評価額の計算式
適用限度面積を超えた場合、評価額は「土地の評価額×限度面積/土地面積×50%もしくは80%」で求めます。
たとえば、土地の評価額が5,000万円で400m²の特定居住用宅地等を相続した場合、400m²のうち330m²までが減額の対象です。
計算式は「5,000万円×330m²/400m²×80%」となり、3,300万円が減額されます。
適用できる宅地は4種類!
小規模宅地等の特例が使える土地は、以下で紹介する4種類です。
特定居住用宅地等
特定居住用宅地等とは、被相続人や被相続人と生計をともにする親族が居住していた宅地のことで、330m²までの部分を80%減額できます。
被相続人が老人ホームに入居していた場合でも、小規模宅地等の特例を利用することが可能です。
ただし、内縁の妻や夫に対して宅地を遺贈した場合は、特例を適用できません。
特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、被相続人が事業を営むために使用していた宅地のことで、400m²の部分までを80%減額できます。
自宅で飲食店や鮮魚店、工場などを営んでいるケースが該当しますが、アパートや駐車場などの貸付事業は含まれていません。
特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社事業等宅地等とは、被相続人が所有し、自ら経営する会社(同族会社)に貸し出されていた宅地のことで、400m²の部分までを80%減額できます。
その宅地を被相続人の親族であるその法人の役員が取得し、一定要件を満たした場合、相続税評価額が減額されます。
貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等とは、賃貸アパートの敷地や駐車場などの貸付事業に使用されていた宅地のことで、200m²の部分までを50%減額できます。
特例が適用されるのは、被相続人が生前に不動産貸付業を行なっていた場合であり、亡くなった後に不動産貸付業を始めても特例は適用されません。
特例適用についてのQ&A
特例適用についてのよくある質問とその回答を紹介します。
Q1.限度面積を超える土地に対しての特例適用は?
限度面積を超える土地は、該当する宅地の種類の限度面積までが特例適用の対象です。
Q2.特例を適用できる土地が複数ある場合は?
特例を適用できる土地が複数ある場合、それぞれの限度面積までは併用可能です。
ただし、併用する宅地の種類によっては、合計面積に制限が生じる場合があります。
その場合は、特例を優先的に適用する土地を選択する必要があります。
Q3.相続時精算課税制度を適用して宅地が贈与された場合は?
相続時精算課税制度を適用して宅地が贈与された場合、特例は適用されません。
特例の適用対象となるのは、相続や遺贈によって取得している土地です。
他にもいろいろ!土地(不動産)の相続税対策に使える控除と特例
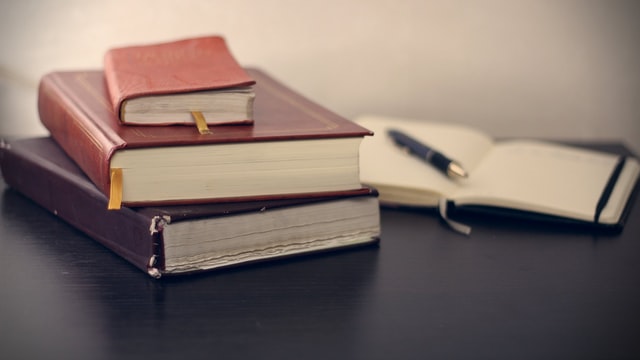
以下では、土地(不動産)の相続税対策に使える控除と特例を6つ紹介します。
贈与税額控除
贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防ぐための制度です。
贈与税額控除は、以下2つの要件を満たしている場合に適用されます。
|
配偶者控除
配偶者控除とは、納税者ではない配偶者の所得を一定額控除する制度です。
配偶者控除は、以下4つの要件を満たしている場合に適用されます。
|
未成年者控除
未成年者控除とは、相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者の相続税額から一定の金額を控除できる制度です。
成人年齢の引き下げに伴い、令和4年4月1日以後の相続または遺贈についての未成年者控除の対象者は18歳未満と言われています。
未成年者控除は、以下3つの要件を満たしている場合に適用されます。
|
障害者控除
障害者控除とは、85歳未満の障害者が、財産を相続した場合に適用される控除制度です。
障害者控除の要件は以下の4つです。
|
相次相続控除
相次相続控除とは、相続が発生してから10年以内に別の相続が発生した場合に、相続税の金額から一定の金額を控除できる制度です。
以下3つの要件に当てはまる場合、相次相続控除を受けられます。
|
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。
贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日の間に申告書を提出することで、この制度を受けられます。
相続した土地(不動産)の活用方法は!?

土地(不動産)相続後は、どのような活用方法があるのでしょうか。
自分や家族・親族が住む
1つ目は、土地(不動産)相続後に自分や家族・親族が住む方法です。
子・孫などの次の世代に不動産を相続させる場合は、小規模宅地等の特例を活用できる可能性があります。
賃貸に出して収益を得る
2つ目は、土地(不動産)相続後に賃貸に出して収益を得る方法です。
固定資産税に加えて、賃貸で利益が発生した場合は所得税を支払う必要がありますが、賃貸に出すことで評価額を30%程度下げることができます。
また、相続した土地(不動産)に自分や家族・親族が住むときと同様、小規模宅地等の特例の活用が可能です。
売却する
3つ目は、土地(不動産)の相続後に売却する方法です。
売買契約が成立した際には、仲介手数料や譲渡所得税、印紙税などがかかりますが、売却により発生した利益を固定資産税や土地計画税などに充てることができます。
相続した不動産の売却にかかる税金
相続した不動産の売却にかかる税金は、印紙税と譲渡所得税です。
印紙税は売買契約書の作成時にかかる税金で、税額は契約金額によって異なります。
譲渡所得税とは、売却益に課税される所得税や住民税のことで、税率は所有期間5年を境に変わります。
特例・控除
相続した土地(不動産)を売却する場合、相続税が発生してから3年以内の売却であれば税負担が軽くなります。
それに加えて、譲渡所得が3,000万円以内であれば、相続日から3年を経過する年の年末まで、かつ2023年末までは譲渡所得課税がかかりません。
等価交換をする
4つ目は、相続した土地(不動産)を等価交換する方法です。
等価交換とは、相続した土地をデベロッパー(開発事業者)に売却して建物を建ててもらうことです。
土地を売却した側は、土地の価値の分だけ建物や不動産を所有できます。
土地所有者は初期費用なしで土地活用を開始でき、節税にもつながるというメリットがあります。
相続放棄をする選択肢もある
相続した土地(不動産)が売れない場合は、相続放棄をするのも一つの方法です。
土地(不動産)をそのまま所有していると、固定資産税や管理費などの費用がかかってしまいますが、相続放棄をするとそのような費用を負担する必要がなくなります。
相続放棄をする際は、相続開始から3か月以内に裁判所へ申し立てを行う必要があるため、期限を過ぎないように注意しましょう。
注意!土地(不動産)の相続で気をつけるポイント

土地(不動産)を相続する際は、以下の8点に注意しましょう。
「そのまま放置」はNG!
土地(不動産)相続後に、そのまま放置するのは避けましょう。
固定資産税や都市計画税がかかり続けるうえに、不動産の維持・管理費用を支払い続ける必要があります。
また、土地(不動産)を放置してしまうと価値も下がってしまうため、早めに活用方法を決めましょう。
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内です。
申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税と延滞税が課されてしまうため、早めの申告を心がけましょう。
万が一申告期限に間に合わない場合は、相続税をいったん納める「未分割申告」を行い、後程修正申告を行なって正式な額の相続税を納めます。
なお、未分割申告で相続税を払い過ぎている場合は、修正申告の際に過払い分を戻すことが可能です。
相続開始前3年以内の贈与などは相続税が課せられる
相続開始前3年以内に行われた贈与には、相続税の支払いが課せられます。
被相続人が亡くなる3年以内に贈与した財産に対して贈与税を支払っている場合でも、相続時には相続税の課税対象です。
相続税額が2割加算される場合がある
相続人が被相続人の配偶者や一親等の血族ではない場合のほか、被相続人の孫が養子になった場合には、相続税額が2割加算されます。
なお、2割加算される場合の金額は「各人の税額控除前の相続税額×0.2」で求めることが可能です。
一次相続と二次相続を総合的に考えよう
相続が発生する場合は、二次相続まで考えましょう。
理由としては、一次相続と二次相続ではかかる税金の負担が大きく異なるためです。
二次相続の場合、相続人が1人減ることで基礎控除額が少なくなり、遺産総額が同じ場合でも、相続税が一次相続よりもかなり高くなってしまう可能性があります。
そのため、一次相続と二次相続を総合的に考え、生前贈与を行なったり一次相続の取得金額を調整したりするなどの対策が必要です。
借地権の相続にも注意!
建物の所有を目的に土地を借りる権利のことを借地権と言います。
借地権を相続する際は、借地権者と土地を保有する地主が存在するため、トラブルが起きやすい傾向があります。
借地権に関する法律も複雑であるため、弁護士に仲介をしてもらうのがおすすめです。
借地権について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
特例や税額控除で相続税が0円でも申告は必要
特例や税額控除などの制度を利用して相続税が0円になった場合にも、相続税申告が必要です。
申告が漏れてしまうと、加算税や延滞税などのペナルティを課せられてしまうため、注意しましょう。
1つの不動産を複数の相続人で分割する場合
1つの不動産を複数の相続人で分割する場合、下記の4つの方法が挙げられます。
|
この中で最も注意しなければならないのが、共有分割です。
共有分割は、土地(不動産)を活用する際に名義人全員の同意が必要であり、名義人の1人が亡くなった場合は相続でトラブルになる可能性があります。
そのため、共有分割はなるべく避けることをおすすめします。
トラブルが起きやすい!?土地(不動産)の相続については林商会にご相談ください
相続した財産に土地や不動産が含まれる場合は、分割方法や活用方法について相続人間でのトラブルに発展しがちです。
また、相続した土地にかかる相続税を計算する際には、土地の評価額を算出しなければなりません。
土地の評価方法や税金対策に効果的な特例には専門知識が必要なため、プロに依頼したほうが安心です。
相続の専門家集団である林商会では、相続に精通した税理士・弁護士・司法書士などの専門家が随時相談を受け付けています。
一人ひとりのお悩みに寄り添った解決策をご提案しますので、まずは無料相談・無料お問い合わせから、お気軽にご連絡ください。
まとめ
土地や不動産の相続後は、登録免許税と相続税、固定資産税、所得税、住民税などの税金がかかります。
特に、相続税は控除や特例などの制度を活用すると負担額が小さくなるため、積極的に活用しましょう。
土地や不動産の相続はトラブルが発生しやすいポイントでもあるため、相続についてはぜひ林商会にご相談ください。




















