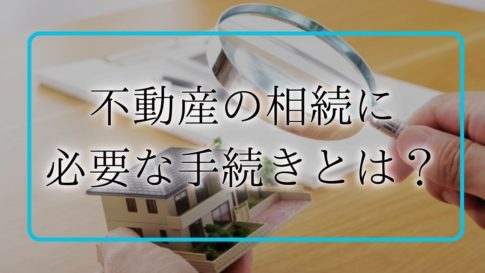相続の開始日をきちんと理解していないと、各種手続きにも影響が出ることをご存じでしたか?
しかし、孤独死のような特殊なケースだと相続の開始日がよくわからない、という方も多いかもしれません。
そこでこの記事では、さまざまなケースの相続の開始日と各種手続きについてわかりやすく解説します!
目次
把握していますか?相続の開始日と開始地のルール

相続は開始日と開始地が重要です。
被相続人の死亡によって相続は開始しますが、そのルールについてきちんと把握しておく必要があります。
亡くなったときから始まる相続の開始日
相続の開始日は、被相続人が亡くなった日から開始します。
つまり、死亡日=相続の開始日です。
死亡日の確認方法は後ほど詳しくご説明しますが、相続開始日の把握は各種手続きに影響するため、しっかり押さえておきましょう。
意外と知らない?相続の開始地について
相続の開始日と同様に重要なのが、相続の開始地(被相続人の最後の住所地)です。
相続に関する各種手続きは、相続開始地を管轄する家庭裁判所などで処理されるため、開始地を把握しておきましょう。
また、住民票地や本籍地と混同されやすいですが、あくまで被相続人が亡くなる直前まで住んでいた住所地が相続開始地です。
相続の開始日をさらに深掘り!
相続の開始日は被相続人が死亡した日ですが、死亡の確認にはいくつかのケースがあり、ケースごとに開始日が変わる場合があります。
どのような場合に開始日が変わるのか、深掘りしていきましょう。
一般的な相続の開始時期はいつから?
一般的な相続は、被相続人が死亡した日、もしくは相続人が被相続人の死亡を知った日から始まります。
自然死亡の場合、医師による死亡診断が行われ診断書に記載された年月日時分が、相続開始時期です。
失踪などの特殊なケースの場合は?
失踪や音信不通で行方がわからないなどの特殊なケースは、「失踪宣告」という手続きを行います。
失踪は普通失踪と特別失踪の2種類です。
7年以上生死不明の場合、普通失踪扱いの「失踪宣告」により死亡したとみなされます。
特別失踪は、自然災害や戦争、船舶の沈没などによる失踪のことで、危難が去った後1年間生死が明らかではない場合に「失踪宣告」を行いましょう。
失踪宣告を行なった、その認定日が相続開始日です。
また「失踪宣告」の他に、「認定死亡」という制度もあります。
「認定死亡」とは、飛行機の墜落事故などのように、はっきりと死亡を確認できなくとも生きている可能性がないと判断できるとき、警察および海上保安庁などが死亡と認定する制度です。
親族側から認定死亡を申し出ることもでき、この場合も認定日が相続開始日として認められます。
相続開始に伴う手続きの1年間の流れを紹介

相続手続きには期限のあるものがほとんどです。
相続が開始してから1年間のうちに、何をどのように進めればいいのかをまとめてご紹介します。
なお、1年後以降に行う手続きもあるので、その点も確認しておきましょう。
相続開始から1年間の主な流れ
相続開始から1年間の主な流れを表にまとめましたので、ご覧ください。
期限のあるものを「やること」、早めにやっておいたほうがよいことを「目安に行うべきこと」としています。
また、時効のある手続きを5年分まとめています。
当てはまるものは、早めの手続きがおすすめです。
| 死亡直後にやること |
|
| 14日以内にやること |
|
| 3か月以内にやること | 3か月以内を目安に行うべきこと |
|
|
| 4か月以内にやること |
|
| 6か月以内にやること |
|
| 10か月以内にやること | 10か月以内を目安として行うべきこと |
|
|
| 時効のある手続き | |
| 1年 |
|
| 2年 |
|
| 3年 |
|
| 5年 |
|
被相続人の状況や遺産の種類などによって必要な手続きは変わるので、注意してください。
【必見】相続税でペナルティを受けたくない方へ

被相続人の死亡によって相続した財産には、相続税という税金がかかります。
納税する額は、相続した財産によってさまざまです。
また、納税期日の遅れには注意してください。
ペナルティを受けないためにも、納税の期日を知っておく必要があります。
相続の開始日と期限はいつ?

相続税の申告と納税の期日は、通常被相続人の死亡を知った日の翌日から数えて10か月までとされています。
たとえば被相続人が1月10日に亡くなったのであれば、その翌日の1月11日から数えて10か月後の11月11日が、申告・納税の期限です。
【要注意】相続税の提出・支払い遅れには気を付けて!
相続税の申告や納税が遅れた場合、ペナルティがかかります。
申告が遅れた場合は無申告加算税という税金がかかり、納税が遅れた場合は延滞税が追加されます。
延滞税は以下の通りです。
|
延滞税は高い割合を請求されてしまうので、申告及び納税の期日はしっかり把握しておきましょう。
相続税手続きの申告までの基本的な流れ
相続税手続きの申告までの流れは以下の通りです。
|
一般的に四十九日の法要を終えてから動き出す人がほとんどですが、手続きは早めに進めておいたほうが無難です。
相続税の計算方法を確認しましょう!

相続税の計算方法をご説明します。
相続する財産がどれくらいあるのか、相続税がかかるのかなどについても把握しておきましょう。
そもそも相続税がかかるのかどうか把握しよう
相続税は、遺産総額が基礎控除より高い場合にかかります。
つまり、遺産総額が基礎控除以下の財産については、相続税申告が不要で相続税もかかりません。
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で決まります。
| 相続人の数 | 基礎控除額 |
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
たとえば、父が被相続人で、相続人が妻と子であれば基礎控除額は4,200万円です。
この場合、4,200万円以上の財産がなければ相続税はかかりません。
誰がいくら払わなければならないのか計算しよう
まずは課税対象となる遺産の価格を計算します。
たとえば、遺産総額が1億円、被相続人が妻と子(2人)の3人の場合で考えてみましょう。
| 遺産総額1億円-基礎控除4,800万円=5,200万円 |
課税遺産総額は5,200万円です。
続いて、相続税の総額を計算しましょう。
民法上の法定相続分割合で課税遺産総額を分配する方法を用いて、仮の税額を計算します。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
先ほどの例から、法定相続人は妻と子の2人なので法定相続分は妻1/2、子がそれぞれ1/4ずつです。
課税遺産総額が5,200万円だったので、妻2,600万円、子1,300万円ずつと計算できます。
上の表にあてはめて税額を計算してみましょう。
妻(2,600万円×税率15%)-控除額50万円=340万円
子(1,300万円×税率15%)-控除額50万円=145万円
最後に相続人それぞれの相続税負担額を計算します。
各相続人の相続税額を合算すると、340万円+(145万円×2)=630万円
630万円を3人で均等に分けた場合、1人210万円と算出できます。
ちなみに配偶者には配偶者特別控除があるので、この例の場合、配偶者の納付税額は0で子2人がそれぞれ210万円ずつ納付することになるでしょう。
【特殊ケース】孤独死による遺産相続を詳しく解説

孤独死は発見まで時間がかかる特殊なケースであるため、相続開始日の判定が難しいでしょう。
ここでは、孤独死の遺産相続を例に詳しく解説します。
わかりづらい?孤独死の相続開始日について
孤独死は病院で医師による死亡診断をされるケースとは異なり、自宅で死後何日か過ぎてから発見されることが多いため、死亡日が特定しづらいケースがほとんどです。
そのため、戸籍には「推定〇年〇月〇日から〇日までの間」と推定の死亡日が記載されます。
この場合、相続開始日は戸籍に記載されている最終日が開始日として取り扱われます。
たとえば、「推定令和4年1月10日から20日までの間」だとすれば、1月20日が開始日です。
「推定令和4年1月頃」という記載の場合は、1月最後の日、つまり1月31日が開始日とみなされます。
孤独死だからこそ優先すべき相続後の手続きって何?
孤独死の場合、被相続人と相続人の関わりがほとんどないこともあるでしょう。
しかし、それでも相続は始まります。
まずはいち早く相続するのか否かを決めましょう。
相続放棄の手続きをする場合は、相続開始日から3か月以内に行う必要があります。
とはいえ、被相続人の情報がないことも多いので、すぐにでも相続放棄したい場合を除けば、被相続人の情報を集めることが先決です。
大変な場合もある孤独死の相続税の申告を解説
孤独死の相続手続きは、一般的な手続きと変わりはありません。
ただ孤独死の場合、被相続人の情報がほとんどないケースもあります。
そのため、相続する財産の調査には大きな労力を費やすことになるでしょう。
たとえば、不動産であれば比較的調査しやすいのですが、金融財産となると以下の調査を行う必要があります。
|
金融財産の調査は数が多いですが、早く正確に行うことで相続税の申告がスムーズに進みます。
孤独死で起こりやすいトラブルに注意!

孤独死で起こりやすいのが不動産トラブルです。
孤独死は室内で亡くなることが多く、発見が遅れると腐敗や臭気など、不動産への影響が考えられます。
不動産の価値が下がると、後に所有権を持つ相続人への負担は大きくなるでしょう。
また、近隣住民は精神的な影響を被り、相続人は事情の説明を行わなければならないため、双方に負担が生じます。
さらに、特殊清掃の依頼や遺品整理も必要です。
遺品整理は、財産に関する情報や書類があるかも知れないので、相続人が行わなければなりません。
孤独死の場合、相続人にはこういった思わぬトラブルも起こりうるのです。
相続の開始日や手続きについてのご相談なら林商会へ
相続の開始日は自身で判断するのが難しいケースもあり、開始日によっては手続きの期限も変わります。
特に相続税は計算も含めて、期限などを判断するのが不安な場合は専門家に相談することをおすすめします。
林商会は、弁護士、司法書士、相続診断士などが在籍する相続の手続きに関するプロの集団です。
専門家の確かな知識と実績をもとに、お客様一人ひとりの悩みや不安に寄り添った解決方法をご提案させていただきます。
相続の開始日や手続きについて悩んでいる方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
今回は相続の開始と手続きの流れについてご説明しました。
相続は死亡と同時に発生し、急な対応を迫られることがほとんどです。
そのときに慌てることのないように、事前に相続の手続きの流れや相続税について理解しておきましょう。
もし相続や相続税に関して不安がある場合や、もっと詳しく知りたい方は専門家へ相談することもおすすめです。