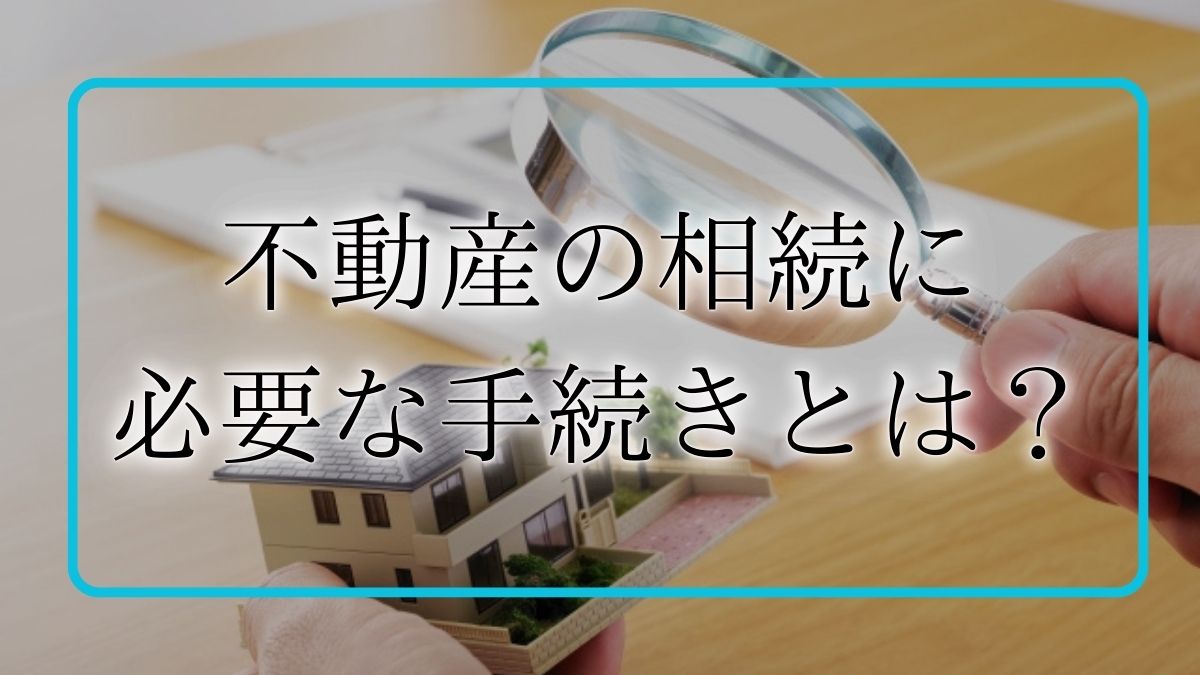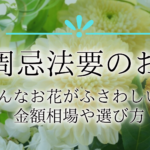不動産を相続した場合は、どのような手続きをすればよいかわからない方も多いのではないでしょうか。
なかには期限が定められているものもあるため、計画的に手続きを進める必要があります。
本記事では、不動産を相続した場合の手続きをはじめ、相続の流れや方法を解説します。
目次
不動産を相続したときの流れ

1.相続財産・相続人の把握
相続が発生したときは、まず「どんな相続財産があるのか」「相続する権利を持つのは誰なのか」を正確に把握する必要があります。
このとき、不動産以外の預貯金や株式なども含めたプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産もすべて洗い出しましょう。
後になってプラスの財産があるとわかった場合や、被相続人の莫大な借金などが発覚して、負債まで相続してしまうなどのリスクもあるため、最初にすべての財産を調べましょう。
続いて、相続人を把握するために被相続人の遺言書を確認します。
遺言書が見つかった場合は、遺言の内容に沿って相続手続きを進めましょう。
ただし、遺言書を開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要なため、勝手に開封してはいけません。
また、被相続人が「自筆証書遺言書保管制度」を利用して遺言書を預けている場合は、法務局に交付申請する必要があります。
遺言書が見つからなかった場合は、被相続人の出生から死亡までの「戸籍謄本」や「除籍謄本」をすべて取得して、相続人を確定させましょう。
他にも、法務局へ被相続人の戸籍や相続人の住民票などを提出して「相続情報一覧図」として証明してもらうのも1つの方法です。
2.遺産分割協議
遺産分割協議とは、遺言書がない場合や遺言書に記載されていない財産がある場合に、相続人同士で遺産をどう分けるか話し合うことです。
遺産分割協議において合意にいたった内容は、遺産分割協議書と呼ばれる書面に取りまとめ、相続人全員が署名・押印します。
遺産分割協議書は「不動産の相続登記」の際に必要になるため、この段階で必ず作成しておきましょう。
ただし、相続人だけで遺産分割協議をすると、もめる可能性もあるため注意が必要です。
話し合いがまとまらなかったり、遺産の分け方をめぐってトラブルに発展したりすることも珍しくありません。
どうしても遺産分割協議が進まない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて審判を仰ぐ必要も出てきます。
そうなる前に、遺産分割に関する相談窓口を設けている法律事務所や、相続問題に強い弁護士に相談することも検討しましょう。
3.不動産の名義変更
遺産分割協議が終われば、必要書類を揃えて不動産の名義変更(相続登記)をする必要があります。
相続時における不動産の名義変更は、さまざまな書類を法務局や役場から取り寄せなければならないなど、非常に手間がかかります。
なお、名義変更は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内が期限です。
4.相続税の申告・納付
相続財産の価格が基礎控除額を超えた場合は、相続税の申告が必要です。
一般的に、相続税の申告書は税理士に依頼して作成してもらいます。
ただし、相続税の申告は「被相続人が死亡した翌日から10か月以内」に行わなければなりません。
申告期限を超えてしまうと、無申告加算税や延滞税などの追徴課税を支払う必要があるため注意が必要です。
相続税は金融機関の窓口で納付するのが一般的ですが、税務署の窓口やクレジットカードでの支払い、コンビニでも納付できます。
不動産を相続したら名義変更が必要

不動産を相続した際は、不動産の取得を知った日から3年以内に名義変更(相続登記)を行う必要があります。
相続登記とは、被相続人の所有していた不動産の名義を相続人に変更し、相続人に所有権を移転させるための手続きです。
具体的には、以下の流れで手続きを進めましょう。
|
なお、遺言書がある場合または法定相続分で相続する場合は、遺産分割協議書を作成する必要ありません。
相続登記の必要書類は、次章で解説します。
相続登記の必要書類
相続登記に必要な書類は以下の通りです。
| 遺産分割協議の場合 |
|
| 法定相続分の相続の場合 |
|
| 遺言書がある場合 |
|
不動産を評価する方法

不動産を相続する場合、相続税は「その不動産の評価額」に基づいて算出されます。
不動産の評価額を決定する方法は、「路線価方式」と「倍率方式」の2種類です。
路線価方式による評価額
路線価方式とは「市街地の道路に面する土地に設定された1m²あたりの価格」に基づいて土地の評価額を計算する方式のことです。
路線価は、国税庁が毎年1月1日時点の路線価を設定して7月上旬に公表しており、国税庁のホームページで調べることができます。
路線価方式による評価額の計算式は以下の通りです。
| 評価額=路線価 × 補正率・加算率 × 地積(土地の面積) |
実際に土地の評価額を計算する際は、その土地の形状に応じて「奥行価格補正率」や「側方路線影響加算率」などの補正がかけられます。
一般的に、宅地は道路からの奥行きが短いと高い評価で、奥行きが長いと低い評価になる傾向です。
「路線価 × 地積」だけでは土地を正しく評価できないため、奥行価格補正率で補正をかけるのです。
また、正面と側面が道路に面している宅地の場合は、側方路線影響加算率による補正がかけられます。
倍率方式による評価額
倍率方式とは、固定資産評価額に「地域ごとに定められた倍率」を乗じて土地の評価額を計算する方式です。
固定資産評価額は毎年送られてくる「固定資産税納税通知書」で、倍率は国税庁ホームページの「財産評価基準書」で調べられます。
| 評価額=固定資産税評価額 × 倍率 |
倍率方式は、路線価が設定されていない郊外の土地を評価する際に用いられます。
不動産を相続する方法

現物分割
現物分割は、不動産を複数に分割して現物で相続する方法です。
具体的には、土地や建物を1人で相続したり、法定相続割合と同じ割合に「分筆」して複数の相続人が取得したりする場合を指します。
分筆とは、一筆の土地をそれぞれ分けて登記して「別の不動産」にすることです。
分筆できるのは土地のみで、建物は分筆できません。
また、地域によっては土地の分筆が認められていない場合もあるため、事前に確認が必要です。
現物分割は相続手続きの容易さがメリットですが、相続人間で不公平が生じやすいデメリットがあります。
1人の相続人が不動産を独り占めしてしまうと、遺産分割協議がまとまらなくなる可能性があるため注意が必要です。
代償分割
代償分割は、1人の相続人が不動産を相続し、他の相続人には法定相続分に応じた現金を支払う方法です。
分筆できない土地を分割する場合や、相続人の中に不動産よりも現金で相続したい人がいる場合は有効な方法でしょう。
不公平が生じにくいのがメリットですが、不動産の評価方法をめぐって相続人同士でもめる可能性があるのがデメリットです。
また、不動産を現物取得した相続人に代償金の支払い能力がない場合は利用できません。
換価分割
換価分割は、相続した不動産を売却して得た利益を複数の相続人で分け合う方法です。
不動産の売却においては「不動産の評価」は不要なため、評価方法をめぐって相続人同士で
もめることがありません。
しかし、売却を急ぐあまり安く売ってしまい、売却利益が少なくなってしまうデメリットもあります。
諸経費を差し引いた結果、手元に残る金額が少なくなってしま可能性もあるため、相続人同士で協力して売却にあたることが必要です。
共有分割
共有分割とは、相続した不動産を複数人で共同所有する方法です。
遺産分割協議がまとまらない場合などには有効な方法ですが、不動産の管理・処分に全員の同意が必要になる点がデメリットです。
共同所有者の1人が「賃貸に出したい」「リフォームしたい」などと考えても、他の共同所有者の同意がないとできません。
また、不動産を売却する場合も、共有名義人全員の同意が必要になることから、後々トラブルになる可能性があります。
不動産の相続にかかる税金
相続税

財産を相続する際には相続税がかかりますが、相続財産すべてに対して相続税が課されるわけではありません。
相続税には、相続財産の一定額までは非課税にする「基礎控除」という制度が設けられています。
基礎控除額は、「3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)」で算出します。
たとえば、財産を3人が相続する場合の基礎控除額は、3,000万円+600万円 × 3人=4,800万円です。
相続財産が基礎控除の範囲内であれば相続税は発生せず、基礎控除額を超えた場合のみ超えた分(課税遺産総額)に対して相続税が課せられます。
具体的には、以下の手順で相続税を算出します。
|
夫婦と子ども2人の4人家族で、夫(相続財産2億円)が亡くなった場合の相続税を計算してみましょう。
実際に妻・子どもが相続する財産額は、「妻:1億5,000万円、子ども:2,500万円ずつ」と仮定します。
最初に、基礎控除額を引いて課税遺産総額を算出します。
| 課税遺産総額:2億円 − 基礎控除4,800万円 = 1億5,200万円 |
課税遺産総額の1億5,200万円を法定相続分で取得したと仮定すると、妻・子どもの課税遺産総額は以下の通りです。
| 妻:1億5,200万円 × 1/2=7,600万円 子ども:1億5,200万円 × 1/4=3,800万円 子ども:1億5,200万円 × 1/4=3,800万円 |
次に、妻・子どもそれぞれの課税遺産総額に、下記の税率を乗じます。
▼相続税の速算表
| 法定相続分に応じる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 3,000万円以下 15% | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 20% | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円以上 | 60% | 7,200万円 |
| 妻:7,600万円 × 30% − 700万円=1,580万円 子ども:3,800万円 × 20% − 200万円=560万円 子ども:3,800万円 × 20% − 200万円=560万円 |
ここから、妻と子どもの相続税額を合計して、実際に取得した財産(妻:1億5,000万円、子ども:2,500万円ずつ)の取得割合に応じて振り分けます。
| 妻:2,700万円 × 1億5,000万円/2億円 = 2,025万円 子ども:2,700万円 × 2,500万円/2億円 = 337.5万円 子ども:2,700万円 × 2,500万円/2億円 = 337.5万円 |
※妻は配偶者控除を使えば、相続税の支払いは不要
上記のように、相続税の計算は非常に複雑なため、不安な場合は税理士などの専門家に任せるほうがよいでしょう。
登録免許税
登録免許税とは、名義変更を行う際に支払う税金で、「固定資産評価額の0.4%」で算出されます。
たとえば、相続する不動産の固定資産評価額が4,000万円だった場合、4,000万円 × 0.4%=16万円の登録免許税がかかる計算です。
登録免許税の納付方法には、現金と収入印紙の2種類があります。
| 【現金で納付】 金融機関で登録免許税(国税)納付用の納付書に必要事項を記入のうえ、窓口で支払います。領収書を法務局での手続き時に提出してください。【収入印紙で納付】 収入印紙は法務局の印紙売り場や金融機関で購入できます。 |
固定資産税
固定資産税は不動産にかかる税金のことで、相続した不動産の価値をもとに税額が決められるため、その不動産が建てられている市町村に納めます。
相続人が相続した不動産に住まなかったとしても、固定資産税を支払う義務があるため注意が必要です。
所得税
また、相続した不動産を売却して収入を得たときは、所得税を支払う必要があります。
不動産の相続で受けられる控除・特例

基礎控除・配偶者控除
配偶者控除とは、1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分が多い場合、その金額までが非課税となる制度です。
▼配偶者の法定相続分
|
たとえば、夫の遺産総額4億円を妻と子どもで相続する場合、妻の法定相続分は半分の2億円です。
この場合は、「2億円>1億6,000万円」となるため、妻の相続財産額が2億円までであれば相続税は0円です。
ただし、配偶者控除があるからといって配偶者に多額の財産を相続させてしまうと、「2次相続」の際に相続税が高くなる可能性があるため注意が必要です。
2次相続とは、夫の遺産を相続した妻が亡くなり、妻の遺産を子どもが相続することを言います。
相続税の税率は、相続財産の額が高ければ高いほど税率も高くなる累進課税制度です。
加えて、妻は配偶者控除を利用できますが、子どもには基礎控除以外の特例は適用されません。
そのため、仮に妻が相続した多額の財産をそのまま子どもが相続した場合、子どもが支払う相続税が莫大になってしまう可能性があるのです。
2次相続のことも考えて、夫婦間での相続は慎重に行うほうがよいでしょう。
取得費加算の特例
取得費加算の特例とは、相続した不動産を売却して利益が出た場合に課される「所得税」を軽減できる特例です。
相続した不動産を売却した場合、売却代金から取得費・手数料を差し引いた利益の分に所得税が課せられます。
つまり、取得費や手数料を数字上で多くできれば、所得税を軽減できるのです。
取得費加算の特例では、相続した不動産を相続税の申告期限から3年以内に売却した場合に、納付した相続税の一部を取得費に計上できます。
取得費加算の特例を使用する際は、以下の3点に注意しましょう。
|
取得費加算の特例が使えるのは、相続開始日の翌日から3年10か月以内です。
遺産分割協議が終わらず、この期限を過ぎてしまった場合は取得費加算の特例を利用できなくなります。
また、相続した不動産が複数ある場合は、期限内にどの不動産から売却するべきか優先順位を決めましょう。
売却利益が大きい不動産のほうが、節税効果も高くなります。
代償分割とは、相続人の1人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払う相続方法です。
代償金を支払って取得した不動産を売却する場合、取得費に加算できる相続税額の計算方法が通常とは異なります。
結果的に取得費に加算できる金額が減少するため、取得費加算の特例による節税効果が少なくなってしまうのです。
小規模宅地の特例
小規模宅地の特例とは、以下の土地を一定の要件を満たす人が相続した場合に、土地の相続税評価額を80%または50%減額できる制度です。
| 土地の種類 | 限度面積 | 減額割合 |
| 被相続人が住んでいた土地 | 330m² | 80% |
| 事業をしていた土地 | 400m² | 80% |
| 貸し付けていた土地 | 200m² | 50% |
たとえば、被相続人が住んでいた土地の相続税評価額が1億円だったとします。
小規模宅地の特例を適用すれば、2,000万円の評価額で相続税を計算できるのです。
ただし、小規模宅地の特例は適用要件が非常に複雑で、いざ蓋を開けてみると特例を受けられなかったなどのケースもあります。
確実に適用を受けるためには、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
地積規模の大きな宅地の評価
地積規模の大きな宅地の評価とは、平成30年1月1日から適用された「面積の多い宅地の評価方法」です。
1,000m²(三大都市圏は500m²)を超える一定の要件を満たす土地であれば、相続税を20~30%ほど減額できます。
ただし、遺産分割などで土地を分割して相続した場合は注意が必要です。
土地が分割された場合は、原則として分割後の土地面積で判定されます。
たとえば、三大都市圏にある800m²の土地を、妻と長男で半分に分割して相続したとしましょう。
妻・子どもが相続する土地面積は400m²となり、三大都市圏の面積要件500m²を満たさないため、地積規模の大きな宅地の評価は適用されません。
不動産の相続に関する注意点

土地を相続した場合
土地の価格は常に変動するため、土地の分割相続には注意が必要です。
相続時には平等に分割したつもりでも、後になって価格が値上がりした場合は相続人間で不平等が生じる可能性があります。
将来の価格変動についてすべての相続人が納得したうえで、分割相続を進めましょう。
戸建てを相続した場合
相続人が別の住宅を所有していれば、相続した戸建て住居が空き家になる可能性があります。
その場合は相続した戸建て住居が特定空き家に指定されてしまい、小規模住宅用地の特例が適用されません。
また、固定資産税も高額になってしまうなどのリスクもあるため、空き家のまま所有するのであれば売却を検討するほうがよいでしょう。
マンションを相続した場合
マンションを相続した場合、賃貸経営を考える人も多いでしょう。
しかし、築年数が古いマンションは入居者を獲得するのが難しい場合もあります。
賃貸物件として所有したまま家賃収入が得られない事態に陥る可能性もあるため、あまりに築年数が古い場合は売却を検討しましょう。
不動産相続のご相談なら林商会へ
不動産の相続にお困りの方は、株式会社林商会にご相談ください。
林商会では、税理士や弁護士、司法書士といった相続に関する専門家だけでなく空き家相談士、空き家管理士も在籍しており、空き家となった不動産のご相談も可能です。
また不動産売却や空き家の解体にも対応しております。
不動産相続に関するご相談は、無料お問い合わせからお待ちしております。
まとめ
不動産の相続では、相続税の計算に「土地の評価」が必要になるため、他の財産を相続する場合に比べて手続きが複雑です。
また、分割しにくい財産という特性上、相続人が多くなればなるほど遺産分割協議をまとめるのに時間と手間がかかります。
トラブルを避けながらすべての手続きをスムーズに行うためには、専門家に相談することも検討しましょう。