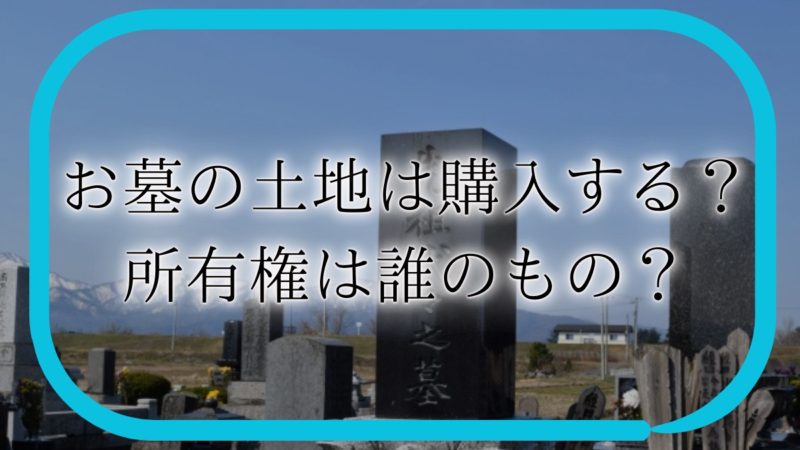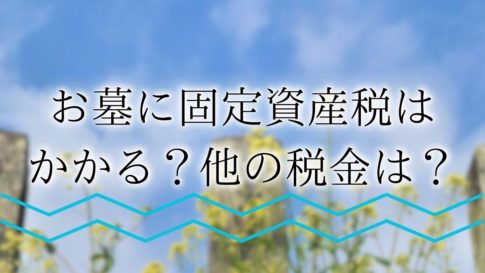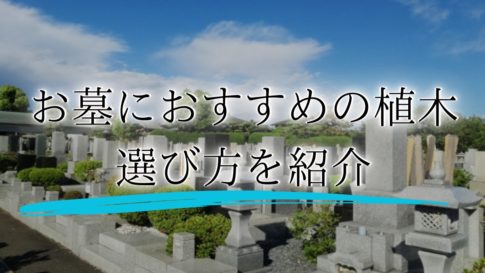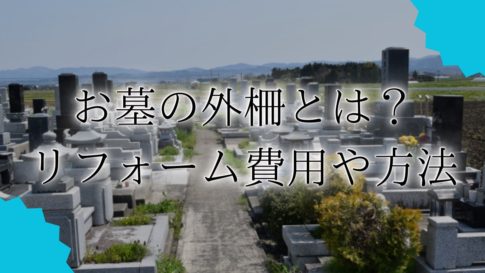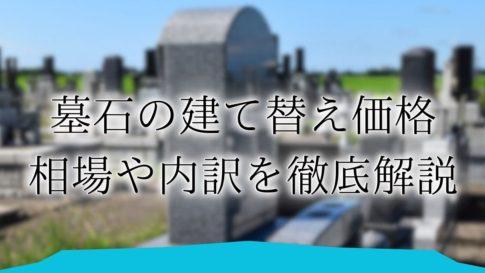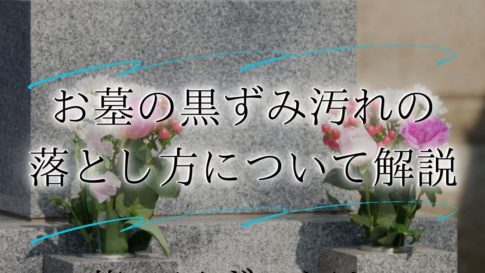「お墓を建てたいけど、土地も一緒に購入すべきなのかな?」「墓守が亡くなってしまったから、お墓をどうすればよいかわからない」など、お墓の土地の所有権について理解している人は少ないかもしれません。
本記事では、墓地の権利や費用、墓守が亡くなった場合の具体的な手続きなどを解説します。
また、お墓の購入に必要な費用や土地を決めるまでの流れも紹介しているので、これからお墓を建てる人はぜひ参考にしてください。
目次
お墓の土地は墓地・霊園から借りるもの

最初に注意しておきたいのが、「墓地の所有権は墓地・霊園のもの」であることです。
「墓地を購入した」と聞くと、お墓とその土地をまるごと含めて買ったと考える人も多いのではないでしょうか。
しかし実際は、墓地の所有権は墓石の購入者ではなく、墓地や霊園の運営者側にあります。
というのも、墓地埋葬法第10条によって、もともとの土地の所有権は運営者にあって、自治体の許可を受けたうえでその土地を墓地として使用しているためです。
お墓を購入したからといって、お墓を含めた土地も自分のものになるわけではありません。
自分の所有地にお墓は建てられる?
お墓を建てられる場所は法律で定められているため、現在は自分の所有地にお墓を建てることは禁じられています。
「みなし墓地」と呼ばれる個人が所有する田畑や山中に建てられた個人墓地や共同墓地は、法律で定められる前に建てられたお墓です。
なお、みなし墓地は通常のお墓と異なり、所有権を取得しています。
墓石の所有権は購入者のもの
墓地の所有権と違い、墓石の所有権は購入者にあります。
借りている土地に自分の家を建てているようなイメージですが、お墓の場合は一般的な不動産と違って借地権や地上権などはありません。
お墓の土地を借りるための「永代使用権」

お墓の土地を借りるには、永代使用権が必要です。
ここからは、墓地の永代使用権と譲渡について紹介します。
永代使用権とは
永代使用権とは、墓地や霊園から墓地を借りて墓地を使用できる権利を指します。
発生する代金は、墓所契約を交わすときに一括で支払うのが一般的です。
永代使用権の譲渡は原則禁止
墓地は遺骨を納める神聖な場所のため、もし勝手に譲渡してしまえば素性のわからない遺骨が増えてしまう可能性もあります。
そのため、譲渡禁止特約のある永代使用権が一般的です。
しかし、前の墓守が亡くなってお墓の管理者を変更する場合など、墓地管理者から承諾が得られれば譲渡できるケースもあります。
なお、永代使用権が有効なのはお墓として墓地を利用しているときだけなので、お墓を引っ越しさせて使わなくなると再利用できません。
新たにお墓を建てる場合、霊園の管理者と譲渡や再契約が必要なのか、事前に相談しておいたほうがよいでしょう。
永代使用料の相場と注意点
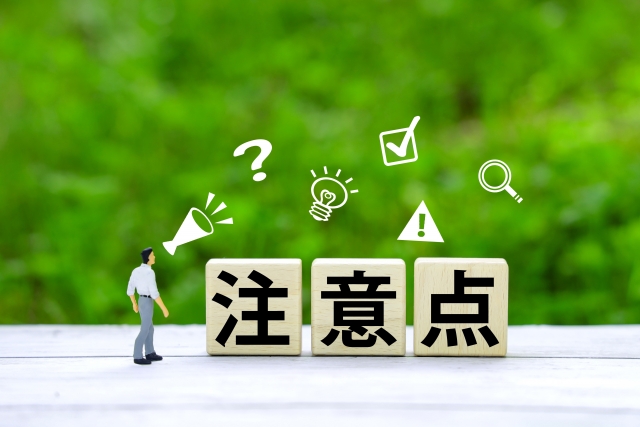
お墓の土地を使用する際に欠かせない「永代使用権」を得るためには、費用がかかります。
以下では、永代使用料の相場と注意すべきポイントについて見ていきましょう。
永代使用料の相場
墓地の権利を買うための永代使用料は、およそ60~80万円が相場です。
ただし、地価の高い都市部は永代使用料が高くなる傾向にあり、さらに設備や立地によっても価格が変動します。
墓地を解約しても返却されない
永代使用権を得るために支払った永代使用料は、墓地を解約しても返却されないので注意しましょう。
短期間の利用なら、墓地を解約すればいくらか永代使用料が戻ってくると考えるかもしれませんが、永代使用権は「墓地を使用するための権利」です。
使用した期間に限らず返金されません。
墓地の管理者とのトラブルを避けるために、お墓の土地は慎重に検討して決めましょう。
墓守が亡くなった場合の手続き

お墓の管理・継承の役割をする墓守が亡くなった場合、無縁仏になったり墓地の使用契約を解除されたりするケースがあります。
公営墓地は、墓地を管理している自治体や霊園の運営事務所に連絡して墓所使用契約の承継手続きが必要です。
民営墓地や寺院墓地も同様に墓地の運営者へ連絡して、管理費の引き落としに使う口座や墓地使用者名義を変更しましょう。
寺院墓地で檀家の場合は檀家を承継する必要があるため、檀家のシステムを把握してから手続きに移ると安心です。
墓守の名義変更に必要な書類
墓守が亡くなると、名義変更のために公的書類の提出が必要です。
実際に必要な書類は霊園や墓地によって異なりますが、以下では一般的に必要となる可能性が高いものを紹介します。
|
用意すべき書類が多いですが、手続きをスムーズに進めるためになるべく早めに用意しておきましょう。
お墓の購入に必要な費用の目安

お墓の購入にかかる費用にはいくつか項目があるため、ここでは一般的な費用を紹介します。
永代使用料
お墓の購入に必要な費用として、墓地を使う権利を購入するための永代使用料が挙げられます。
購入時に支払えば、その使用権は先祖代々引き継ぐことが可能です。
先述の通り、相場は60~80万円が一般的で、東京などの都市部や使用する面積が大きいほど使用料も高くなります。
墓石代
墓石代はお墓の建物にかかる費用で、相場はおよそ70~200万円です。
石材の種類や量、加工の方法、立地などによっても価格が異なります。
設置代
設置代とは、お墓を設置する際の基礎工事や外柵工事にかかる費用で、相場は5万円程度です。
ただし、墓石の運搬などにクレーン車を使用すると工事費も高くなります。
設置代が安すぎると施工が雑に行われる恐れもあるので、相場を目安に金額に見合った工事をしてもらえるか確認しましょう。
お布施代
新しくお墓を建てる際には開眼供養の儀式を行うのが一般的ですが、読経への謝礼としてお布施代を支払いましょう。
相場はおよそ3~10万円で、お布施代の他にもお車代や御膳料として1万円程包みます。
初めてお墓を購入する方は、以下の記事も参考にしてください。
▼お墓の購入方法を詳しく見る
お墓の土地を決めるまでの流れ

墓地を選んでお墓を購入するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。
以下で紹介する手順を理解して、スムーズに手続きができるように準備しておきましょう。
1.情報・資料を集める
まずは、お墓を建てるために必要な情報や資料を集めることが重要です。
予算や墓石の大きさとデザイン、立地などを最初に決めておきましょう。
情報収集の方法にはネットで検索したり、お寺や霊園、石材店に連絡してみたりとさまざまな方法があります。
正確な情報を得るために、なるべく多くの資料を集めて比較検討してみてください。
2.気になる墓地を見学する
資料を見て気になる墓地があれば、直接足を運んで見学してみましょう。
その際、墓地へのアクセスのよさや墓地全体の雰囲気、管理状況などを実際に確認してみてください。
また、石材店の指定の有無やスタッフの対応もチェックしておきたいポイントです。
3.気に入れば契約する
墓地を見学して気に入れば、契約手続きを進めましょう。
契約する際は、購入費と合わせて、年間管理費も確認しておいてください。
墓所の使用契約書を結ぶためには公的書類も必要になるため、お寺や霊園に事前に必要な書類を問い合わせておくことも大切です。
墓石は墓地を決めてから購入しよう
墓石は、墓地を契約してから購入するのが一般的な流れです。
なかには墓地によって石材店の指定があるため、事前に確認しておきましょう。
指定がない際は複数の石材店に見積もりを依頼して、墓石の材質やデザインの希望も伝えておくとスムーズです。
お墓を購入する際の流れや注意点など詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
※内部リンク「墓 購入」
まとめ
今回は、墓地の所有権やお墓の購入に必要な費用から土地を決めるまでの流れを解説しました。
お墓の土地の所有権は墓石を購入した人ではなく、墓地や霊園の運営管理者にあります。
土地を借りるために必要な永代使用権や、その権利を得るための永代使用料についても紹介したので、見積もりを依頼する際の参考にしてください。
トラブルを避けるために、本記事で紹介した内容をしっかり確認して新しいお墓を建てるときに役立てましょう。