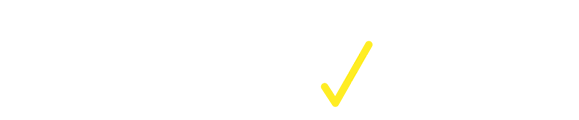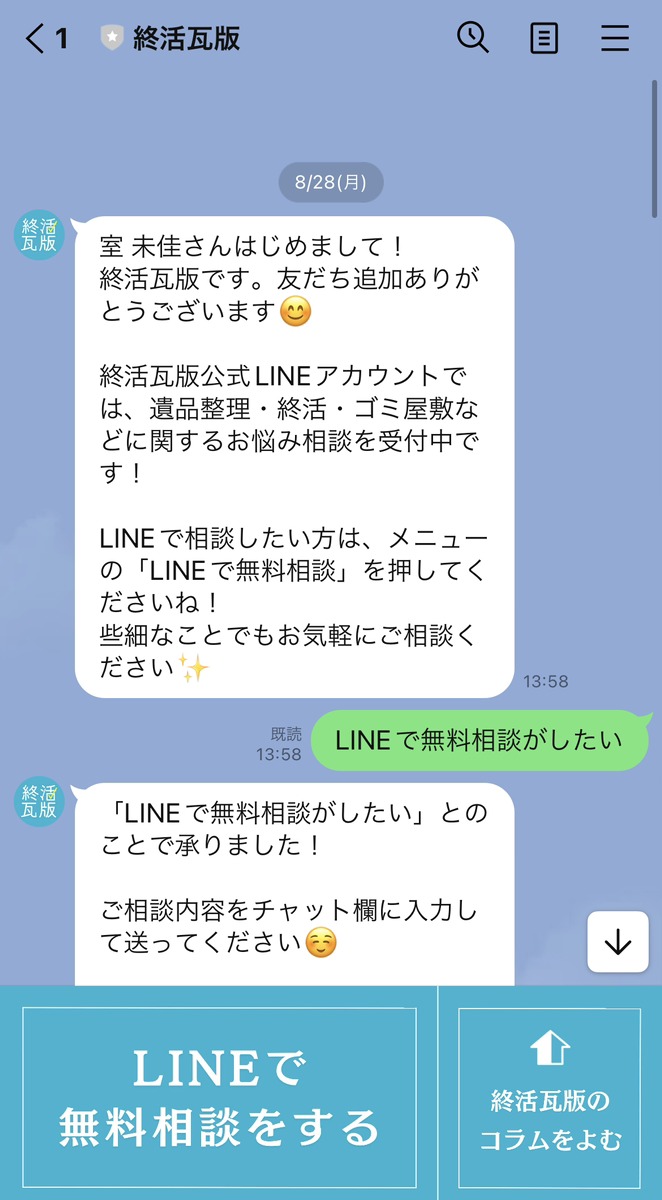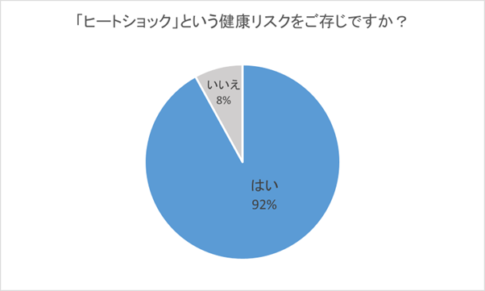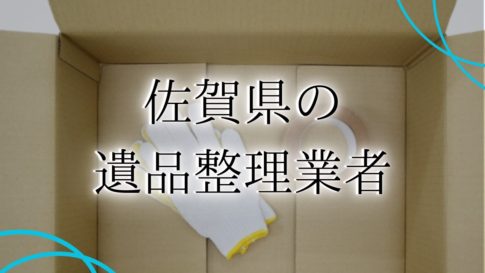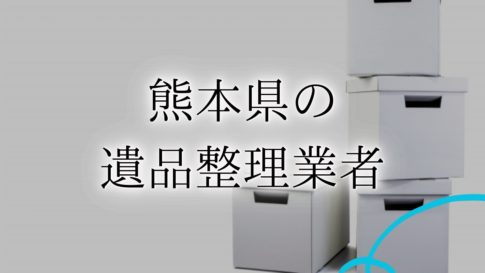相続時精算課税制度は、生前贈与を受ける際に最大2,500万円まで非課税になる制度です。
住宅資金の贈与を受ける際にも活用可能ですが、住宅取得等資金の非課税制度と併用できることはご存じでしょうか?
この記事では、相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税制度の概要のほか、相続時精算課税制度を活用して住宅や土地を贈与されるときの注意点についても解説します。
目次
相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度と住宅取得資金の非課税制度のメリットを最大限享受するためには、それぞれの特徴や要件を把握しておかなければなりません。
まずは相続時精算課税制度について知り、相続や贈与への理解を深めましょう。
贈与時に発生する税金の支払いを相続時まで先延ばしできる制度
相続時精算課税制度とは、2,500万円までの生前贈与に対して非課税枠が利用できる制度で、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に財産を贈る際に選択可能です。
この制度を利用すると、非課税枠の2,500万円を超えた財産のみに20%の贈与税が課せられ、相続発生時に、すでに贈られた贈与財産と相続財産を合わせて税額を計算します。
相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。
住宅資金の贈与を受ける場合は「住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例」も選択できる
父母または祖父母から住宅取得のための資金贈与を受ける際は、「相続時精算課税制度」と「相続時精算課税選択の特例」の2つから課税方法を選択できます。
相続時精算課税選択の特例とは、一定の要件を満たす場合に限り、贈与者が贈与を行う年の1月1日時点で60歳未満であっても、相続時精算課税制度を選べる制度です。
通常の相続時精算課税制度と同じく、非課税枠内の贈与額であれば課税されず、2,500万円を超えた場合は一律20%の贈与税が発生します。
どちらも相続時に精算することを前提とし、相続関係にある親から子への生前贈与を後押ししていることから、積極的に活用していきたい制度と言えるでしょう。
【相続時精算課税制度と併用可能】住宅取得等資金の非課税制度とは?

次に、住宅取得等資金の非課税制度について解説します。
冒頭でも述べたように、相続時精算課税制度と併用すれば、より高い節税効果が得られます。
ただし制度の適用には複数の要件があるため、しっかりと確認しておきましょう。
住宅取得等資金の非課税制度について
住宅取得等資金の非課税制度とは、両親や祖父母などの直系尊属から住宅取得のための資金を贈与された場合、一定の金額が非課税となる制度です。
当初は2020年(令和2年)4月1日~2021年(令和3年)12月31日までの適用でしたが、2022年(令和4年)度の税制改正により、2023年(令和5年)12月31日までに期間が延長されています。
単独で利用することはもちろん、相続時精算課税制度(非課税枠2,500万円)との併用も可能で、住宅取得の際に高い節税効果が期待できます。
非課税の限度額一覧表
住宅取得等資金の非課税制度の非課税限度額は、取得する住宅の種類によって異なります。
住宅の種類ごとの限度額は、以下の通りです。
| 省エネ等住宅 | 左記以外の一般住宅 |
| 1,000万円 | 500万円 |
現行の税制では、贈与された資金を省エネ等住宅の取得に充てた場合は1,000万円、その他の一般住宅は500万円が上限です。
相続税精算課税制度と併用すれば、最大で3,500万円を非課税で贈与できます。
適用要件
住宅取得等資金の非課税制度の適用要件は、次の通りです。
|
注意しなければならないのは、居住用不動産そのものの贈与、住宅の取得後に受けた贈与、不動産の仲介手数料等の経費に充てられた金銭は、制度の対象にならないということです。
また贈与金額が非課税枠の範囲内でも、贈与税の申告は必要なため、必ず申告期限内に手続きを行うようにしましょう。
【どう違う?】相続時精算課税制度・住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例・住宅取得等資金の非課税制度

相続時精算課税制度・住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例・住宅取得等資金の非課税制度の3つは、それぞれ異なる制度ですが混同する人が多く見られます。
ここでは3制度の違いを表にまとめたので、ぜひ複数の制度を活用する際の参考にしてください。
| 相続時精算課税制度 | 住宅取得等資金の相続時 精算課税選択の特例 |
住宅取得等資金の 非課税制度 |
|
| 非課税枠 | 一律2,500万円 | <省エネ等住宅>1,000万円 <一般住宅>500万円 |
|
| 贈与者 | 贈与した年の1月1日において60歳以上の直系尊属 | 直系尊属(年齢制限なし) | |
| 受贈者 | 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の推定相続人(代襲相続人も含む)、かつ直系卑属 ※受遺者である兄弟姉妹がそれぞれ贈与者ごとに選択可能 |
贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の直系卑属 ※2022年(令和4年)以前の贈与は20歳以上 |
|
| 税率 | 2,500万円を超えた場合に一律20% | <暦年課税の場合>住宅種別ごとの非課税枠+基礎控除110万円を超える場合に累進課税(10~55%) <相続時精算課税制度と併用の場合>非課税枠(2,500万円+住宅種別ごとの非課税枠)を超える場合に一律20% |
|
| 贈与財産 | 不動産・有価証券・借入金など、どのような財産にも充当可能 | 自己の居住用住宅およびその敷地の購入資金、一定の増改築費用に充てるための金銭贈与であること ※2023年(令和5年)12月31日までの贈与に限る |
|
| 物件の引渡し時期 | 規定なし | 贈与の翌年3月15日までに、住宅の引渡し、居住を済ませていること(同年12月31日までの居住が確実であること) | |
| 物件の要件 | 規定なし | <新築住宅>
<中古住宅>
<増改築>
|
新築住宅・中古住宅・増改築ともに、登記床面積が50m2以上 240m2以下であること(ただし、震災被害者は除き、受贈者の所得金額が1,000万円以下の場合は40m2以上50m2未満も対象となる)
登記床面積以外の要件については、左記に同じ |
| 申告義務 | 制度の適用を受ける者は課税額の有無に関係なく、贈与の翌年2月1日~3月15日までに税務署への申告が必要 | ||
| その他 (注意点) |
受贈者の所得金額が2,000万円以上の場合は適用の対象外 | ||
土地売却時に相続時精算課税を活用したときのメリット

相続時精算課税は、贈与を受けて購入した土地を売却する際にも活用できます。
ここからは、土地売却時に相続時精算課税を活用する場合のメリットについて解説するので、ぜひ今後の参考にしてください。
売却利益が大きくなる可能性が高い
土地売却では、取得にかかった費用が少ないほど、売却時の利益は大きくなるのが基本です。
相続時精算課税を活用すれば最大2,500万円の贈与が非課税で受けられるため、より多くの利益を得られる可能性があります。
なお、相続時精算課税では、相続時に非課税分の2,500万円に対して相続税が課税されますが、相続税は基礎控除額が高いうえに税率が低いため、それほど大きな課税額にはならないでしょう。
一方、暦年課税では110万円の基礎控除を差し引いた額に10~55%の累進課税がかけられるため、土地売却も踏まえて利用するのは得策とは言えません。
相続時精算課税を利用したほうが、土地の購入費用を安く抑えられ、売却時の利益も大きくなるでしょう。
売却手続きをスムーズに進められる
節税のために年間110万円の基礎控除内で暦年課税を続けようとすると、土地のすべての購入資金を得るまでに長い時間がかかります。
たとえば3,000万円の土地を購入するために年間110万円ずつ贈与する場合、資金が揃うのは28年後です。
しかし、相続時精算課税を選択した場合、2,500万円までの贈与が非課税対象となるため、複数回に分けて贈与を行う必要はありません。
贈与の回数が少ない分、土地の売却にも早く着手できるのです。
取得費加算の特例を活用できる
取得費加算の特例とは、相続した土地を3年以内に売却する場合に限り、相続税の一部を取得費として加算できる制度です。
相続税の一部を住宅の取得費に加算することで、譲渡所得税の課税対象額が減額され、譲渡所得税の節税ができます。
この特例は相続に関する特例のため、通常は土地取得のための贈与には利用できません。
ただし相続時精算課税を選択する場合は、相続時に贈与税非課税分の相続税が発生するので、適用が可能です。
土地を売却した際の譲渡所得税を軽減したい場合に有効な手立てと言えるでしょう。
なお、贈与税非課税分と他の相続財産の合計額が相続税の基礎控除額以下のケースでは、取得費加算の特例対象から外れてしまうため注意してください。
売却利益で税金の支払いができる
贈与税は、原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告し、納める必要があります。
支払いに十分な資金がない場合、贈与を辞退するか、資金が得られるまで贈与を延期してもらわなければなりません。
しかし相続時精算課税を選択すれば、贈与税額が大幅に減額されたり非課税で贈与が受けられたりします。
また、贈与された土地を相続が発生するまでに売却し、得た利益を他の税金に充てることも可能です。
相続税精算課税は、こうした経済的な理由で贈与を受けることが難しいケースにも活用できます。
必読!相続時精算課税制度を活用して住宅や土地を贈与されるときの注意点

相続時精算課税制度は、住宅や土地、またはその購入費用を贈与してもらう際に便利な制度ですが、注意点もあります。
「住宅購入費の負担を減らすために贈与してもらったのに、支払う税金が増えた」といったことがないよう、しっかりと確認しておきましょう。
相続税の小規模宅地等の特例が使えなくなる
小規模宅地等の特例とは、被相続人と同居していた土地を相続しており、かつ面積が330m²以下の場合の場合に、財産評価額の80%を非課税とする制度です。
原則として、相続時精算課税で贈与された土地には適用されません。
そのため、本来は小規模宅地等の特例で支払わずに済んだ相続税が、相続時精算課税を利用することで余計にかかってしまう可能性があります。
例として、4,000万円の土地を小規模宅地の特例を適用して相続した場合で考えると、4,000万円×80%の3,200万円が非課税です。
4,000万円から非課税額3,200万円を差し引いた800万円が相続税の課税対象になりますが、相続税の基礎控除額内に収まるため、結果として相続税はかかりません。
一方、相続時精算課税を利用した場合、(土地価格4,000万円-非課税額2,500万円)×20%の300万円が贈与税額になります。
相続時は非課税額分の2,500万円から贈与税額300万円が差し引かれた2,200万円が課税対象となるため、小規模宅地等の特例同様に相続税は発生しませんが、300万円の贈与税は支払ったままです。
このように相続時精算課税を選択して小規模宅地等の特例が適用されなかったことで、税金を多く支払ってしまうケースが考えられます。
相続税の負担が増える可能性もある
民法では、遺贈や相続時精算課税による贈与を受けた受贈者が、被相続人から見て一親等の血族(父母や子)または配偶者でない場合、相続税額を2割加算することが定められています。
この制度を「相続税額の2割加算」といい、相続時精算課税によって孫が土地の贈与を受けた場合も適用の対象です。
そのため孫は相続人でないにもかかわらず、2割加算された相続税を納めなければなりません。
もし代襲相続人となって法定相続分を獲得できれば、受け継いだ財産を税金に充てられますが、そうでない限り、自分の貯金から支払う必要があります。
贈与税以外の税がかかる
土地や家屋などの不動産を取得する場合は、不動産取得税がかかります。
贈与によって取得した不動産も同様で、税率はそれぞれの市区町村で決められた固定資産税評価額の3%または4%です。
家屋は使用状況に応じて税率が変わり、土地は固定資産税評価額の1/2で計算します。
ただし相続時精算課税を利用した贈与の場合、一定の要件を満たせば、不動産所得税を軽減することが可能です。
他にも上記で述べたように、相続税や譲渡所得税の支払いが必要になる可能性も押さえておきましょう。
相続時精算課税制度の疑問や住宅・土地の贈与についてのご相談は林商会にお任せください!
相続税対策の一環で生前贈与を行なった場合は贈与税が課せられますが、相続時精算課税制度を利用すると最大2,500万円まで非課税になります。
住宅資金の贈与を受ける際には、住宅取得等資金の非課税制度との併用が可能ですが、正しい知識が必要で手続きも煩雑なため、専門家に相談や依頼するのがおすすめです。
林商会には、相続の専門知識が豊富な税理士・弁護士・司法書士・行政書士などの専門家が在籍しており、お悩みや疑問の一つひとつに真摯に対応します。
最善の解決策をご提案しますので、まずは無料相談からお気軽にご連絡ください。
まとめ

相続時精算課税制度は、次世代へとより多くの財産を残したい場合に有効な制度です。
住宅取得等資金の非課税制と併用すれば、子や孫が住宅の取得・売却をする際に、税金の負担を軽くできます。
ただし、他の特例が使えなくなったり、かえって税金の負担が大きくなったりする可能性もあるため、制度の活用は慎重に行なっていきましょう。