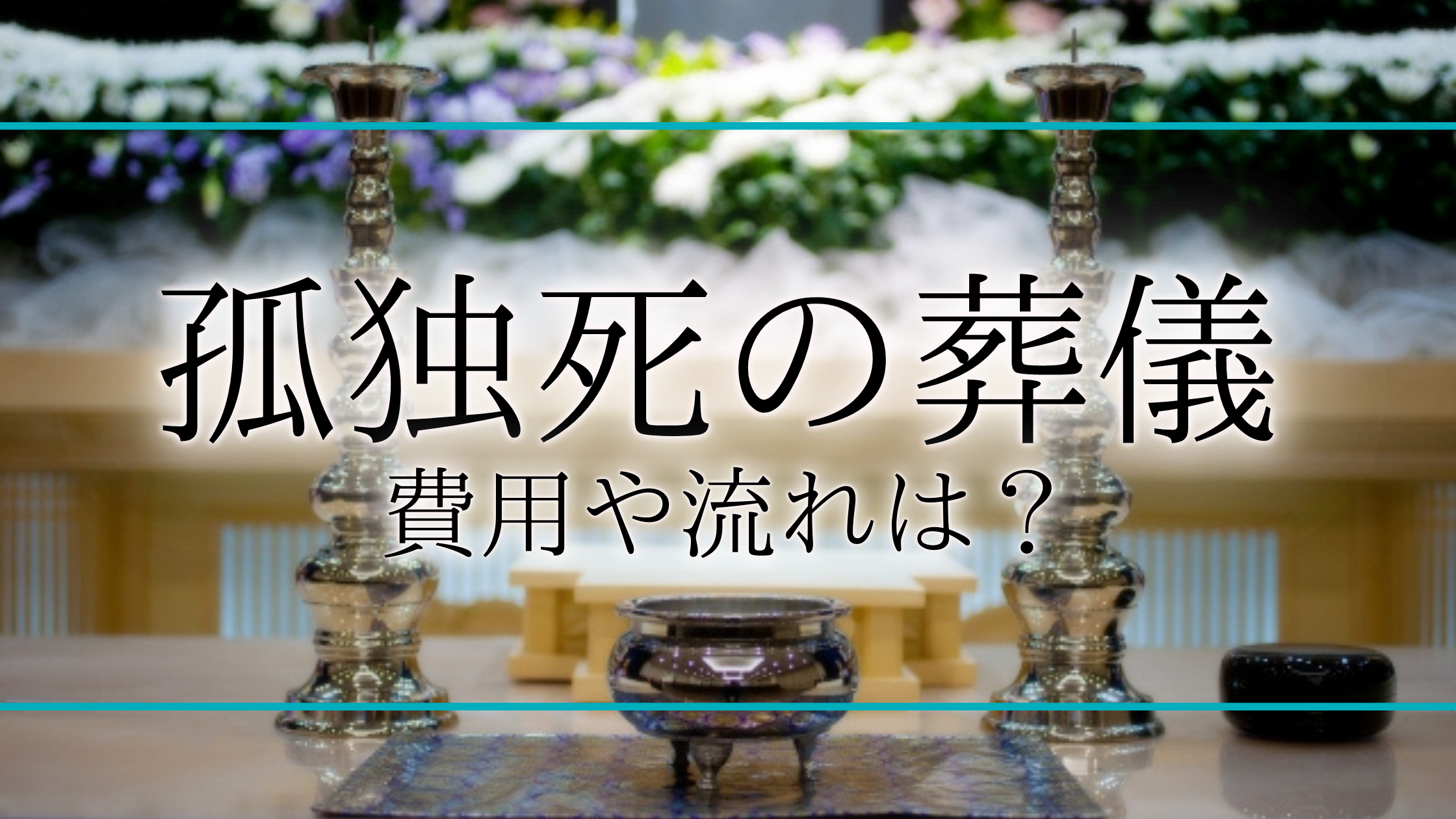・自身が所有する物件で孤独死があった
・親が自宅で孤独死をしていた
上記の場合、清掃や賠償、家賃収入、売却金額など、費用面での心配が大きいのではないでしょうか。
少しでも費用面での負担を抑えたいのであれば、孤独死保険へ加入しておくことをおすすめします。
孤独死のあった物件はほとんどが「事故物件」となり、物件の持ち主は今後物件を貸す・売ることが困難になることがあります。
この記事では孤独死が起こった物件での対処法と孤独死保険について解説します。
孤独死のあった物件は“事故物件”に該当するのか

未婚化が進む現在、ひとりでひっそりと亡くなる孤独死という最期を迎えるケースも珍しいものではなくなってきました。
家の中で孤独死しているのが見つかった場合、その家は事故物件となるのでしょうか。
人が亡くなっていても事故物件に該当しないケース
前提として、孤独死(病死)は「自然死」とされ事故物件にはなりません。
亡くなってからすぐに発見された、救急車を手配したが自室で死亡した、または倒れているところを発見され病院で亡くなった などの場合事故物件にはなりません。
注意!事故物件に該当するケース
ただし、亡くなってから発見されるまでに一定期間が経過していた場合や、ニュースで取り上げられてしまった場合は事故物件に該当します。
孤独死=事故物件というわけではないですが、そもそも孤独死は気にかけてくれる人が身の回りにおらず孤独のまま亡くなっていく方が多いため、亡くなってからかなりの日数経過してから発見されるケースがほとんどです。
亡くなると遺体は腐敗していきますが、床が変色していたり部屋に臭いが残っていたりなど室内の一部でも孤独死の影響がある場合も事故物件という扱いになります。
事故物件に該当する物件では【売却・賃貸時に告知義務が発生します】
物件所有者は入居希望者に対し、心理的瑕疵(かし)や物理的瑕疵がある物件では告知義務が発生します。
心理的瑕疵とは
心理的瑕疵物件とは借主や買主が「そのことを知っていればこの物件を借りなかった(購入しなかった)」という抵抗感を覚える可能性がある物件です。
自殺や他殺のほか、近く墓地がある場合や暴力団の構成員が近所に住んでいるなどの場合に適用されます。
孤独死があった物件では心理的瑕疵に該当します。
物理的瑕疵とは
物理的瑕疵とは、物件においては耐震強度が不足していたりシロアリの被害にあっているなど「物理的に問題がある物件」に対して適用されます。
土地においては土壌が汚染されていたり、地中に障害物が埋まっている場合などに適用されます。
事故物件に該当する孤独死で起こるリスク

事故物件扱いとなる孤独死があった場合、その物件の所有者にどんなリスクが起こり得るのでしょうか。
賠償問題や特殊清掃にかかる費用
孤独死が発見されるきっかけのひとつが、異臭による近隣住民からの通報です。
季節や室内環境にもよりますが、異臭が出るほど時間が経っていた場合は賠償問題に発展することがあります。
賃貸においては、借主の相続人は家主に対して賠償が発生する可能性があります。
また室内に変色や臭気が残ってしまった場合、特殊清掃も必要となります。
特殊清掃の費用はワンルームで3万円~8万円程度ですが、遺品整理も一緒に依頼する場合はそのぶん料金が加算されます。
賃貸物件では家賃収入が大幅に低下する恐れ
事故物件に該当する場合、事故物件の家賃は相場よりも安く設定せざるを得ず、値下げをしたとしてもすぐに入居希望者が決まることは少ないでしょう。
それだけではなく孤独死した部屋の近隣住人が退去してしまうこともあり、そうすると空き家が増え家賃収入が大幅に低下してしまう恐れがあります。
持家の場合、手放すことは容易ではない
不動産は築年数とともに価値が下がるケースが圧倒的で、売値に対して買い取り額が7割程度になることが通例です。
しかし孤独死のあった部屋ではさらに価値が低下してしまうことが予想されます。
孤独死のあった物件はどう対処する?

貸し出している部屋で孤独死があった場合、どのように対処するべきなのでしょうか。
まずは特殊清掃を
特殊清掃とは、体液や血液の清掃・害虫駆除、徹底した消臭などです。
体液がフローリングに染み込んでしまっているなど清掃だけで原状回復が難しい場合は、リフォームをすることもあります。
株式会社林商会では、清掃や害虫駆除、消臭、リフォームまですべて取り扱っています。
最新の除菌技術「ナノゾーンコート」も取り扱っており、丁寧に除菌作業をしたいという方に選ばれているメニューです。
売却・賃貸の際は必ず告知する
事故物件においては、数年間入居希望者に対し告知義務があります。
売買・賃貸契約を締結する前に、重要事項として文章化し宅建士の資格をもつスタッフが説明をする必要があります。
もしもこの告知を怠ってしまうと、賃貸および売買契約の解約だけにとどまらず宅地建物取引業法違反となり損害賠償が発生する可能性があります。
過去に、自殺があったことの告知を行わなかった業者の弁護士に対し慰謝料や賃料などあわせて100万円以上もの支払い命令がなされた判例も存在します。
売却の際は不動産買取業者に頼むと◎
孤独死があった物件では通常の不動産売却方法ではなかなか買い手がつきません。
そのため不動産買取業のプロに買取を依頼することで、時間と手間の削減につながります。
株式会社林商会では、特殊清掃とご一緒に不動産売却のサポートもさせて頂いております。
不動産売却についてもご相談お待ちしております。
最近では孤独死保険も登場
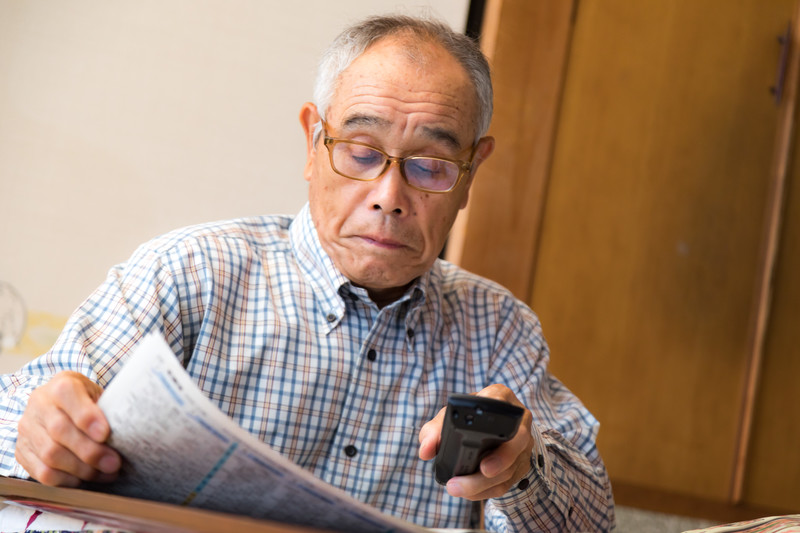
孤独死保険には「家主型」「入居者型」の2種類があります。
家主型はオーナーが加入し、入居者型は借主が加入する保険です。
いつどこで孤独死が起こっても不思議ではない世の中ですので、備えておいてはいかがでしょうか。
「家主型」孤独死保険
家主型はオーナーが保険料の支払いを行いますが、万が一孤独死があった場合に一定期間の家賃損失をカバーできるプランもあります。
集合住宅の場合、保険料は1戸室ごとに月額数百円に設定されていますが、保険会社によっては1棟ごとの月額家賃総額に対応した料金設定となる場合もあります。
家主型の孤独死保険を取り扱う保険会社をいくつか紹介します。
気になる保険があれば、電話して相談してみてはいかがでしょうか。
【無縁社会のお守り:アイアル少額短期保険株式会社】
原状回復費用保険金、事故見舞金、さらに家賃損失補償保険金がついています。
空室期間と家賃値下げ期間の家賃補償があるのが特徴です。
【大家の味方:株式会社あそしあ少額短期保険】
修理費用の保険金と臨時費用保険金がおります。
家賃損失補償はありませんが、修理費以外に発生した費用が補償されます。
【あんしん総合保険:少額短期保険 ハウスガード 株式会社】
家賃損失額、修理費用保険金、遺品整理用保険金、事故時諸費用保険金がついています。
家賃損失額は、孤独死以外にも火災や水災などの災害にも適用されます。
「入居者型」孤独死保険
入居者型は、入居者が加入する保険です。
孤独死だけを補償するのではなく、家財保険の補償内容のひとつとして孤独死をカバーしているのが入居者型孤独死保険の特徴です。
孤独死保険を取り扱う保険会社をいくつかご紹介します。
【ライフアシスト家財保険:ユーミーLA少額短期保険株式会社】
保険料は2年間で20,000円ほど。
孤独死を含め家財に関するほぼすべての損害をカバーしている保険です。
【賃貸くらし安心保険プラス:セーフティジャパン・リスクマネジメント株式会社】
保険料は2年間で16,000円ほど。
孤独死による室内の特殊清掃費用と遺品整理費用をセットで100万円まで補償してくれます。
【住まいるパートナー:アクア少額短期保険株式会社】
保険料は2年間で13,000円ほど。
孤独死による損害の復旧費用として100万円を計上しています。
孤独死保険の選び方
孤独死保険はどの点を比較して選んだら良いのでしょうか。
【家主型孤独死保険の選び方】
孤独死が起こってしまった場合、入居者型の保険で室内の原状回復はできても、次の入居者が決まるまでの家賃損失の補償はできません。
小さなアパートであれば月額数百円の保険料はお守り代わりに加入していて損はありませんが、部屋数の多いマンションなどは保険料も大きくなります。
支払う保険料に対して得ることができる補償は見合うものであるのか、家賃損失の補償はどのくらいの期間もらえるのかを比較・検討しましょう。
【入居者型孤独死保険の選び方】
入居者型の孤独死保険は、家財保険の一部です。
孤独死のみを扱う性質ではないため、孤独死がもたらす損害をどのくらいカバーしてくれるのかは保険会社によって異なります。
また孤独死が起こってしまった場合、通常借主の相続人に保険金が支払われます。
相続人がいない場合は補償の対象外となってしまう可能性がありますので、そういった場合は家主に対し復旧費用が支払われるのかを確認することが大切です。
各社に資料請求や電話相談をしてみるなど、自分が求める補償を比較・検討してみましょう。
まとめ【孤独死への対処、負担を少しでも軽く】
孤独死する人は、誰にも看取られることなく一人孤独に亡くなっていきます。
本人が悲しい末路をたどるだけでなく、残された家族や大家さんが大きな負担を背負うのも事実でしょう。
孤独死しないに越したことはありませんが、もしもに備えておくと直面した際も慌てないでしょう。
孤独死保険への加入はおすすめ
孤独死は高齢の一人暮らしの方だけのものと思ってしまいがちですが、そうではありません。
コロナ禍もあり部屋で過ごす機会も多くなった今、高齢者だけではなく若い一人暮らしの方にも十分起こり得ます。
万が一孤独死が起こってしまった場合に、まとまった金額を受け取れる孤独死保険はとてもありがたいものです。
家主の方は積極的に加入の検討を、入居者の方は現在入っている家財保険の特約をチェックしてみましょう。
特殊清掃は株式会社林商会へ

株式会社林商会は、事件現場特殊清掃士の資格を持ったスタッフが在籍しており、特殊清掃業務を行っています。
徹底した清掃からリフォーム・半永久的な抗菌処理まで、お困りのお部屋の問題を解決いたします。
遺品整理や遺品供養も承っており、「ゴミではなく、モノとして。」をコンセプトに故人の大切な思い出をお取り扱いいたします。
孤独死はいつ起こるか誰にも分かりません。365日24時間体制で受け付けております。
最短でその日のうちに無料お見積りも可能ですので、もしもの際はご連絡ください。
孤独死について詳しく知りたい方はこちらの記事もお読みください。
▼【孤独死】なぜ急増?原因と対策、実際の事例や発見時の対処方法まとめ




アイキャッチ.png)

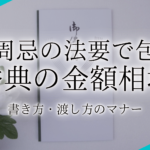
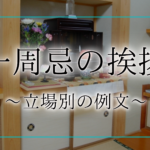

アイキャッチ.png)