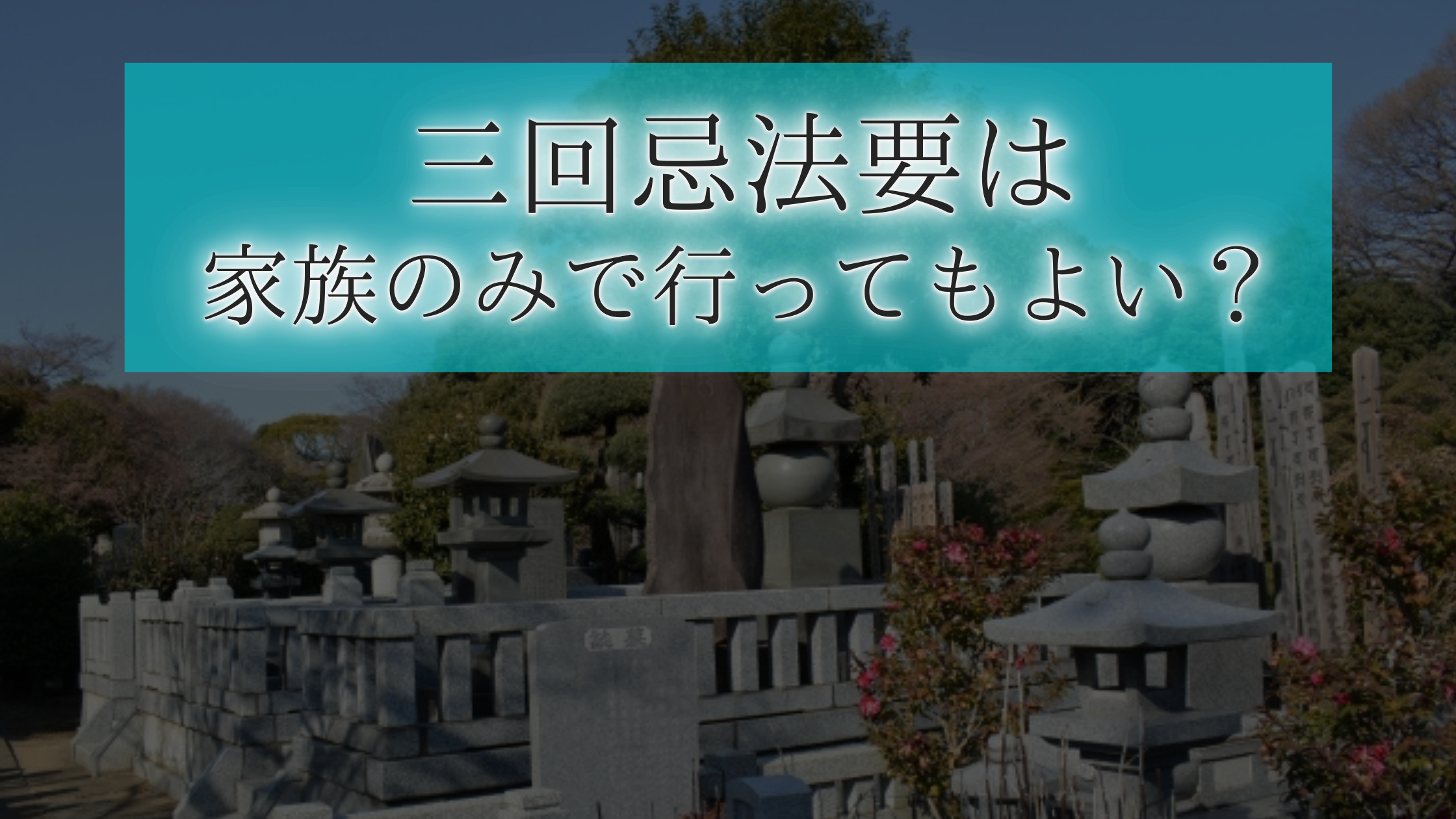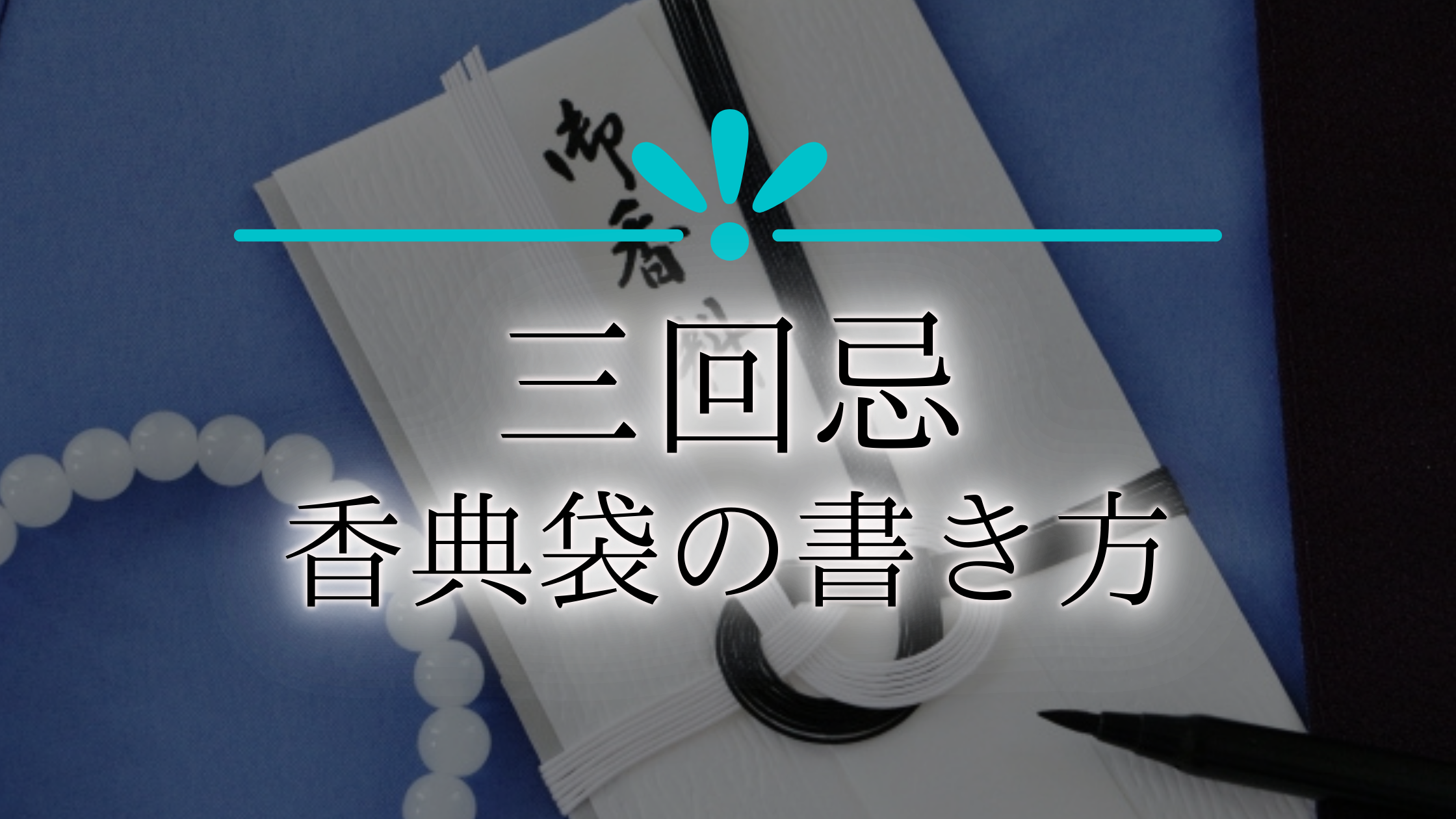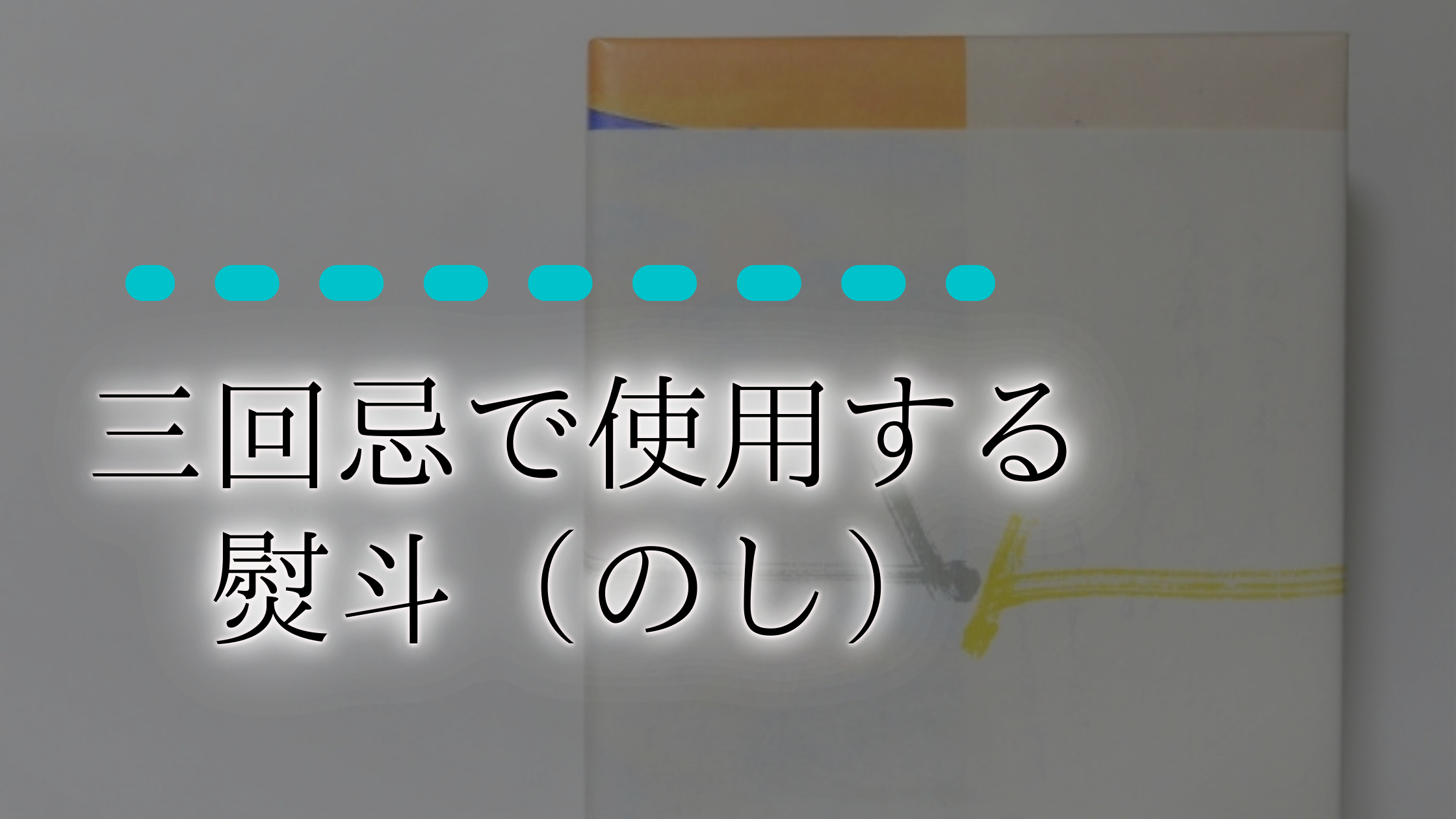一周忌方法で包む香典の相場は、3千円~1万円程度です。ただし、故人との関係性によって変わります。
香典を渡すときには書き方やマナーも理解しておきたいですよね。
今回この記事では、故人との関係性ごとの金額相場、書き方、渡し方のマナーなど詳しくご紹介します。
マナーを知らず恥をかくといったことが内容にしたいですね。
一周忌について詳しくはこちらの記事をお読みください。
▼一周忌とは?マナーや準備について解説
目次
一周忌で包む香典:金額の相場は?

一周忌に出席することになった場合、香典はどれくらいの額を包むのが一般的でしょうか。
間柄が親族の場合やそれ以外の場合など、ケース別でみてみましょう。
故人が親の場合
故人が親の場合の相場は3万円~10万円ほどでしょう。
故人が親ということは、故人からみれば我が子。故人にとても近い存在です。
喪主を務める場合は必要ありませんが、兄弟または親戚が喪主となり一周忌に参列する場合は香典を渡すことがマナーです。
その額は収入によって考慮されることも多いとされています。
例えば就職したての場合は3万円のこともありますし、それなりに年齢を重ね、役職や年収も相応である場合は10万円以上包むこともあります。
義両親の場合
故人が義両親の場合の相場は3万円~10万円ほどでしょう。
配偶者の親ですから、自分の親が亡くなった時と同じ額を包みます。
故人と同居していても別居していても、相場は同様です。
祖父母の場合
祖父母が亡くなった場合は、1万円から3万円が相場でしょう。
この金額は、孫の年齢や収入によっても変動します。孫本人が未成年の場合は必要ありません。両親が用意する香典に未成年の孫の分も含まれると考えるためです。
孫が成年してはいるものの就職して間もない場合は1万円程度、ある程度収入を得ていれば3万円程度を包むのが良いでしょう。
叔父・叔母などの親戚の場合
叔父・叔母などの親戚が亡くなった場合は、1万円から3万円程度が相場でしょう。
叔父・叔母(伯父・伯母)は両親の兄弟にあたりますので、近しい親戚と言えます。
この金額も、年齢や収入によって変動することがあります。祖父母の場合と同様、就職してあまり年数が経っていなければ1万円ほど、ある程度の年数を経ていれば3万円ほどとなります。
なお,、故人からみた甥・姪が未成年であれば香典を渡す必要はありません。
それ以外の親戚においては近しい親戚ではなくなりますので、5千円から1万円ほどが相場でしょう。
とはいえ血筋は遠くても故人と深くお付き合いをしていたのなら、多めに包むこともあります。
知人や友人の場合
知人や友人などが亡くなった場合の相場は、5千円から1万円ほどでしょう。
一周忌の際、多くの場合「精進落とし」や「お斎(おとき)」などといった会食の席が設けられます。この会食に出席するかどうかによって、香典の金額は変動します。
出席するのであれば多めに、法要のみの場合には通常の金額を包むと良いでしょう。
連名で包む場合
自分ひとりで香典を渡すのではなく、複数人で連名として1つの香典を包む場合がありますね。
いくつかのパターンに分けて紹介します。
友人・知人同士の場合
友人・知人同士の複数人でひとつの香典を包む場合、知人や友人が亡くなった場合に個人で包む金額の相場が5千円から1万円ということを踏まえて包みます。
会食に出席する場合は多めに包みますので、一人あたり3千円程度。法要のみの場合は千円から3千円程度となります。
この時に注意したいのが、合計金額です。縁起が良くないとされる4や9の数字は避けることが望ましいです。
トータルの金額が4千円や9千円になってしまう場合は、切り上げて5千円・1万円に調整しましょう。
また連名で香典を出した際は、その人数分の香典返しをいただくことになります。
もし連名となる人数が多く、一人あたりが出す金額が少額である場合は、香典返しを辞退するなど施主の方の負担を配慮することも大切です。
夫婦や家族の場合
夫婦や家族の場合、そろって一周忌に参列するのであればお付き合いが深い親戚であると言えます。
会食に出席するのであれば家族あわせて3万円程度が相場となります。
家族の人数が多い場合には、会食にかかる料金もありますので施主の方の気持ちを汲んで多めに包むのが良いでしょう。
法要のみの出席であれば合わせて2万円程度の金額が目安となります。
この際も、香典返しは辞退するか家族で1つにするなどの配慮を忘れないようにしましょう。
一周忌での香典袋の書き方

香典袋といっても、御霊前、御仏前などさまざまな名目が存在します。
一周忌での香典袋は、どのようなものを使えば良いのでしょうか。
表書き
香典袋の名目は、宗教や宗派によって異なります。
仏教の場合
仏教の一周忌法要において一般的に使用される香典袋は「御仏前(御沸前)」です。
葬儀や四十九日の法要の際に出す香典の表書きは宗派によって違いますが、仏事の一周忌法要であれば宗派に関係なく「御仏前」を準備しましょう。
神式の場合
神式では「御神前」を使用します。
神道においては、亡くなった人はその家の神様になると考えられているためです。御神前の香典袋が見つからない場合は、手書きでもいいですし「御霊前」を使用しても失礼ではありません。
また神式ではご焼香やお線香ではなく玉串を捧げることから、「御玉串料」「御榊料」を使用することもあります。
キリスト教の場合
キリスト式では主に「御霊前」を使用します。
キリスト式は大きくカトリックとプロテスタントという宗派に分けられます。
それぞれ「御花料」「御ミサ料」の名目が使用されますが、葬家の宗派がどちらかわからない場合は御霊前を使用すれば間違いが避けられるでしょう。
名前の書き方
表書きの下に名前を記入しますが、個人なのか連名なのかで書き方が異なってきます。
個人の場合
個人の場合は、表書きの下半分にフルネームを記入します。
表書きが書いてある短冊状ののしを水引に挟みこむ形式の香典袋がありますが、挟み込むだけだと集計の段階で抜け落ちてしまうことがあります。
こういった形の香典袋を使用する際は、短冊にフルネーム記入し水引に挟んだあと、上部をのりづけして落ちないようにするなどの配慮をすると混乱を防ぐことができます。
3名以下の場合
連名にする人数が3名以下の場合は、まず右端に「〇〇学校同級生」「△△会社営業部」など共通する団体名や所属などを記入します。
その隣に目上の人から順にフルネームを記入します。
その際、個人個人が記入するのではなく代表の方が3名分の記入をするようにしましょう。
4名以上の場合
4名以上での連名の場合、表書きの下半分に会社名や団体名、および代表者の役職とフルネームを記入し、全員のフルネームと金額を記入した別紙をお金と一緒に入れます。
決まりはありませんが、袋の表に別紙ありと記入しておくと、葬家の方も包んでくださった方の名前を見落とすことがなく混乱を避けられるでしょう。
夫婦や家族の場合
夫婦や家族で出す場合は、一般的には家族の代表のフルネームを記入します。
夫婦の名前を記入するならば右側に夫婦の代表者、その横に配偶者の下の名前を記入します。
中袋の書き方
中袋は、お金を直接入れる封筒を指します。
お金を入れる前に、住所と氏名、金額を記入しましょう。
中袋に記入欄が印刷されていることが多いので、それに従って記入します。
また金額の書き方は旧字体および漢数字が使われることが一般的で、例えば3万円包むのであれば、「金 参萬円也」と記入します。
なお、故人とは交流があっても喪主の方との交流がない場合は、中袋に故人との関係を記入しておくと親切です。
結婚前に交流があったが苗字が変わったという場合も、中袋に旧姓を記入しておくと親切です。
詳しくはこちらの記事をお読みください。
金額・書き方以外のマナー

香典を渡す上で、金額や書き方以外にもマナーがあります。
知らず知らずのうちに失礼なことにならないよう、注意をしておきましょう。
香典袋に使用できるペンの種類
葬儀の際にお渡しする香典袋には、薄墨で記入することが望ましく濃いインクのペンや簡易的な筆記具であるボールペンは避けられます。
薄墨で書く理由は、「あなたが亡くなった悲しみの涙で墨も薄れます」という気持ちがこめられるためだと言われています。
しかし一周忌では悲しみから立ち直る時期であるため、薄墨を使用せず黒いインクまたは墨で書くことが多くなっています。
中袋にはボールペンを使用できますが、誤字があった場合は修正テープなど使用せず書き直すようにしましょう。
香典袋に包むお札のマナー
中袋にお札を入れる際にもマナーがあります。
新札は準備しないと手に入らないことから「香典となるお金を事前に用意していた」という意味になるため使用しません。
かといってボロボロすぎず適度にユーズド感のあるお札を使用しましょう。
お札を入れる向きは、裏返してお札の顔を下(底側)に向けてそろえて入れます。
香典の渡し方
一周忌の法要では、葬儀の時のように会計窓口は設置しないことが多いです。
会場に到着したら施主および葬家の方にご挨拶をし、さりげなく袱紗から香典を取り出し「ご仏前にお供えください」とひとことかけてお渡ししましょう。
なお都合が悪く法要に出席できない場合には、現金書留にて香典を郵送で提出することもできます。
その際は事前に郵送をしたいことを伝え、どの住所に送ったら良いのかを確認しましょう。
香典返しのマナー
香典をいただいたら、香典返しをお渡しします。その相場はいただいた金額の二分の一から三分の一が相場といわれています。
かといって参列してくださる方がどのくらいの金額を包んでくださるのか予想はできません。
そのため5千円の方用、1万円の方用、3万円以上の方用など何パターンか分けて用意しておくとスマートにお渡しができます。
「のし」については、一般的に「志」を使用します。
下半分には、葬家の苗字、もしくは苗字+家を記入します。
詳しくはこちらの記事をお読みください。
まとめ

香典の金額の相場と、記入の仕方やマナーを解説しました。
たくさんの方が参列する通夜や葬儀とは違い、一周忌に訪れるのはごく近しい方のみであることが一般的です。
だからこそ心を尽くし、故人や葬家に寄り添いながら故人の旅立ちを祈りたいものですね。




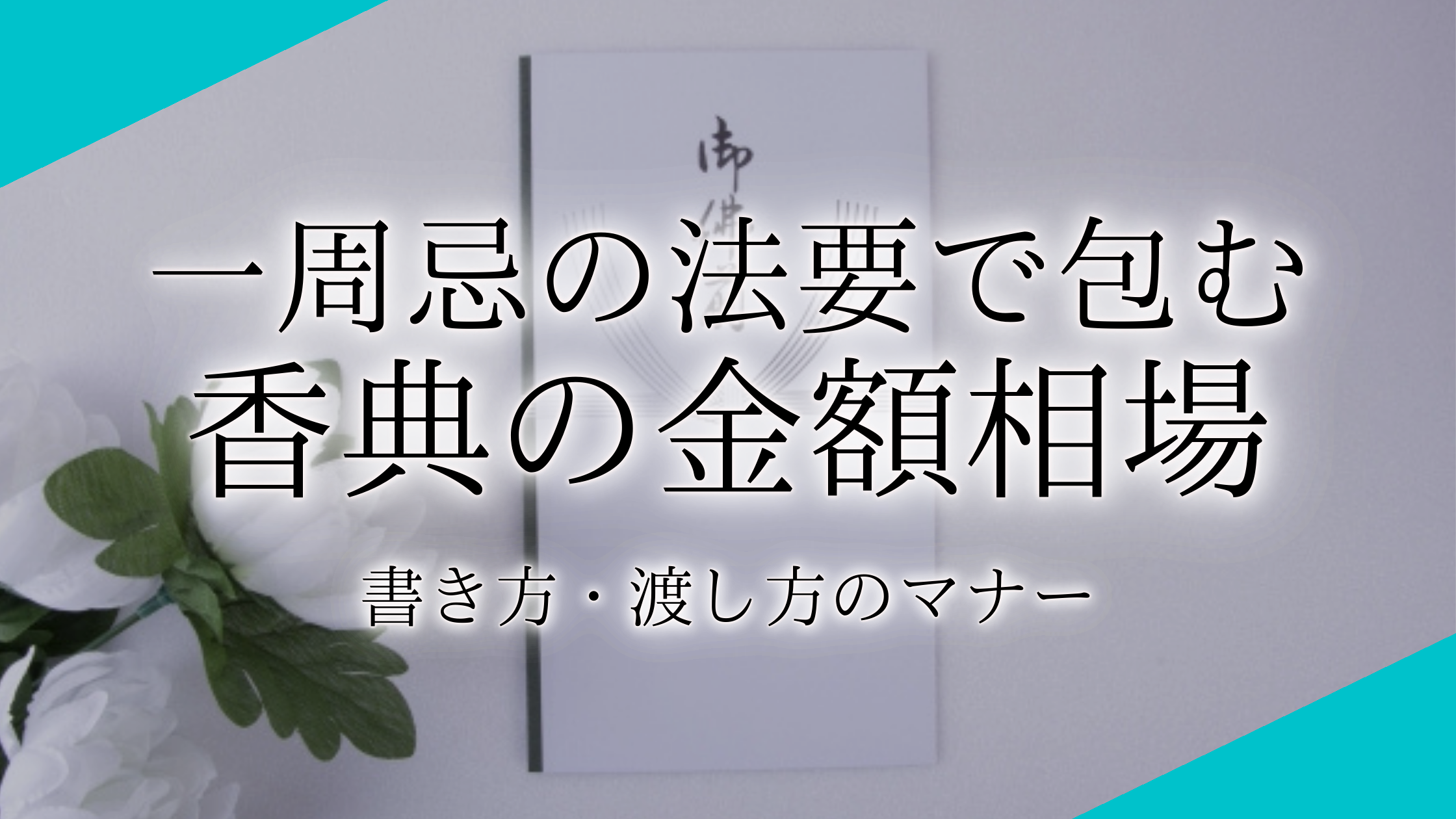

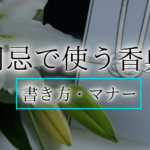
アイキャッチ-150x150.png)