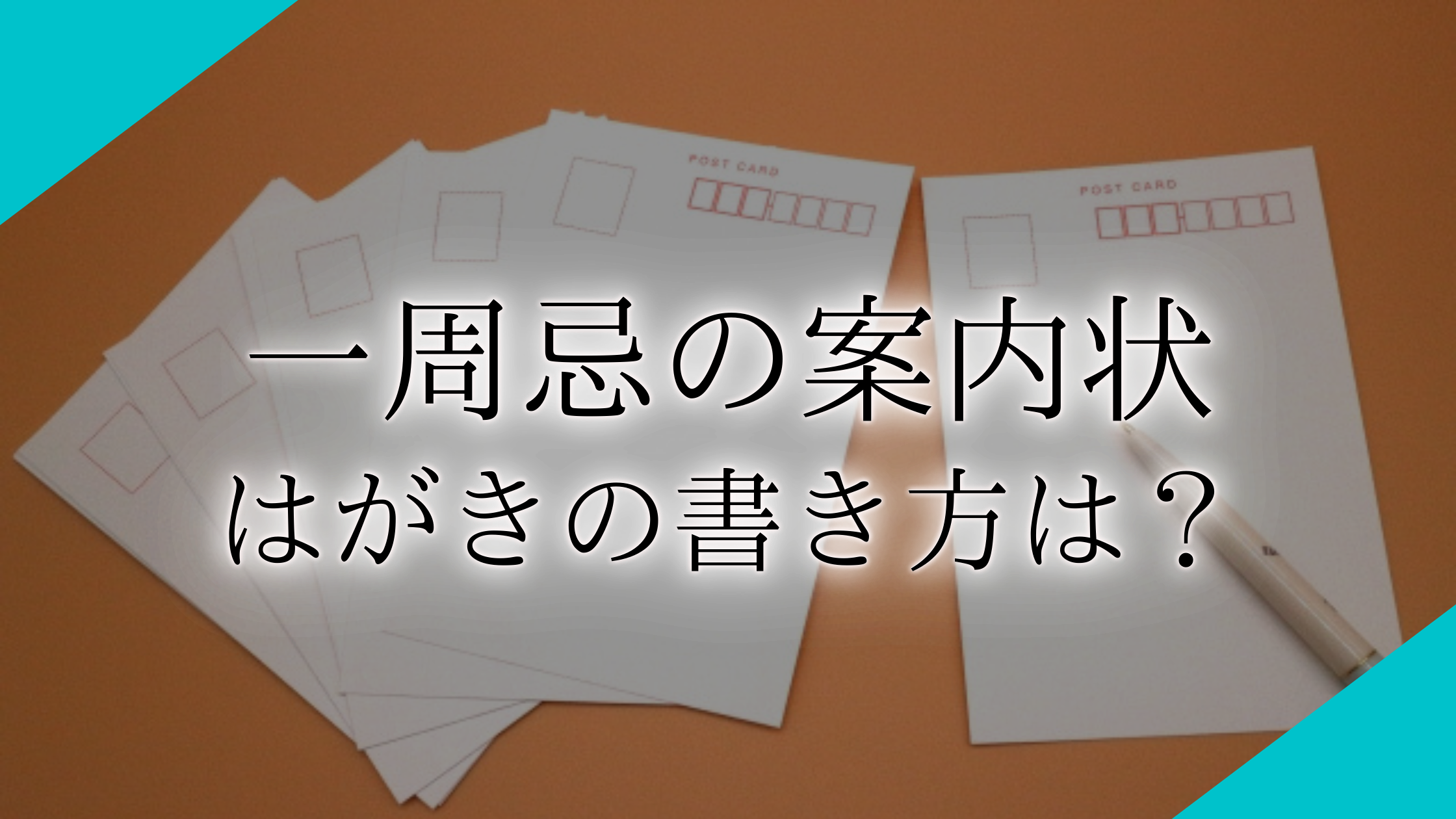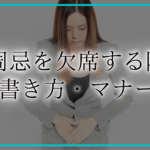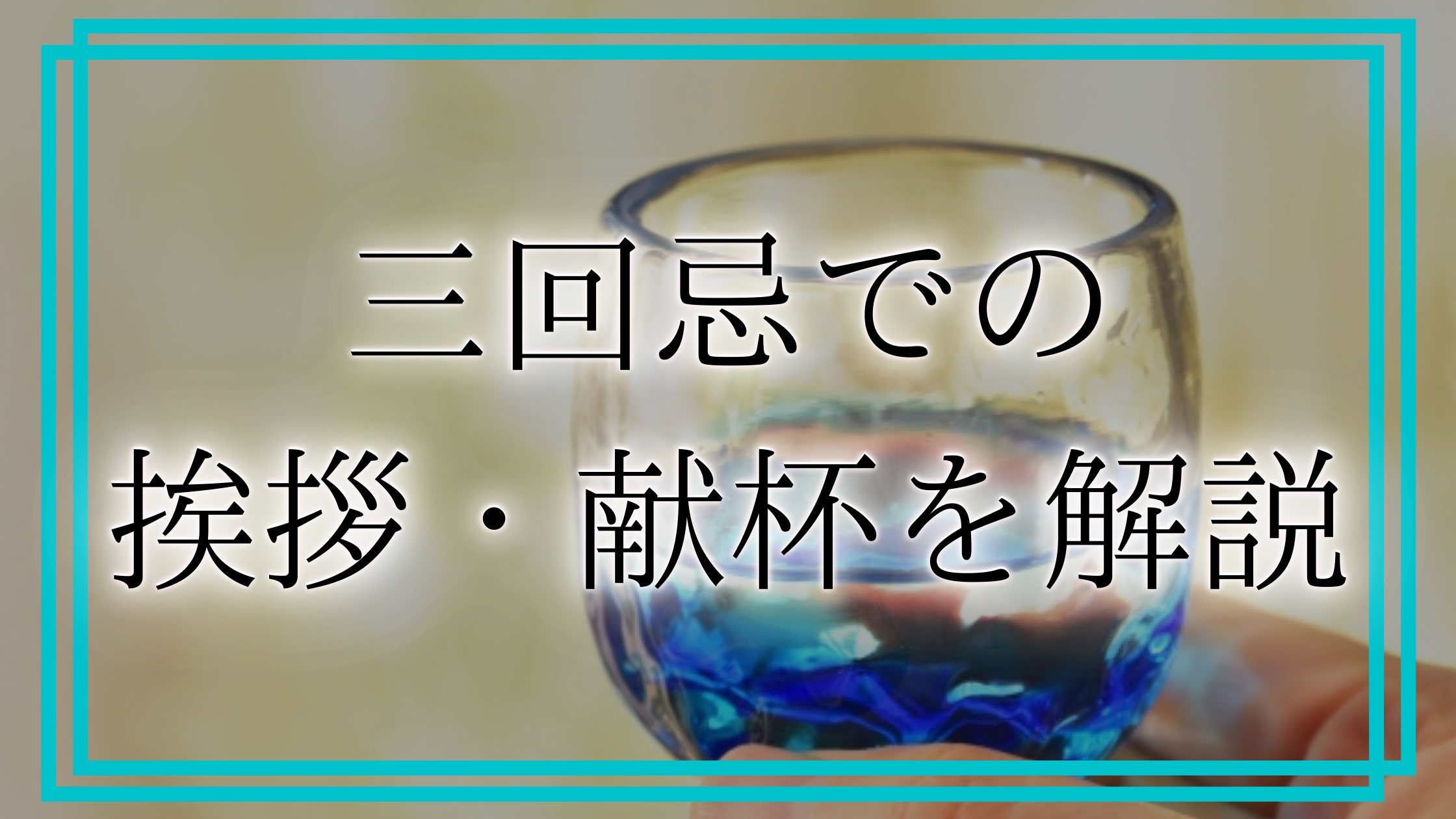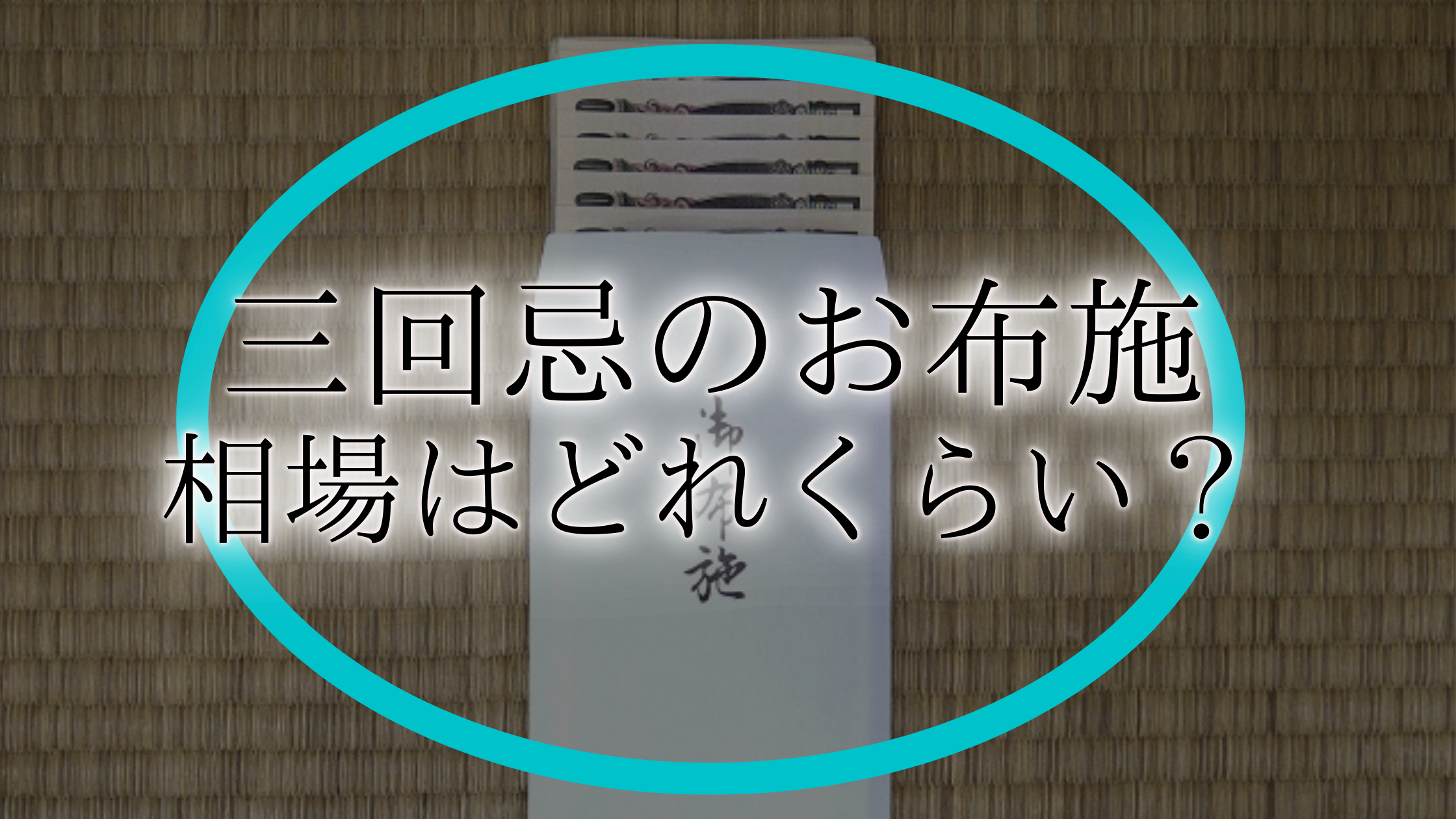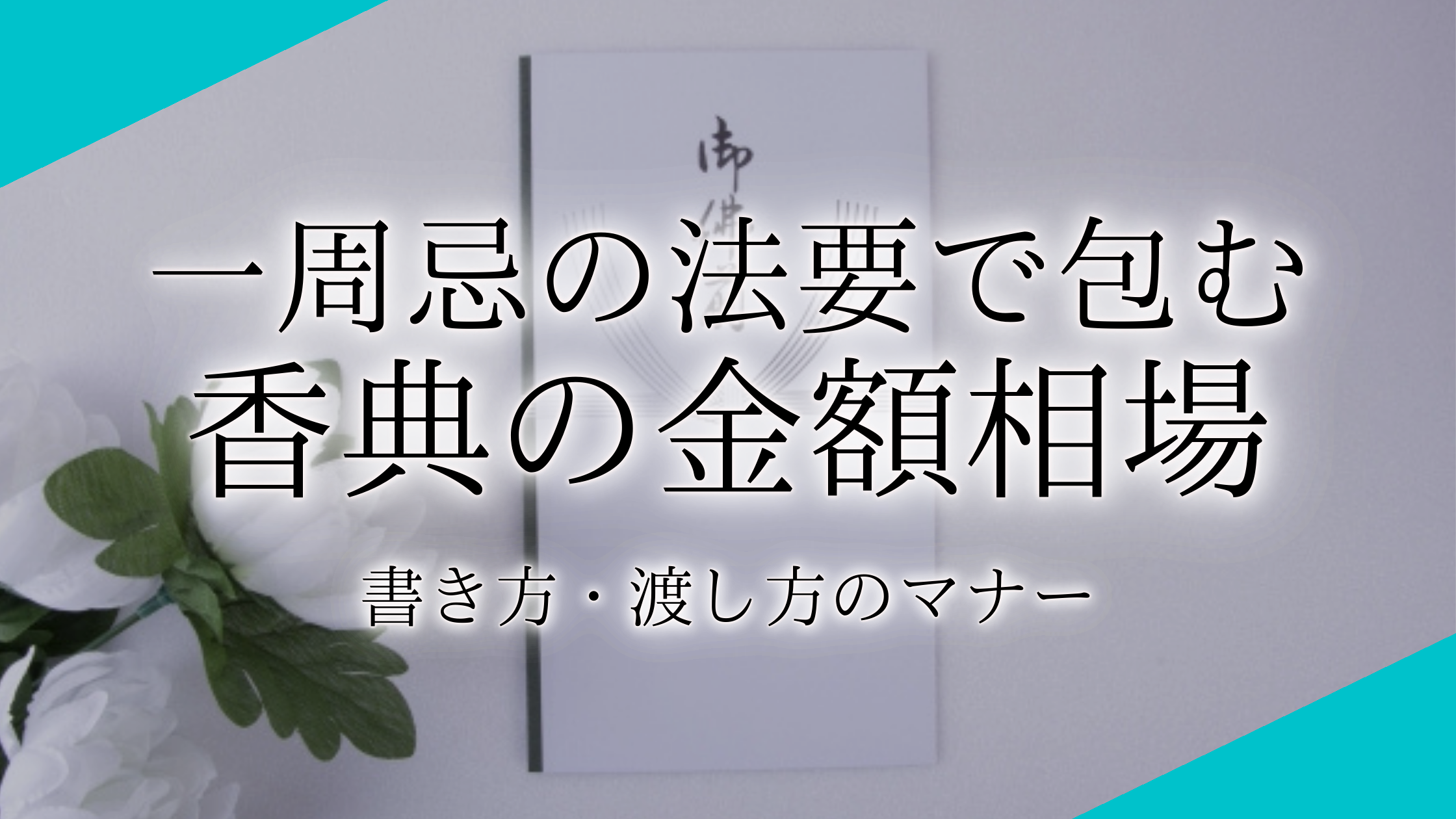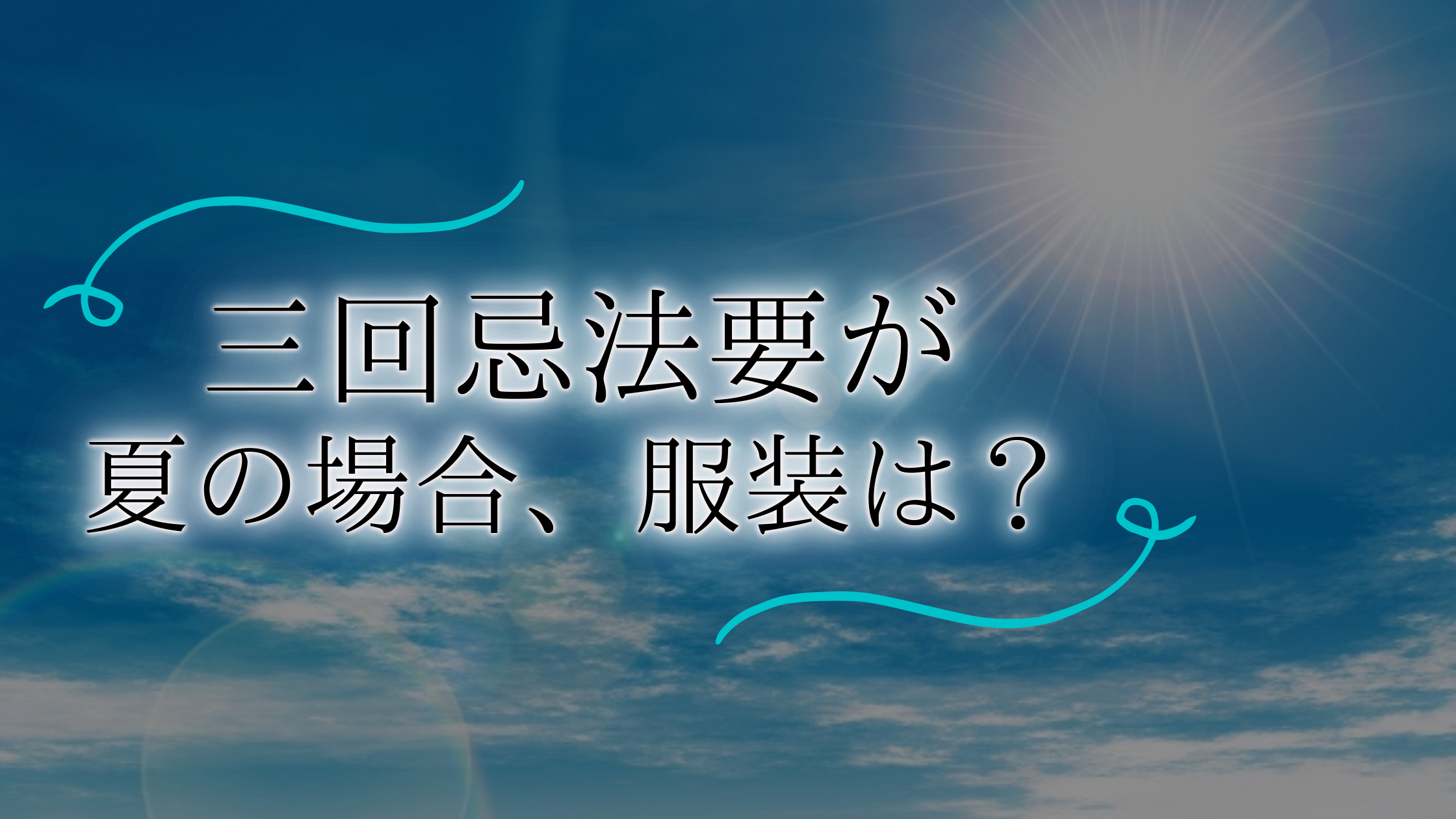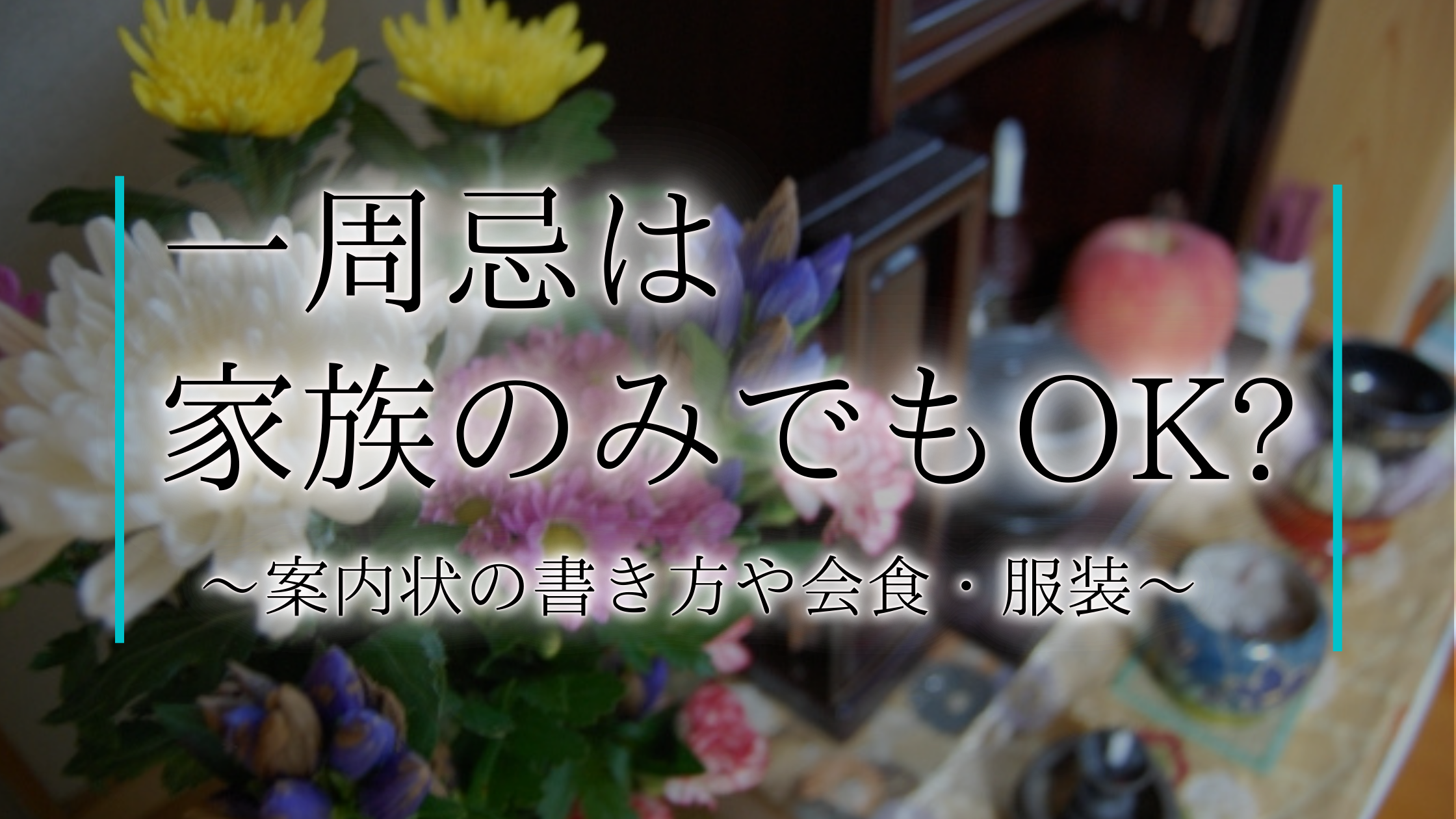一周忌法要では親族や参列者の方へ法要の開催を知らせる案内状を送ります。
案内状には特有のマナーや書き方があり、知らずに送ってしまうと参列者に対し失礼ともなりかねません。
この記事では、案内状に記載すべき内容と文例、送り方までわかりやすく解説します。
一周忌について詳しくはこちらの記事をお読みください。
▼一周忌とは?マナーや準備について解説
一周忌案内状に記載する内容

ここからは、一周忌の案内状で記載すべき内容を紹介します。
一周忌の案内状に記載する内容をまとめると下記の通り。
| ・差出人と故人の関係・故人の氏名 ・頭語・結語 ・時候の挨拶 ・一周忌法要の日時と会場 ・お斎について ・差出人の住所・氏名 ・返信の依頼 |
それでは各項目について詳しく見ていきましょう。
差出人(施主)と故人の関係・故人の氏名
誰の法要が行われるのかを明確にするために、差出人(施主)と故人の関係・故人の氏名を記載します。
差出人(施主)から見て、故人が母にあたる場合は「亡母 ○○ ○○」のように書きます。
また、故人の何回忌の法要なのかといった付加情報も、必ずお知らせしましょう。
頭語・結語
一周忌の案内状では、冒頭に「頭語」、文末には「結語」を記載します。
頭語には「こんにちは」、結語には「さようなら」のような挨拶にあたる意味合いが含まれており、これらは必ずセットで記載するというルールがあります。
例:頭語「拝啓」結語「敬具」
例:頭語「謹啓」結語「謹言」
時候の挨拶
頭語の後には、季節に合った「時候の挨拶」を書きます。
時候の挨拶とは、季節に合わせた心情などを表すもので挨拶状などの改まった文章には頭語の後に記載することがマナー。
また、時候の挨拶の後には相手の健康や安否を気遣う一文を書きます。
例:「皆様にはますますご壮健のことと拝察いたします」など
月ごとの頭語を2種ずつご紹介しますので、一周忌を執り行う時期に合う時候の挨拶はどれか、チェックしてみてください。
| 1月 | 極寒の候・厳冬の候 |
| 2月 | 晩冬の候・余寒の候 |
| 3月 | 春分の候・早春の候 |
| 4月 | 春和の候・春風の候 |
| 5月 | 万緑の候・新緑の候 |
| 6月 | 入梅の候・小夏の候 |
| 7月 | 盛夏の候・仲夏の候 |
| 8月 | 晩夏の候・暮夏の候 |
| 9月 | 初秋の候・涼風の候 |
| 10月 | 秋晴の候・仲秋の候 |
| 11月 | 晩秋の候・向寒の候 |
| 12月 | 初雪の候・師走の候 |
法事の日時・会場
特に、日時や場所は分かりやすく記載しましょう。
挨拶状を受け取った方は、この日時を見て参列のために予定や仕事を調整します。
そのため一周忌法要の日付・開始時刻が解りやすいようしっかりと記載する必要があります。
また、この時に西暦では記載しないようにしましょう。
会場に関しては、自宅で執り行うのであれば「自宅にて」でも構いません。
しかし、ホテルなどの会場で法要を行うのであれば、会場となる部屋の名前も加えて記載すると参列する方も当日迷うことなく、親切です。
そして、会場となる場所を記載するときは、会場の名称だけではなく住所・電話番号も記載するとより良いでしょう。
お斎(会食)について
一周忌法要を行う場所と異なる会場で会食を行う際は、会食を行う会場名や住所、アクセス方法なども明確に記載しましょう。
一周忌法要をホテルで行った場合など、移動がなくその会場内で会食をする際は「法要後は ささやかではございますが 粗宴をご用意いたしております」と一文付け加えるのみでも構いません。
差出人(施主)の住所・氏名
差出人の名前はフルネームで記載し、出欠の返信様に住所も記載します。
また、参列する予定だった方が何らかの事情で欠席しなければいけなくなってしまった際など、すぐに連絡がとれるように電話番号も記載しておくと良いでしょう。
宛名・宛先
一周忌に招く方(案内状の送り先)の宛名と宛先を記載します。
夫婦の場合や子どもがいる、など複数人の場合は連名で記載しましょう。
返信の依頼
一周忌の出席の有無、返信の期限を記載します。
相手型がスムーズに返事を出せるように、返信用ハガキを用意することも忘れないようにしましょう。
返信用の宛先にあたる自身の名前の下には「行」と記載します。
一周忌案内状の例文

仏式で執り行う場合
仏式で執り行う場合は、縦書きで句読点を使わずに記載します。
| 謹啓 紅葉の候 皆様にはお健やかにお過ごしのことと存じます 来る○月○日には 亡母○○の一周忌の命日を迎えます つきましては ○月○日に 左記のとおり法要を営みたいと存じます 法要後 ささやかではございますが 粗餐の席を設けさせていただいております ご多忙中のところまことに恐縮ではございますが ぜひともご参会賜りますようご案内申し上げます 日時 ○月○日(○曜日) 午前○時より 場所 〇〇○ 住所 〇〇○〇〇○〇〇○ 電話番号 〇〇○-〇〇○-〇〇○○ 令和○年○月○日 喪主 ○○○○○(氏名) 住所 〇〇○〇〇○〇〇○ 電話番号 〇〇○-〇〇○-〇〇○○ お手数ですが、○月○日までに返事をお知らせください 謹白 |
神式で執り行う場合
仏式で一周忌にあたる法要は、神式では「一年祭」と呼ばれています。
神式での一年祭の案内状の例文は下記の通りです。
| 謹啓 残寒の候 皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます このたび 亡父○○の一年祭を左記のとおり営みたいと存じます まことに恐縮ではございますが ぜひともご臨席たまわりたくご案内申し上げます 日時 ○月○日(○曜日) 午前○時より 場所 〇〇○ 住所 〇〇○〇〇○〇〇○ 電話番号 〇〇○-〇〇○-〇〇○○ 令和○年○月○日 喪主 ○○○○○(氏名) 住所 〇〇○〇〇○〇〇○ 電話番号 〇〇○-〇〇○-〇〇○○ 恐れ入りますが、○月○日までに返信はがきにて出欠席の有無をお知らせください 謹白 |
キリスト式で執り行う場合
キリスト式でも、カトリックとプロテスタントでは文言が異なります。
ここでは、カトリックを信仰している方が案内状を出す場合の例文を紹介します。
| 故〇〇が神の下に召されてから 一年が経ちました つきましては 左記の日程で追悼ミサを行うことになりました お忙しい中恐縮ではございますが、ぜひご来席していただきたく、こちらにご連絡させていただきました 日時 ○月○日(○曜日) 午前○時より 場所 〇〇○ 住所 〇〇○〇〇○〇〇○ 電話番号 〇〇○-〇〇○-〇〇○○ 令和○年○月○日 喪主 ○○○○○(氏名) 住所 〇〇○〇〇○〇〇○ 電話番号 〇〇○-〇〇○-〇〇○○ お手数ですが、○月○日までに出席の有無のお返事をお知らせください |
キリスト教の場合、供養という概念はなく死ぬと神の元へ帰っていくという考えがあります。
仏教や神道などで使用する言葉は利用することができないので、注意してください。
親族・家族のみで一周忌を行う場合は?

近年は、親族や家族のみでひっそりと一周忌を行うという方も多いですよね。
ここからは、親族や家族のみで一周忌を行う場合のマナーを紹介します。
招待しない人には挨拶状を
身内のみで一周忌を行う場合には、法要が終わった後に挨拶状を出しましょう。
基本的に葬式や通夜に参加した人に、1ヶ月程度で送るのがマナーとされています。
一周忌に呼ばれないことに不快な思いを感じる方もいらっしゃいますので、丁寧に対応しましょう。
挨拶状の場合も、案内状と同様に句読点を使用してはいけません。
親しい家族・親族のみの一周忌でも案内状は送るべき?
親しい家族や親族のみで一周忌を行う場合でも、案内状には日時や場所などが記載されているため、基本的に参加してほしい方に案内状を送るのがマナーとされています。
関係性にもよりますが、案内状を送らずに電話やメールなどで済ませるという方も多くいます。
電話で知らせたからといって、マナー違反になることはありません。
一周忌案内状のマナーについて
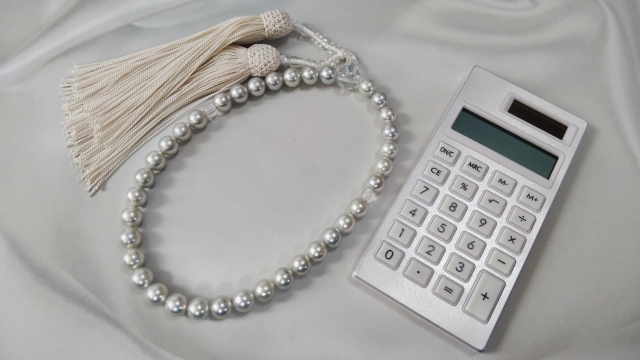
ここからは、一周忌の案内状を書く上で、必ず押さえておかなければいけないマナーを紹介します。
句読点は使わない
法事や法要などの案内状を送る場合、「、」や「。」などの句読点は使用しません。
句読点がなく読みづらくなってしまう場合は、適度に文字の間隔をあける・改行するなどで対応すると良いでしょう。
二重封筒にしない
不幸が重なると言い伝えられている二重封筒は、使用しません。
一周忌の案内状に使用する封筒は、白い無地の封筒を利用しましょう。
往復はがきでもOK
近年は往復はがきを利用して、一周忌の案内状を送る場合も増えてきています。
往復はがきで案内状を送ること自体がマナー違反という訳ではありませんが、年配の方では不快な思いを抱く方がいるのも事実です。
親しい間柄でなければ、できるだけ使用するのは避けたほうがいいかもしれません。
一周忌の日程1か月前には送る
相手側のスケジュールもあるので、遅くとも1ヶ月前を目安に案内状を送るようにしましょう。
早く案内状を送ることで、出欠席の返事も早くいただくことができます。
参列者する方が早い段階で把握できることから、施主側も一周忌の準備をゆっくり行うことができます。
一周忌の案内状を受け取ったら?

ここからは、一周忌の案内状を受け取ったら、どのように行動すべきなのか、そのマナーや行動について詳しく紹介していきます。
1つでも抜けてしまうと、マナー違反となってしまうものばかりですので、ぜひ参考にしてください。
なるべく早く返事をする
一周忌の案内状を受け取ったら、なるべく早く返事を出しましょう。
主催者は、案内状の返事から出欠席を確認し、引き出物や食事の準備をします。
少なくとも届いてから2〜3日で返事を出すのがマナーです。
住所・氏名の「御」を消す
通常、一周忌の案内状には住所や名前の前に「御住所・御芳名」と記載されています。
返信時には、御と御芳名の上に二重線を引きましょう。
さらに、出席や欠席の欄にも御の文字がありますので、こちらも忘れずに消してください。
出席に丸をしたら、下に「させていただきます」や「お招きいただき、ありがとうございます」などの言葉を添えると、より丁寧な印象になります。
やむを得ず欠席する場合
一周忌は、数ある年忌法要の中でも重要度が高い法要です。
なるべく出席すべきですが、止むを得ず欠席する場合は、出席できない理由やお悔やみの気持ちを記載し、お詫びの手紙を同封しましょう。
香典やお供え物を送るのも忘れずに。
一周忌案内状は印刷サービスへの依頼もあり
一周忌の案内状は、必ず自分で行わなければいけないものではありません。
業者や郵便局で案内状の印刷を請け負ってくれるサービスが実施されています。
インターネットで簡単に申し込みすることができます。
案内状印刷料金の相場は?
案内状の相場は、20枚で3000円〜5000円となっています。
業者によっても金額等は異なりますが、封筒の場合値段が高くなる傾向にあります。
まとめ
この記事では一周忌での案内状の書き方やマナーについてご紹介しました。
一周忌のような年忌法要を含む冠婚葬祭には気を付けるべきマナーが多く存在します。
招待される側が気持ちよく法要に参列していただけるよう、マナーには一層の注意を払う必要がありますので、ぜひ本記事を参考になさってくださいね。
一周忌では挨拶にもマナーが存在します。詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
▼一周忌挨拶でのマナーや例文