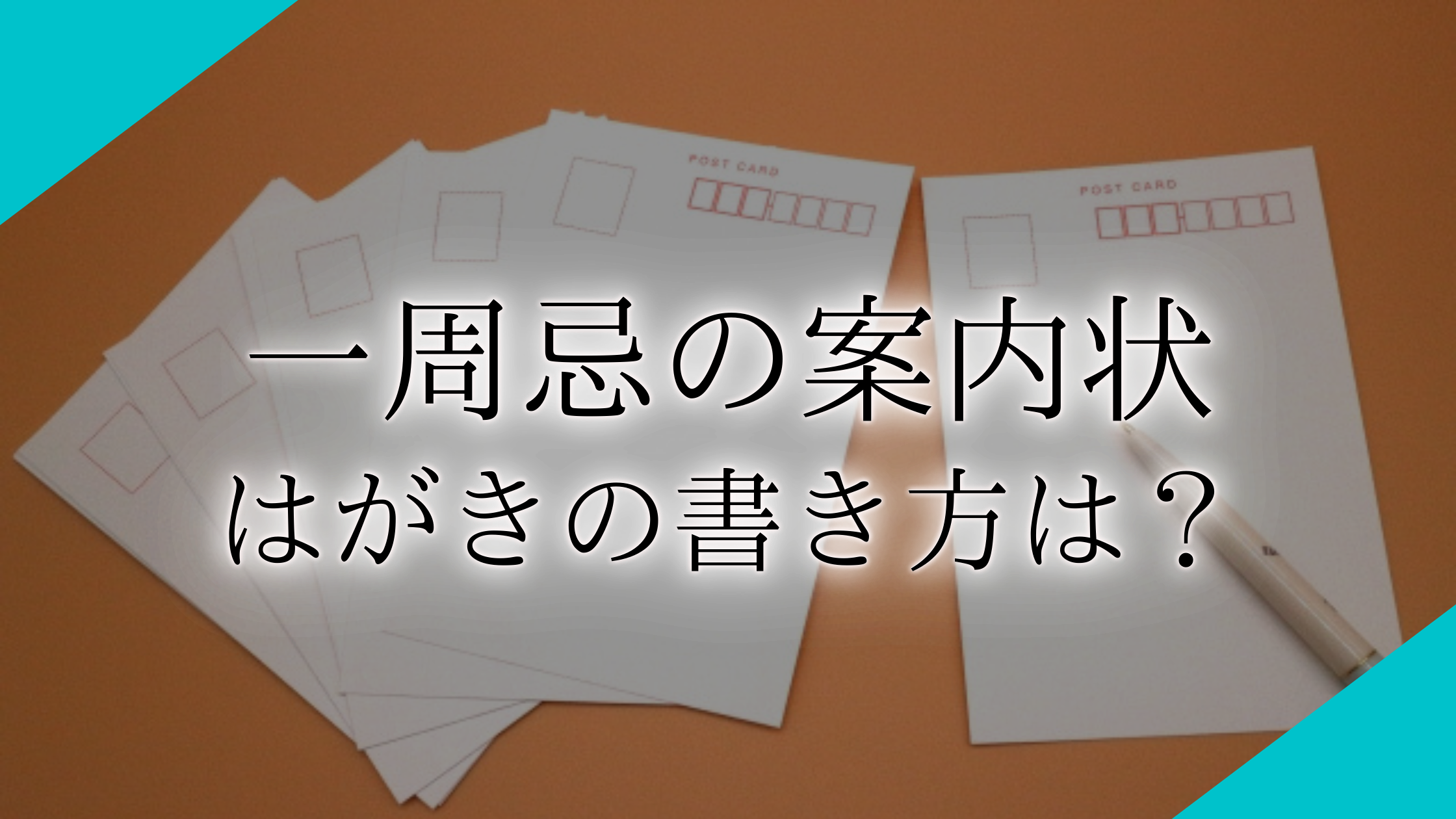仏教の場合、葬儀や法事ではほとんどの人が自分の数珠を持参します。
使い方や持ち方は宗派によって異なるので、この記事で自分の宗派を確認してみてくださいね。
また、記事の後半では数珠に関するマナーもご紹介しています。
恥をかかないためにも、マナーはきちんと心得ておきましょう。
目次
そもそも数珠とは

数珠を知らない人は少ないですが、使い方となると話は別です。
いざ使うときに恥をかかないよう、使い方を覚えておきましょう。
もともと数珠は念仏の回数を数えるためのもの
数珠は本来、念仏を唱える際に何回唱えたかを数えるための道具です。
一説には、数をかぞえる珠(たま)で「数珠」と呼ばれるようになったと言われており、念仏に用いる珠との意味からとって「念珠(ねんじゅ)」とも呼ばれます。
珠が連なる様は、仏と人との縁をつなぐ力を持っていると考えられていて、故人への敬意や哀悼を表すために数珠を持つとされています。
葬儀やお通夜には数珠が必ず必要なのか
日本のお葬式のおよそ8割は仏教式で行われるそうですが、お通夜を含め、数珠を持参する人が多いです。
故人への礼儀としても持っていた方がいいのですが、必ず持って行かなければいけないかというとそうでもありません。
数珠は仏教式で行われる際に用いられる法具で、神道やキリスト教などほかの宗教では必要とされません。
そのため、仏教以外の宗教を信仰し数珠を持ち合わせていない場合は、数珠を持たなくても良いとされているのです。
ただ日本人の一般的常識として、葬儀には数珠が必要と思っている人は多いので参列する葬儀が仏教式であればできるだけ数珠を持参しましょう。
数珠の種類

数珠には本式数珠と略式数珠があり、それぞれに男性用・女性用があります。
本数珠と略式数珠
数珠は複数の小さな珠に糸を通して輪にした法具で、本式数珠と略式数珠に分けられます。
本式数珠とは、文字通り各宗派が正式であると認めた108珠仕立ての格式高い数珠を指します。
108珠の珠数にこだわりを持っていない宗派もありますが、108という数字は人間の煩悩の数を表し、身を護るなどの功徳がある数とされています。
一方、略式数珠は宗派に関わりなく使える実用的な数珠で「片手数珠」とも呼ばれます。
珠の数は本式数珠の半分にあたる54珠や4分の1の27珠などの他、22珠、20珠、18珠などもあります。
男性用と女性用の数珠
数珠は男性用と女性用とでは珠の大きさや数珠全体の大きさに違いがあります。
略式数珠では1つの珠大きさが、男性用で10mm~12mm、女性用は6mm~8mmが一般的です。
本式数珠は主に数珠全体の大きさが異なります。
数珠を左右に広げたときに男性用は、九寸(約27cm)~一尺二寸(約36cm)、女性用は八寸(約24cm)が一般的です。
宗派関係なくお葬式・通夜に使えるのは略式数珠!
使い方を覚えればどの宗派でも使える利便性の高い略式数珠。
ここでは、略式数珠の使い方や持ちかたと購入する際のポイントを解説します。
略式数珠の使い方・持ち方

基本的に数珠は、左手の4本の指を輪の中に入れ親指で軽く押えるようにして持ちます。
諸説ありますが、数珠を左手で持つのは左手が仏様の清浄な世界、右手が現世の人間が住む不浄の世界を表していることに由来しているようです。
手を合わせるときは2通りのやり方があり、1つは左手のみに数珠の輪をかけて合掌する方法ともう1つは両手に数珠の輪をかける方法です。

左手か両手、どちらでも問題はないので持ちやすい方で行ってください。
略式数珠の選び方
略式数珠を選ぶときに一番大事なことは、地域のルールを知ることです。
例えば名古屋や金沢近辺では、葬式には白房の数珠、法事には色房の数珠が使われることが多いようです。
それがルールとして確立されているわけではありませんが、地方の習慣には合わせて購入した方が無難です。
数珠の種類にとりたてて縛りが無ければ、略式数珠は自分の好みで選んで大丈夫です。
素材で言えば、木や木の実、天然石、珊瑚、パール、ガラスなど様々な数珠があります。
本式数珠では素材の意味が重要視されますが、略式数珠では特に気にする必要が無く、房の色も気に入った物を選べます。
最近では、手の小さい男性や手が大きい女性のために長さが調整された略式数珠もあるのでサイズの心配もありません。
ただし、男性用と女性用の区別はあるので注意してください。
弔事という公共性の高い場面では、男性用の数珠を女性が使ったり、その逆だったりするのは良いこととされていません。
宗派別:本数珠の使い方・持ちかた

本式数珠は各宗派の考え方が、数珠の呼び名や形式に反映されています。
数珠の持ち方にも違いがあるので、通夜や葬儀などでのマナーとして覚えておきましょう。
浄土宗
数珠の持ち方は、
| 1.副玉が入っていない方の輪を左手の親指と人差し指の間にかける 2.もう一つの輪を人差し指と中指の間に挟む 3.そのまま握る |
合掌をするときは、
| 1.二つの輪の親珠の位置をそろえる 2.下から両手の親指を入れる 3.親指と人差し指で親珠を挟む 4.房は自分側に垂らす |
浄土宗は、法然を宗祖とする宗派で総本山は知恩院、ご本尊は阿弥陀如来などです。
お念仏の宗派とも呼ばれ、「南無阿弥陀仏」と念仏をひたすら唱えることで、阿弥陀如来の救いによって死後に極楽浄土に生まれることを願います。
「南無阿弥陀仏」の南無は、相手への最大の尊敬や絶対的な信頼を表現した言葉で、尊敬する阿弥陀如来様という意味があり、法然上人は一日に6万回の念仏を唱えたと言われています。
数珠は、「荘厳数珠」「修法数珠」「日課数珠」の他、大勢で輪になり繰る巨大な「百万遍数珠」など特殊な数珠があります。
一般の檀家・信徒が使用する日課数珠は、珠の数は108ではありません。2つの輪を交差させて一つに繋いだような独自の形をしているのが特徴です。
念仏の数をたくさん数えるのに適した形になっており、その形状から二連数珠、環貫数珠などとも呼ばれています。
浄土真宗
数珠の持ち方は、
| ・男性は略式数珠の基本的な持ち方 ・女性は二重にして房を下に垂らして左手に持つ |

合掌をするときは、
| 1.二重にして房を下に垂らす 2.親指と人差し指の間に数珠を挟むように両手にかける 3.親指で軽く上からおさえる |
浄土真宗は、親鸞を宗祖とする宗派で総本山は西本願寺、ご本尊は阿弥陀如来のみです。
日本で一番信徒が多い宗派で、阿弥陀如来を信じて全てをゆだねることで、煩悩を持った人でも死後に阿弥陀如来の極楽浄土に生まれることができるという教えです。
「南無阿弥陀仏」を「なもあみだぶつ」と唱えますが、これは願掛けのセリフではなく、阿弥陀如来に対する感謝を意味します。
数珠は、男性が略式数珠を使い、女性は108珠の数珠を二重にして使います。
煩悩を持っていても極楽浄土に生まれることができるという考えから、煩悩を消すために唱えた念仏を数える数珠にこだわりがありません。
また、房が数珠を繰ることができないとされる「蓮如(れんにょ)結び」なのも、同じ理由からです。
真言宗
数珠の持ち方は、
| 1.親珠が上にくるように二重にする 2.房は手のひら側に垂らして珠と一緒に左手で握る |
合掌をするときは、
| 1.二つの親玉を両手の中指にかける 2.そのまま手のひらを合わせる (3.合掌した手を擦り合わせ、音を立てて使う) |
真言宗は、空海を宗祖とする宗派で総本山は高野山金剛峰寺、ご本尊は大日如来などです。
空海が、唐(現在の中国)で学んだ密教を基盤としている宗派で、宇宙の本体であり絶対の真理である大日如来と一体化することを目指して修行します。
数珠は、親玉、四天玉(四菩薩)の他、108珠あり二重にして使います。
ほかの宗派に比べ数珠を重要視しており、4本の房には弟子珠5つずつの計20珠と露珠がついているのが特徴的です。
日蓮宗
数珠の持ち方は、
| 房を下に垂らして二重にして持つ |
合掌では2通りのやり方があり、故人のための法要を行うときには、
| 1.3つに分かれた房がついている方の親珠を左手中指にかける 2.数珠をひとひねりする(∞のような形になる) 3.もう一方の親珠を右手中指にかける 4.そのまま数珠を手のひらに挟むようにして両手を合わせる |
お経を唱える際の合掌では、
| 1.房を下に垂らして数珠を二重にする 2.左手の親指と人差し指の間に挟むようにかける 3.両方の手を合わせる |
日蓮宗は、日蓮を宗祖とする宗派で総本山は久遠寺、ご本尊は大曼荼羅などです。
法華経信仰による仏教の宗派で、宗祖の名前がそのまま名称になっています。
釈迦の言葉をまとめたお経の数は、8万4千と言われていますが、その中でも、「法華経(妙法蓮華経)」は唯一最高の経典だと考え、日蓮宗がもっとも大切にしている教えです。
尊敬の意を込めた「南無」と「法華経」を合わせた「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」という題目を唱えることで自ずと悟りが得られ、全ての人々が成仏できると説いています。
数珠は、108珠の数珠を二重にして使います。
日蓮宗では正式な数珠を使用することを重んじており、2つの親玉からはそれぞれ2本、3本の房が出ているのが特徴です。
曹洞宗

数珠の持ち方は、
| 房を下に垂らして二重にして持つ |
合掌をするときは、
| 1.房を下に垂らして数珠を二重にする 2.左手の親指と人差し指の間に挟むようにかける 3.両方の手を合わせる |
曹洞宗は、道元を宗祖とする宗派で総本山は永平寺、ご本尊は釈迦如来などです。
坐禅の実践で得る心身のやすらぎが、そのまま仏の姿だと自覚することにあるという考え方があり、座禅を修行の中心としていることから「禅宗」とも呼ばれています。
壁に向かってひたすら禅を組むことで自分の心と向きあい、自分の中にある仏心を見出すことが目的にあります。
二重にした数珠に、金属の輪がついた108珠の数珠を使います。
特に念仏よりも座禅などの修行を重んじる傾向があるので、他の宗派ほどあまり数珠にこだわりがなく、数珠の作りはシンプルで親玉は1つ、房には弟子玉もありません。
しかしながら、数珠を持つことで煩悩を消し去って身を清めるご利益があると信じられており、本式数珠を持つ檀家・信徒が多いです。
真宗大谷派
数珠の持ち方は、
| ・男性は略式数珠の基本的な持ち方 ・女性は二重にして房を下に垂らして左手に持つ |
合掌をするときは、
| 1.親玉を上にして二重にする 2.両方の親珠を両手の親指と人差し指の間ではさむ 3.房は上から左手の甲に垂らす |
真宗大谷派は、親鸞を宗祖とする宗派で総本山は東本願寺、ご本尊は釈迦如来です。
浄土真宗の宗派の1つで、基本的な教えは浄土真宗本願寺派と同じですが、「南無阿弥陀仏」を「なもあみだぶつ」ではなく「なむあみだぶつ」と唱えます。
煩悩を持った人でも死後に阿弥陀如来の極楽浄土に生まれるという考え方から、数珠の作りにこだわりが少なく、房が数珠を繰ることができない「蓮如(れんにょ)結び」になっています。
臨済宗
数珠の持ち方は、
| 房を下に垂らして二重にして持つ |
合掌をするときは、
| 1.房を下に垂らして数珠を二重にする 2.左手の親指と人差し指の間に挟むようにかける 3.両方の手を合わせる |
臨済宗は、栄西を宗祖とする宗派で総本山は妙心寺(妙心寺派)、ご本尊は釈迦如来などです。
座禅を修行の中心とした「禅宗」ですが、ひたすら座禅に徹する曹洞宗に対し、臨済宗では禅問答で師匠から弟子に悟りを伝達する「法嗣(はっす)」を重んじています。
数珠は、108珠の数珠を二重にして使います。
念仏よりも座禅などの修行を重んじるため、数珠にこだわりが少なく数珠の作りは、親玉が1つ、房には弟子玉もないシンプルな物です。
天台宗
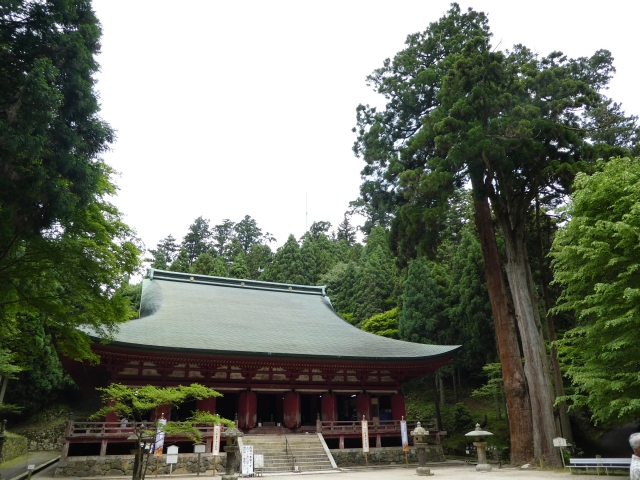
数珠の持ち方は、
| 1.二重にして親珠は上にする 房は手の外側にくるようにして持つ |
合掌をするときは、
| 1.数珠を両手の人差し指と中指の間にかけて挟む 2.中指・薬指・小指が数珠の輪の内側にくるように広げる 3.そのまま手のひらの間に数珠を挟むように両手を合わせる |
天台宗は、最澄を宗祖とする宗派で総本山は比叡山延暦寺、ご本尊は釈迦如来などです。
日本仏教の母山と呼ばれる比叡山延暦寺を総本山とする天台宗は、浄土宗、浄土真宗、臨済宗など日本の主要仏教宗派の始祖が修行を積んでいたことでも有名です。
阿弥陀如来の他、釈迦如来や薬師如来、観世音菩薩など複数の本尊を祀っていますが、これは、法華経、密教、禅、念仏など、さまざまな教えを取り入れているためです。
数珠は、108珠の数珠を二重にして使います。
主珠の平玉はそろばん珠のような形で、房には、20珠の平珠と10珠の丸珠と露珠が付いています。
特徴のある数珠ですが、本式数珠を使うのは寺院や熱心な檀信徒のみ。
一般の人は略式数珠や、二連の振り分け数珠を使います。
創価学会
合掌をするときは、
| 1.2本の房側を右手に持ち3本の房側を左手に持つ 2.両手の中指のみを数珠の輪の内側入る 3.そのまま手のひらの間に数珠を挟むように両手を合わせる |
創価学会は、法華経系の在家仏教の団体を指します。
名前にある「創価」とは「価値創造」のことを意味していて、価値の中心は生命の尊厳の確立。
さらには、「世界の平和」の実現と「万人の幸福」を目標としています。
数珠は、108珠で白房がついています。
創価学会の数珠専門店で購入されることを推奨しています。
お葬式やお通夜などでの数珠の取り扱いマナー

いつ使うことになるかわからない数珠ですが、取り扱いのマナーを知っておけば安心ですね。
ここではお葬式やお通夜などでのマナーをご紹介します。
共有せず自分専用を用意
例え家族間であっても親しい友人であっても、数珠の貸し借りはしないのがマナーです。
数珠は本人の分身や魂を表すものでお守りの役割もある仏具です。
また、数珠は念珠ともいい、これまで手を合わしていた時の個人の念が込められています。
使うほどに個人の数珠になっていく物なので自分以外の人に渡すのはよくないのです。
人から借りるくらいなら数珠なしで葬儀へ参列した方が良いとされていますが、どうしてもという場合は、葬儀会場の人に聞いてみると貸し出し用の数珠があるかもしれません。
もしくは近くに100均やコンビニがあれば売っている可能性もあるので確認してみてください。
焼香の際の数珠の持ち方
焼香台の前で慌てて数珠を取り出すのはあまり良くないことです。
焼香が必要なお通夜や葬式などでは最初から最後まで数珠は左手に付けておきましょう。
焼香の順番待ちで座っているときは左手首にかけておき、歩くときや列に並んでいるときは房を下にして左手で持ち歩きます。
焼香で合掌する際は、左手のみにかけても両手にかけてもどちらでも構いませんが、焼香が済んだらまた左手で数珠を持つのがマナーです。
数珠に関するNGマナー
お通夜式や葬儀・告別式などで、ときおり間違った数珠の扱い方をしている人を見かけます。
| ・右手で持ち歩く ・房を持って移動する ・席や床に直置き |
これらはすべてマナー違反です。
数珠は故人や遺族に対する敬意を表す法具だということを忘れてはいけません。
雑な扱いはせず、席を離れるときはバッグやポケットに入れて持ち歩いたり、席取りに使いたい場合はハンカチの上に置いたりするなどして大切に扱ってください。
まとめ

数珠の使い方をマナーとともにご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
数珠には本式数珠と略式数珠があり、略式数珠は宗派を問わず使えることがわかりました。
また、略式数珠は男性用と女性用を間違えなければどれを選んでも良いので、お気に入りを見つけられそうです。
数珠は原則左手で持つなど数珠のマナーはたくさんありますが、いざという時に恥をかかない、かつ失礼にあたらない数珠の使い方を覚えてください。
こちらの記事もよく読まれています。









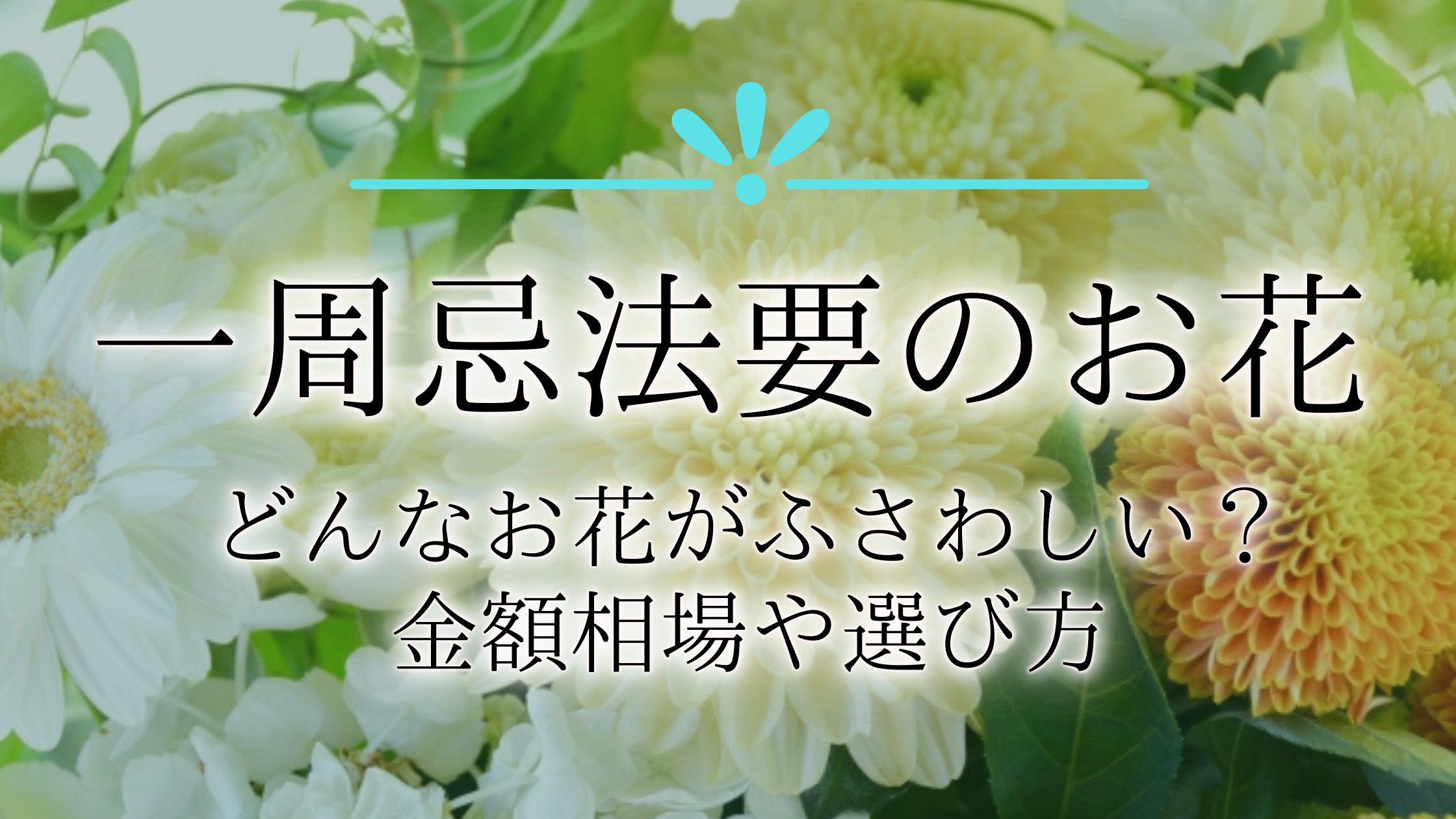
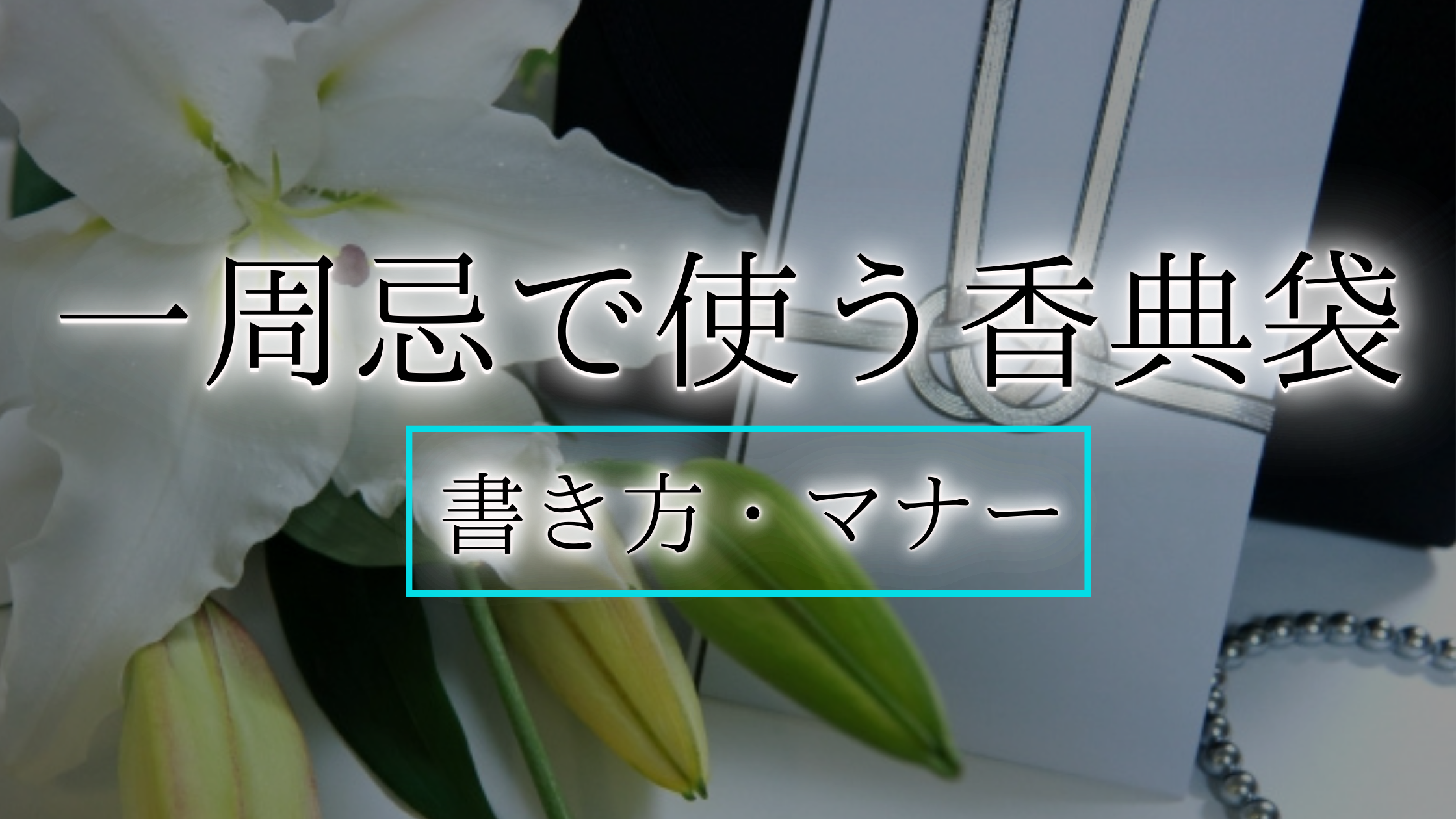
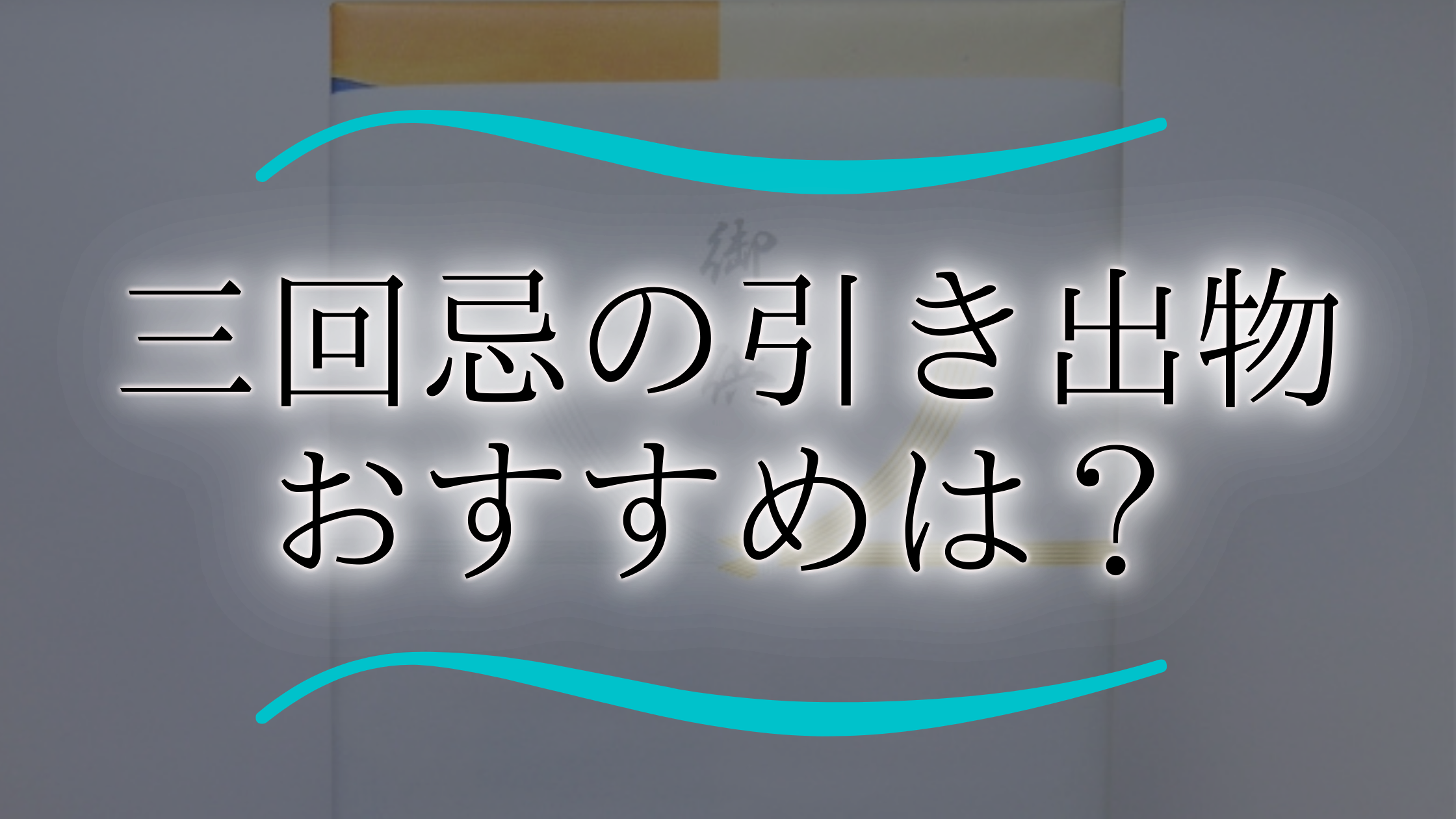
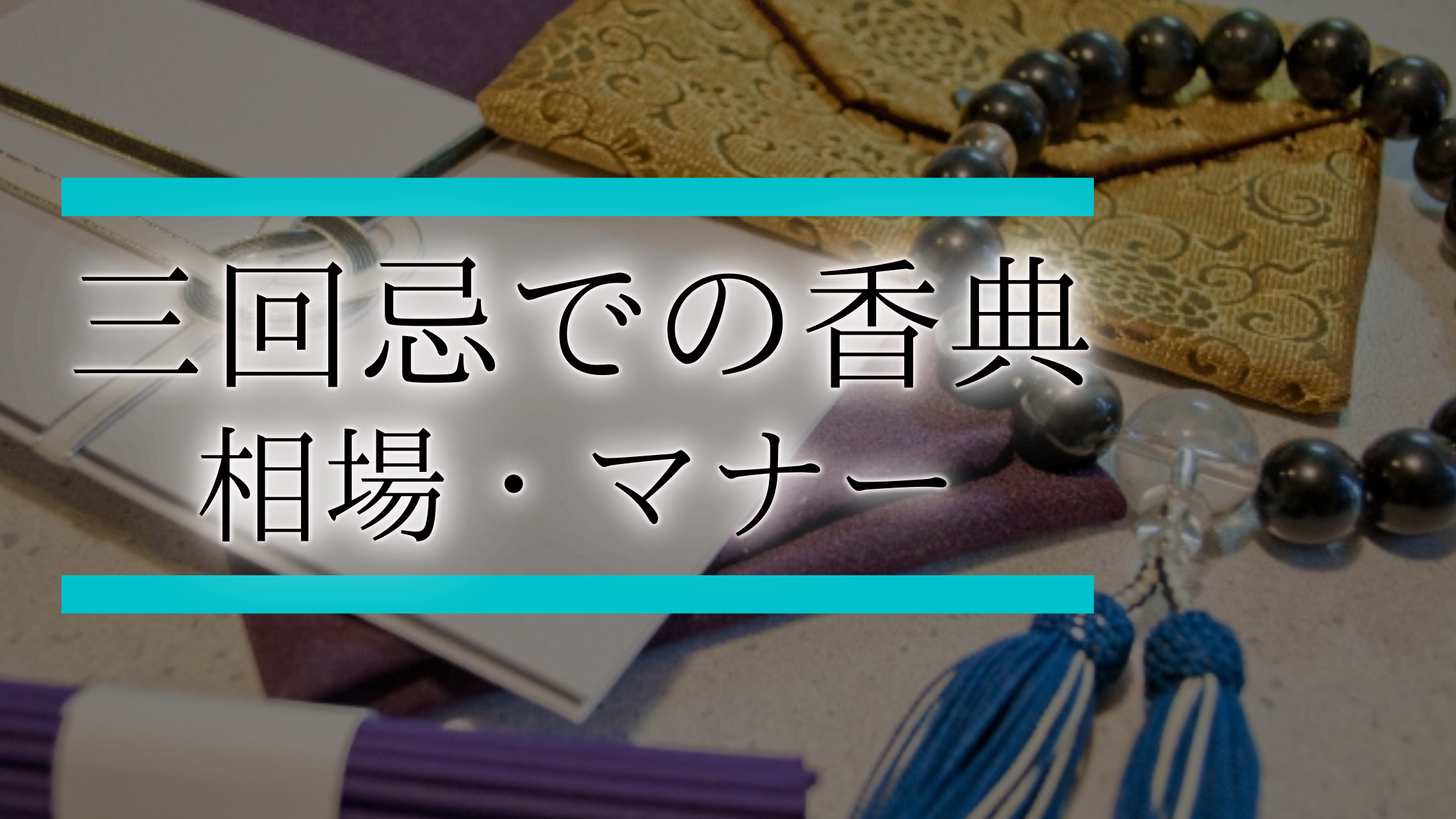
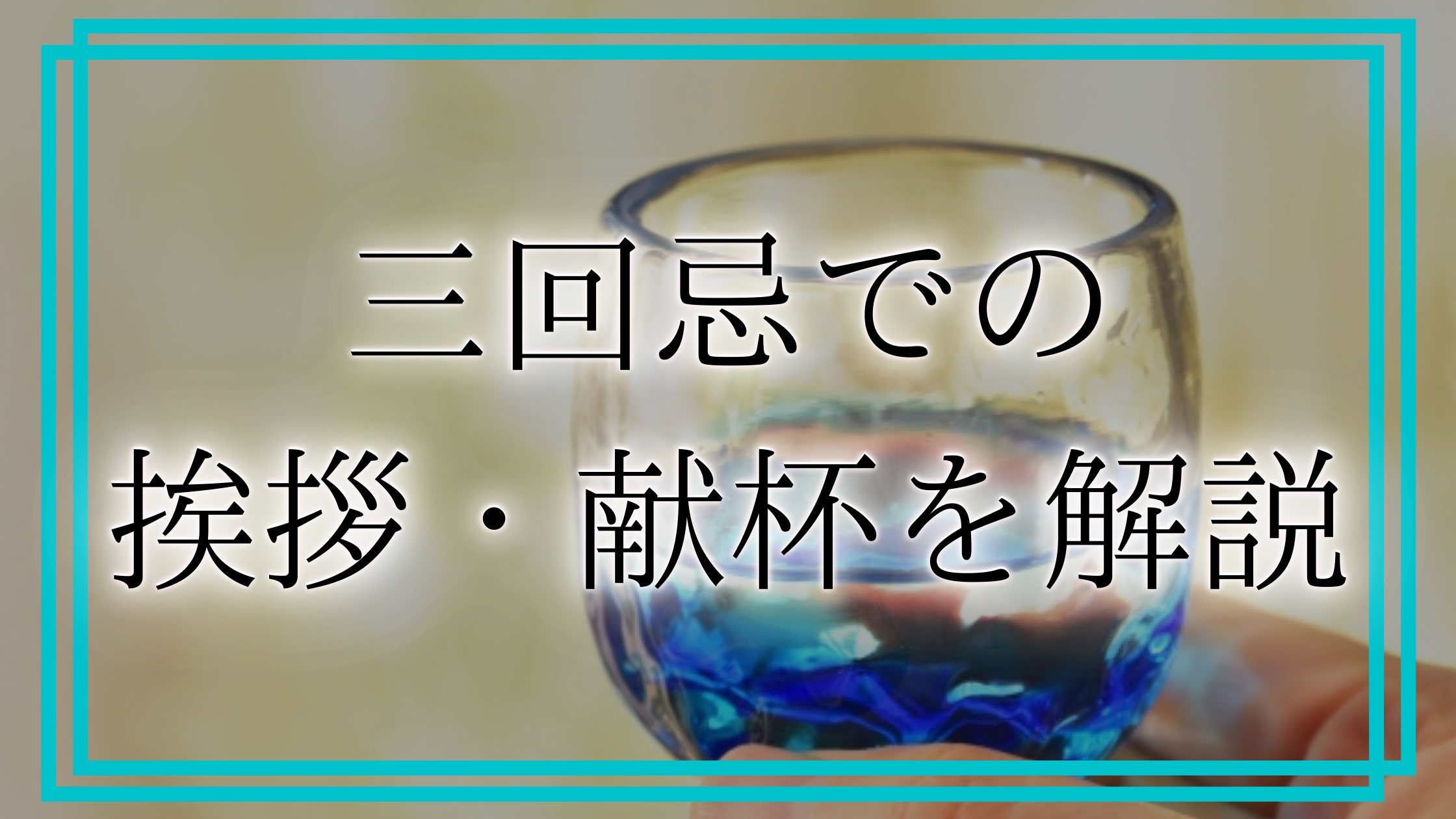
アイキャッチ.png)