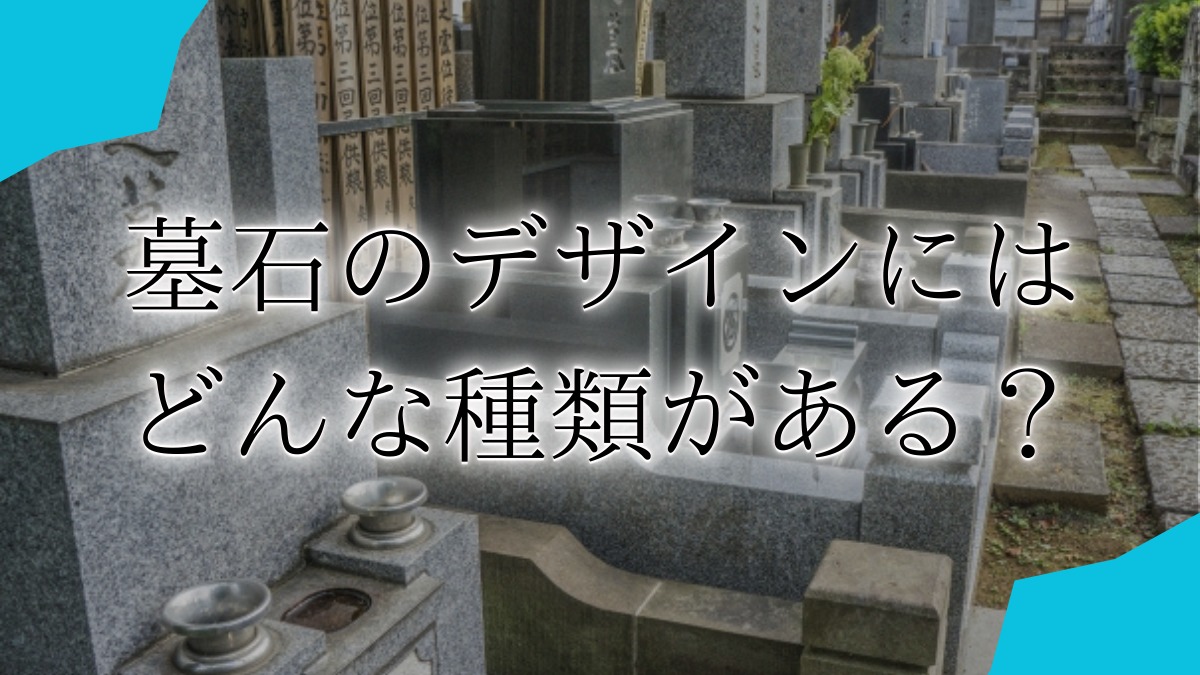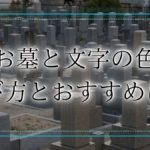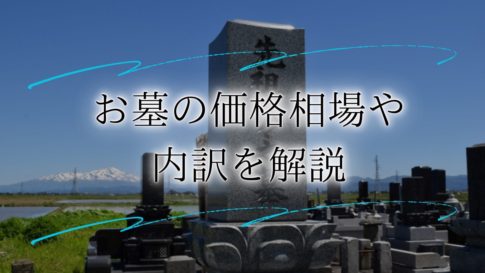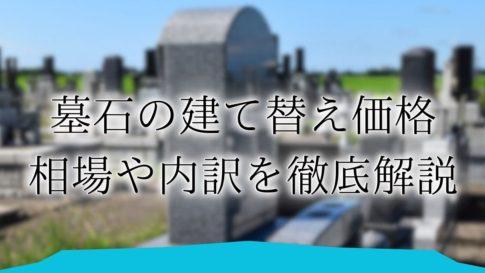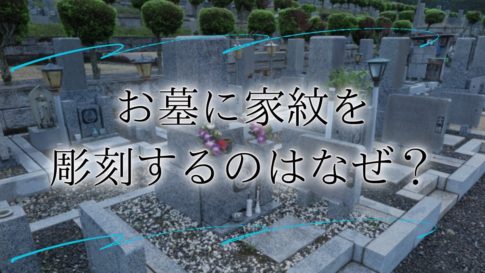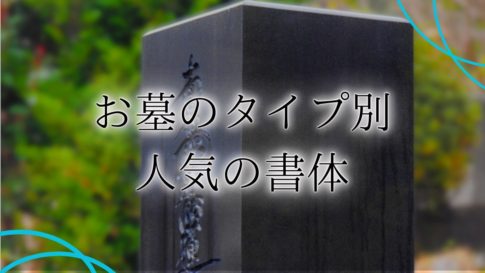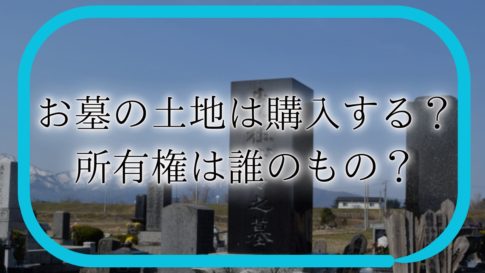最近では、故人の趣味・嗜好(しこう)を取り入れた独創的なお墓が増えています。
その中で、墓石のデザインがうまくまとまらず、お墓作りに苦労している方もいるのではないでしょうか。
そこで、本記事では墓石のデザインにはどのような種類があるのか知りたい方に向けて、種類別の特徴を解説します。
お墓のデザインを決める手順・注意点も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
お墓のデザインは大きく分けると3種類!

お墓のデザインは大きく分けると「和型墓石」「洋型墓石」「デザイン墓石」の3種類で、現在は和型墓石が主流です。
近年では、お墓の価値観やニーズが多様化し、形にとらわれない個性的なデザインのお墓が増えてきました。
また、宗派ごとの特別な決まりはなく、好みのデザインで建てられます。
ただし、霊園や墓地によっては墓石の形状を規制している場合もあるため、それぞれの規定・区画に応じた形、大きさに従わなければなりません。
故人や遺族にとって心休まる場所にするためにも、お墓のデザインは慎重に決めましょう。
和型墓石

和型墓石は、江戸時代中頃から普及した昔ながらの墓石です。
馴染み深さと重厚な見た目から、今も世代を問わず好まれています。
和型墓石の特徴と構成
和型墓石は角型で、石が3~4段に積まれ、縦長の形をしているのが特徴です。
起源については諸説ありますが、お釈迦様の遺骨を納めた「ストゥーパ(卒塔婆)」や「仏舎利塔(ぶっしゃりとう)」が原型だと考えられています。
江戸時代になって檀家制度が整い、庶民もお墓を建て始めたことで、角柱墓が広く親しまれるようになりました。
現在の和型墓石は、板碑(いたび)や位牌を模したもので、上から「棹石(さおいし)」「上台石」「中台石」「芝石(芝台)」で構成されている場合がほとんどです。
棹石は天(夫婦円満)、上台石は人(事業繁盛・人望)、中台石は地(財産安定)と、それぞれ特別な意味が込められています。
また、棹石は横幅によって分類されます。
|
「南妙法蓮華経」や「南無阿弥陀仏」などのお経の一部を彫刻する宗派もありますが、正面に家名を彫ることが一般的です。
お墓といえば、この和型墓石を想像する人も多く、伝統的なデザインと言えるでしょう。
和型の供養塔
江戸時代に現在の主流である角柱墓石が誕生する前は、石造の供養塔がお墓の役割を担っていました。
ここからは、代表的な和型の供養塔を紹介します。
五輪塔(ごりんとう)
五輪塔は、弘法大師(空海)が伝えた真言密教の教えに基づいて、平安時代から建てられるようになった供養塔です。
「故人は仏教における宇宙観の五大元素に回帰する」という考えにならい、上から宝珠形の「空輪」、半月形の「風輪」、三角形の「火輪」、円形の「水輪」、方形の「地輪」で構成されています。
現在でも五輪塔の構成を再現したお墓は多く、一石五輪塔や略式五輪塔といった狭い場所にも建てられるデザインが選ばれています。
宝篋印塔(ほうきょういんとう)
宝篋印塔は中国から伝わった石塔で、五輪塔とともに鎌倉時代を代表する供養塔の一つです。
「一切如来心秘密全身舎利宝篋印陀羅尼経」という経典を納めていました。
上から相輪・笠・塔身・基礎・基壇の順に構成されており、笠にある「隅飾(すみかざり)」という突起が特徴です。
100年以上前のご先祖を供養するお墓とされ、江戸時代では支配階級の墓石、現在では法人や名家、旧家、寺院の歴代墓など、先祖代々から続く家系で使われています。
多宝塔(たほうとう)
多宝塔は円筒型の棹石に笠石を重ねた石塔で、平安時代後期~鎌倉時代後期にかけて多く建てられていました。
五輪塔と同様、真言宗開祖の空海が着想したと言われており、寺院建築の様式としても有名です。
現在では、個人の墓石や供養塔として用いられています。
無縫塔(むほうとう)
無縫塔は、鎌倉時代に中国の宋から伝来した禅宗の石塔です。
台座に卵の形に似た塔身が載っていることから、「卵塔」とも呼ばれています。
また、無縫塔は構成の形式が分かれており、基礎・棹・中台・請花・塔身の「重制」と、基礎・請花・塔身の「単制」の2つです。
当初は禅僧の供養塔でしたが、現在では宗派に関係なく僧侶のお墓として使われています。
神道のお墓
神道のお墓は基本的に仏式と同じものの、香炉がなく、玉串を捧げる八足台が必要です。
頂部にある「兜巾(ときん)」と呼ばれる加工を施した細長い角柱型の棹石が特徴的で、三種の神器である「天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)」をかたどったものと考えられています。
また、墓石には「◯◯家之奥津(都)城」と刻み、墓石の横に「霊標(墓誌)」を設けるのが通例です。
「津」は万葉仮名で「~の」を意味し、一般の信徒には「津」、神官や氏子のお墓には「都」と表記します。
神道の場合は、神社ではなく公営および民営の霊園にお墓を建てることになるため、墓地を購入する際は注意しましょう。
洋型墓石

ガーデニング霊園や芝生墓地などの登場により、最近では首都圏や東日本を中心に現代風の洋型墓石を選択する人が増えています。
宗教や宗派を選ばず使用でき、石の色・種類の自由度が高い点も人気の理由と言えるでしょう。
洋型墓石の特徴
洋型墓石は和型墓石と比べて背が低く、横に長いのが特徴です。
そのため、地震に強いうえに少ない墓石量・スペースで建てられるメリットがあります。
また、多くの場合外柵工事や土盛りの必要がなく、和型墓石よりも安価です。
基本的な形状はキリスト教のお墓がベースとなっており、「オルガン型」や「ストレート型」、「プレート型」などがありますが、香炉や花立てといった墓石の付属品は、和型墓石と変わりません。
洋型墓石には家名ではなく、故人へのメッセージを刻むのが基本で、オリジナルの文字やレリーフを使い、自由に気持ちを表現できる点が魅力です。
キリスト教のお墓
日本で最初につくられたキリスト教のお墓は外国人墓地で、現在はカトリック教会ごとの墓地や納骨堂、プロテスタントの場合は日本キリスト教団地区ごとの墓地があります。
墓石の形・構成については、十字架を刻むこと以外は比較的自由に決められ、平型やオルガン型、敷石に十字架を載せたものなどさまざまです。
石材には大理石や赤御影石を使い、香炉の代わりに蝋台を設けます。
また、キリスト教では故人1人につき1つのお墓を建てる単独墓が基本ですが、最近では家族で入れるお墓も増えてきました。
デザイン墓石

従来の形式にとらわれない故人や施主の個性、発想を取り入れたお墓は「デザイン墓石」と呼ばれます。
墓石そのものを加工・デザインすることで、故人の趣味や嗜好、家族の気持ちを表現できる点が魅力です。
最近では、設計時にCADや3Dシミュレーターを使う石材店も多く、事前に仕上がりのイメージを確認できるため、ぜひ活用してみましょう。
故人をイメージしたオリジナルデザイン
デザイン墓石には、生前に故人が好んだ品や趣味を反映したものも多く見られます。
たとえば、将棋が好きなら将棋盤や駒の形、お酒が好きなら徳利(とっくり)の形にするなどです。
生前の趣味・嗜好を墓石に表現すれば、亡くなった方の雰囲気や印象を強く残し、お墓参りの際に故人の存在を感じることができるでしょう。
デザインにこだわるほど墓石量が増えたり費用もかさんだりするものの、故人への深い愛情を表現できる方法として人気があります。
漢字一文字・メッセージを彫刻
デザイン墓石で増えてきているのが、漢字一文字を彫刻した墓石です。
人気の傾向としては、偲・想・心・絆など、故人の極楽浄土や感謝の気持ちを祈る漢字が挙げられるでしょう。
墓石全体にしっかりと大きく彫れる漢字一文字以外にも、「ありがとう」や「やすらかに」といった短いメッセージを彫るケースもあります。
【人気】お花のイラストを彫刻
最近では、文字とお花の彫刻を組み合わせたデザインも人気です。
墓石にお花を彫ることで、華やかさとやわらかさを印象づけられます。
お花には花言葉や季節感もあるため、故人の好み・イメージに合ったものを選びましょう。
お花の種類
墓石に彫るお花の種類について、特別な決まりはありません。
故人の好みやイメージに合っていて、石材店が対応できるものを選びましょう。
選ばれやすい傾向としては、桜・百合・牡丹・蓮華などの和風の花や仏教に関連するお花が挙げられますが、藤やすみれ、ひまわり、モミジなども人気です。
仏教ではふさわしくないとされるバラも、お供えはできずとも彫刻であれば華やかに飾れます。
お花を彫刻する場所
お花を彫刻する場所には、お墓のメインとなる棹石が選ばれやすい傾向にあります。
棹石は面積が広く目立ちやすいため、大きく彫りたいときや墓石を華やかに飾りたいときによいでしょう。
また、花立や丘カロートの蓋に彫刻するのもおすすめです。
丘カロートの蓋は墓誌に使用する場合もあるため、全体の構成をよく考えて決めましょう。
お花を彫刻する手法
お花の彫刻で多く用いられるのは、線彫りや二度彫りなどの手法です。
線彫りは一本線で花の輪郭のみを描く手法で、イラストのように仕上がります。
彫刻をより目立たせたい場合は、サンドブラストによる二度彫りがおすすめです。
サンドブラストを施した部分は白くなるため、色の濃い墓石によく映えるでしょう。
他にも、花びらのふっくらとした様子を再現できる立体彫りや、異なる石を埋め込む象嵌(ぞうがん)などの手法があります。
お墓のデザインを決める手順と注意すべきポイント

ここからは、お墓のデザインを決める手順と注意すべきポイントを解説します。
よりよいお墓作りのためにも、しっかりと確認しましょう。
①お墓を建てる土地を確認・調査する
まずはお墓を建てる土地を調べ、区画面積や立地、霊園のルールを確認することが大切です。
霊園やお寺の中には、墓石の種類や形状、石材店を指定しているケースもあります。
施工難易度や土地の条件によっても建てられるお墓は変わるため、必ず確認しておきましょう。
特に、石材の運搬が困難な山墓地や狭所では、費用が高額になる可能性もあります。
➁墓石デザインを決める
お墓を建てる土地が決定したら、墓石デザイナーと相談して墓石デザインを決めていきます。
墓石のデザインごとの費用相場は、次の通りです。
| 種類 | 費用の相場 |
| 和型墓石 | 800,000円~ |
| 洋型墓石 | 500,000円~ |
| 和洋型墓石 | 600,000円~ |
| デザイン墓石 | 700,000円~ |
石材店によってはデザインカタログをつくっていることもあるため、イメージがまとまらない場合は参考にさせてもらうとよいでしょう。
③石材を選ぶ
石材ごとに色や質(硬度、吸水率、耐久性)など、メリット・デメリットが異なるため、デザイナーと相談しながら選びます。
日本のお墓に多いのは御影石ですが、石材の原産国や採掘量によってもお墓の価格は大きく変わるため、慎重に決めましょう。
墓石に使われる石材の種類については、以下の記事で詳しく解説しています。
④彫刻内容を決める
墓石に刻む文字や家紋、絵柄を決めます。
先ほど解説したデザインの種類や特徴を参考に、ふさわしいものを選びましょう。
⑤付属品を選ぶ
墓石のデザインに合った付属品を選びます。
主な付属品は、次の通りです。
|
⑥見積もりを取る
最後に、石材店から見積もりを取ります。
施工後のトラブルを避けるためにも、具体的には次のポイントに沿って内容を確認しましょう。
|
【墓石デザインを左右する!】信頼できる石材店を選ぶポイント
石材店の施工技術や実績は墓石のデザインに大きく影響するため、信頼できる石材店を選びましょう。
ここからは、見極めるポイントを解説します。
口コミ
信頼できる石材店かどうかを見極めるには、口コミが重要です。
検索エンジンの口コミ評価のほか、石材店のホームページでお礼のお便り紹介をしている場合もあるため、一度確認してみましょう。
施工事例
石材店が過去に行なった施工事例なども、依頼先を選ぶよい基準の一つです。
得意なデザインは石材店によって異なるため、イメージに合ったお店を選びましょう。
店舗で相談
墓石のデザインやイメージがまとまらない場合は、実際の店舗に行って相談しましょう。
墓石デザイナーと対面して相談することで、質問や見積もりもスムーズにできます。
建立現場を確認
実際の建立現場を確認することも、石材店を選ぶうえで重要なポイントです。
細部の彫刻や加工の丁寧さは、写真だけで判断できません。
完成後にイメージと違ったなどのトラブルがないよう、確認しておきましょう。
【要注意】意匠トラブルが増加中
近年、独自の発想を取り込んだ墓石が注目を集め、石材店でもデザイン墓石をつくるようになって以降、「意匠」トラブルが増加しています。
意匠とは、物品の形状や色、模様など、視覚的な美しさを感じさせるデザインのことです。
意匠には、彫刻や文字といった部分的なデザインも含まれ、意匠法により、意匠登録がされて「意匠権」が発生したデザインは無断で使用できません。
意匠権の存続期間は、意匠登録出願日によりけり異なりますが、現在は最長25年です。
なかには施主の希望に応えようと、他社の墓石デザインを模倣する石材店もあります。
意匠登録済みのデザインを真似た場合、意匠権を侵害したとして「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」に処されるため、注意しましょう。
まとめ

お墓作りで最も大切なのは、故人を思いやり、安らげる場所にすることです。
故人・家族ともに納得のいくお墓をつくるためにも、墓石デザインは慎重に決めましょう。
ただし、文字やデザインを盛り込みすぎると全体のバランスが悪くなり、イメージ通りのお墓にできない可能性があります。
石材店や墓石デザイナーと相談して、完成後の墓石をイメージしながらデザインを考えることが大切です。