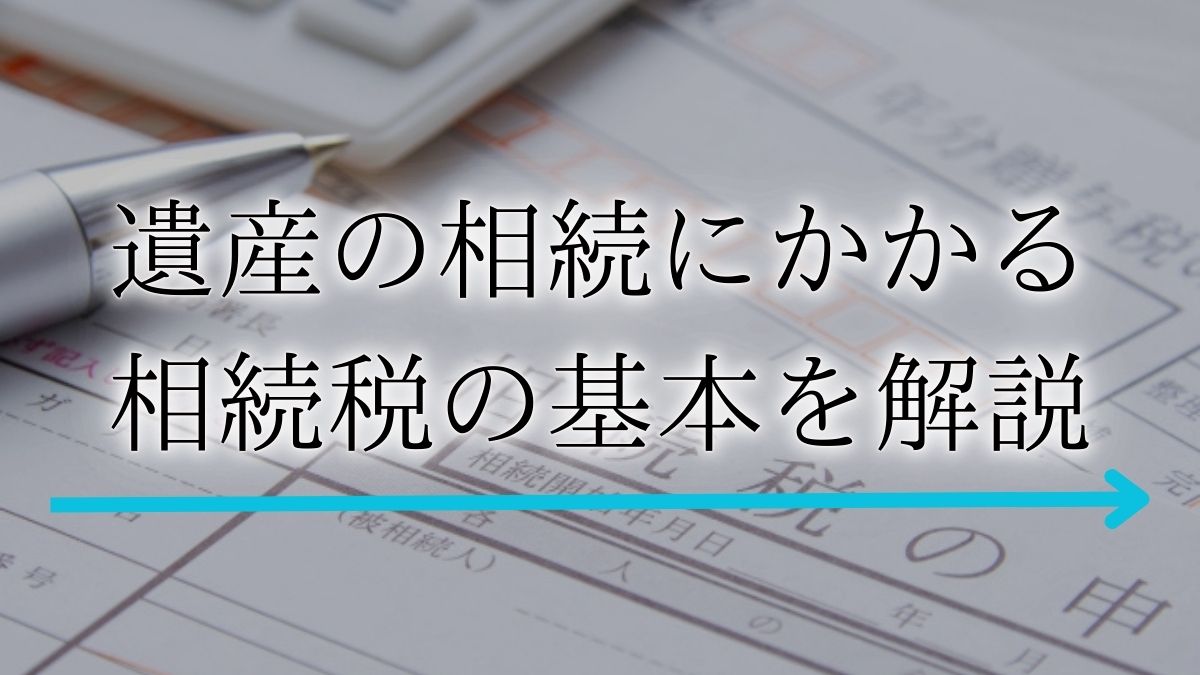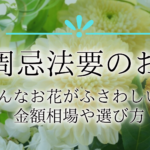遺産を相続すると、相続税がかかります。
基礎控除額を超えた場合に超えた金額に対してかかる税金で、必ずしもかかるわけではありません。
本記事では、相続税がかかる基準や税率、基礎控除額の計算方法を解説します。
相続税がかかる場合の手続きも解説しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
遺産を相続すると「相続税」がかかる

相続税とは、相続した財産の評価額に応じて相続人が支払う税金です。
とはいえ、必ずしもかかるわけではなく「相続した財産の総額が一定の金額内であれば相続税がかからない」という税額計算方法が採用されています。
この相続税がかからない範囲の金額のことを「基礎控除額」と言い、基礎控除額を超えて相続した財産額にのみ相続税が課せられます。
基礎控除額の計算方法
基礎控除額は、以下の計算式で算出できます。
| 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額 |
たとえば、相続した財産額が4,500万円で法定相続人が2人いたとします。
この場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×2)=4,200万円」となるため、基礎控除額を超えた300万円が課税対象です。
相続税の税率
相続税は、相続額が一定額を超えるごとに税率が上がる「超過累進課税率」が採用されています。
▼相続税の超過累進課税率
| 法定相続分に応じる取得金額(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税を計算するのは非常に複雑で難しいため、後ほど紹介する早見表を参考にしてください。
すべての相続財産が課税対象ではない
相続する財産には、課税対象の財産と非課税対象の財産があります。
課税対象の財産
課税対象となる財産は以下の4種類です。
|
相続財産
相続財産とは、相続や遺贈により取得した財産を指します。
課税対象となる相続財産には、以下のものがあります。
|
有形無形を問わず、経済的価値のある相続財産はすべて課税対象です。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、「被相続人が亡くなったことで受け取る保険金などの財産」のことです。
厳密には、相続や遺贈で取得した財産ではないため相続財産にはあたりませんが、税法上は相続財産とみなされて課税対象となります。
代表的なみなし財産は「生命保険金」と「死亡退職金」です。
生命保険金は、生命保険料の負担者が被相続人であった場合に、原則相続税が課税されます。
生命保険料の負担者が被相続人ではなかった場合は相続税ではなく、所得税や住民税が課税されます。
死亡退職金は、金銭であるかもの・権利であるかは問わず、実質的に被相続人の退職手当金などとして支給される金品を言います。
死亡退職金に相続税が課せられるのは、死亡後3年以内に金品を受け取った場合です。
死亡後3年が経過した後に受け取った場合は、相続税ではなく所得税が課せられます。
生命保険金や死亡退職金には「非課税枠」があり、一定額までは相続税がかかりません。
こちらについては、後の項で解説します。
相続開始前3年以内に贈与された財産
相続開始日前の3年以内に生前贈与された財産を生前贈与加算と言い、相続財産に加算されて相続税が課税されます。
生前贈与加算により課税される相続税は、相続時の時価ではなく贈与時の時価で評価されるのが特徴です。
また、生前贈与時に贈与税を納めていた場合は、二重課税を防止するために納付済みの贈与税額が相続税から控除されます。
なお、令和6年4月1日以降に贈与された財産は、加算対象の期間が以下に変更されています。
| 相続開始日 | 加算対象の期間 |
| 令和6年1月1日~令和8年12月31日 | 相続開始前3年間 |
| 令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日~相続開始日 |
| 令和13年1月1日~ | 相続開始前7年間 |
相続時精算課税制度を適用して贈与された財産
相続時精算課税制度とは、「2,500万円までの生前贈与を非課税として、その人が亡くなった際は相続財産額に生前贈与した財産額を合わせて相続税に課税する制度」です。
たとえば、1億円の財産を持っているAさんが、相続時精算課税制度を適用して子どもに2,500万円の生前贈与を行なったとします。
相続時精算課税制度を使えば2,500万円までが非課税となるため、贈与税は課税されません。
しかし、Aさんが亡くなって子どもが残りの7,500万円を相続した際は、生前贈与された2,500万円を加算した1億円に相続税が課せられる仕組みです。
非課税の財産
非課税となる財産には、以下のものがあります。
|
祭祀財産(さいしざいさん)
家系図、墓地、墓石、仏壇、神具・仏具、神棚などの祭祀財産は非課税です。
ただし、金の仏像などのように資産価値のあるものや、投資目的で所有している祭祀財産は非課税とはならないため注意が必要です。
弔慰金、花輪代
遺族へのお悔やみとして支給される弔慰金や花輪代などは、世間一般の常識的な金額の範囲内であれば相続税が非課税です。
ただし、常識的な金額かどうかの判断は難しいため、相続税法で下記のように基準が
定められています。
|
上記の基準を超えた分については、退職金に加算して相続税が課税されます。
生命保険金・退職手当金の非課税枠
みなし相続財産として相続税が課せられる生命保険金・死亡退職金ですが、それぞれ一定の金額までは相続税がかからない非課税枠が設けられています。
生命保険金と死亡退職金の非課税限度額は、ともに「500万円×法定相続人の数」で算出が可能です。
事故などの損害賠償金
交通事故や飛行機事故などで被相続人が死亡した場合は、生命保険金や損害保険金のほかに損害賠償金も支払われます。
遺族の精神的な苦痛に対する慰謝料としての損害賠償金には、相続税がかかりません。
ただし、事故によって発生した付添看護費や医療費などに対する損害賠償金は相続財産とされ、相続税がかかる場合があります。
国や地方公共団体などへ寄付した財産
国や地方公共団体、特定の公益法人や認定NPO法人などに寄付した相続財産には、相続税はかかりません。
ただし、以下の条件が設けられています。
|
おおよその税額は早見表で確認できる

相続税早見表では、おおよその相続税額を確認できます。
相続人が子どものみの場合と配偶者がいる場合で税額が変わるため、自分に合う早見表を参考にしてください。
▼相続人が子どものみの場合
| 遺産総額 | 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
| 9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
| 2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
| 5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,120万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 |
| 10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 | 3億1,770万円 |
※法定相続分で分割した場合で、子どもは全員平等に分割
▼配偶者がいる場合(相続人が配偶者と子どもの場合)
| 遺産総額 | 配偶者 子ども1人 |
配偶者 子ども2人 |
配偶者 子ども3人 |
配偶者 子ども4人 |
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 | 225万円 |
| 1億5,000万円 | 920万円 | 747万円 | 665万円 | 587万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217万円 | 1,125万円 |
| 2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,687万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 5,500万円 |
| 10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 | 1億5,650万円 |
※法定相続分で分割した場合で、配偶者は配偶者控除を適用
相続税の基礎控除以外の控除・特例
相続税には、基礎控除以外にもさまざまな控除が適用されます。
配偶者控除
配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産のうち1億6,000万円までであれば、相続税が課税されない制度です。
また、規定の1億6,000万円を超えた場合でも、「配偶者の法定相続分」までであれば課税されません。
▼配偶者の法定相続分
| 法定相続人 | 配偶者の法定相続分 |
| 配偶者と子ども | 遺産の2分の1 |
| 配偶者と親 | 遺産の3分の2 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 遺産の4分の3 |
| 配偶者のみ | 遺産のすべて |
配偶者控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
|
ただし、2次相続の際は配偶者控除が使えないため注意が必要です。
2次相続とは、父親が亡くなって母親と子どもが遺産相続(1次相続)した後、母親が亡くなって子どもが遺産相続する場合を指します。
2次相続では配偶者(母親)が被相続人となっているため、配偶者控除は使用できません。
そのため、1次相続で配偶者控除を使って大幅に節税対策できたとしても、2次相続の際に子どもの相続税が大きくなる可能性があります。
未成年者控除・障害者控除
未成年者控除とは、相続人が未成年者の場合に相続税額から一定の金額を控除できる制度です。
親が亡くなった未成年者が、成年に達するまでには養育費が必要なため、負担を減らす目的で設けられました。
控除額は、「10万円×その未成年者が満20歳になるまでの年数」で算出します。
一方の障害者控除とは、相続人が障害者の場合に相続税額から一定の金額を控除できる制度です。
親の死後における障害者の生活保障や、健常者に比べて療養費・医療費などの負担が大きいことを考慮して設けられました。
控除額は「(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)」で算出します。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続した土地の評価額を減額できる制度です。
仮に1億円の土地を相続した場合は、小規模宅地等の特例を使えば評価額を2,000万円まで下げることが可能です。
相続した土地の評価額が2,000万円になれば、基礎控除額の範囲内となるため相続税は発生しません。
小規模宅地等の特例が使える土地や人、減額率などの条件は以下の通りです。
| 相続した土地の種類 | 使える条件など | 適用面積 | 減額率 |
| 住宅として使っていた土地 | 配偶者もしくは被相続人と同居していた人
※配偶者も同居人もいない場合は、3年間借家住まいの相続人が取得 |
330m² | 80% |
| 事業で使っていた土地 | 相続開始前からその土地で事業をやっている
相続税の申告終了(申告期限の10か月間)まで事業用の土地として使う |
400m² | 80% |
| 賃貸していた土地 | 相続開始前から土地の貸付を行なっている
相続税の申告終了(申告期限の10か月間)まで貸付を行なっている |
200m² | 50% |
相続税の申告を行う流れと必要書類
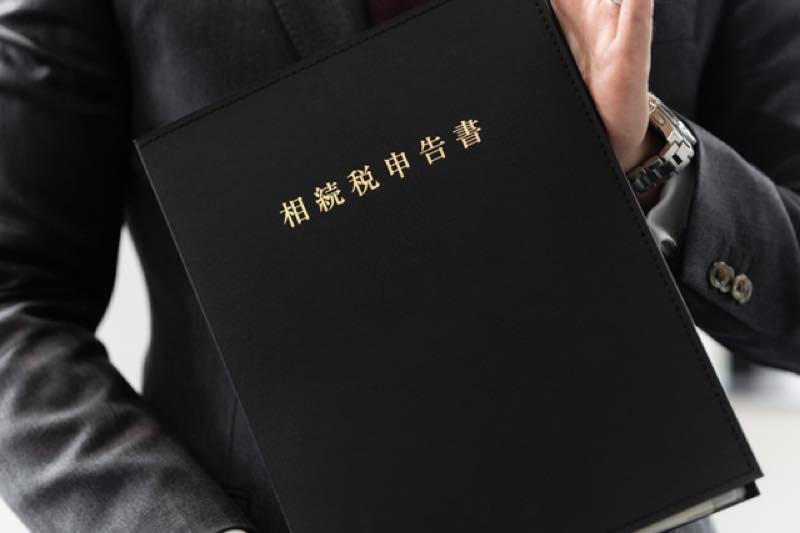
相続税の申告は、以下の手順で進めます。
|
申告に必要な書類
一般的な相続の場合は、相続税の申告に以下の書類が必要です。
|
相続時精算課税適用者がいる場合には、上記に加えて「被相続人および相続時精算課税適用者の戸籍の附票(写し)」が必要です。
相続税の納付は現金一括払いが基本

相続税の納付は現金一括払いが基本です。
以前は相続税を土地などで納める「物納」や、分割で支払う「延納」なども可能でしたが、現在は認められないケースが増えています。
相続税を工面できない場合は?
相続税を工面できない場合は、相続した不動産を担保に銀行でローンを組んだり、相続財産を売却して納税資金に回したりする方法がありますが、できれば避けたいところでしょう。
そこで、生前の相続税対策として生命保険を活用するのも1つの手です。
死亡保険金の非課税枠(500万円×相続する人数)を使えば、相続税が節税できます。
たとえば、配偶者のいない母親が亡くなって、3人の子どもが6,000万円の財産を相続すると仮定しましょう。
母親が生命保険に入っていなければ、6,000万円から基礎控除額4,800万円(3,000万円+600万円×3)を差し引いた1,200万円が課税対象です。
3人の子どもはそれぞれ400万円を相続することになり、1人あたり40万円(400万円×10%%)の相続税を支払わなければなりません。
しかし、母親が生命保険に加入して、財産を死亡保険金3,000万円とその他の財産3,000万円に分けていたとします。
6,000万円から基礎控除額4,800万円と死亡保険金の非課税枠1,500万円が引かれて、財産の評価額が0円になるため相続税は一切かかりません。
母親が生命保険に入っていたおかげで、合計120万円も相続税が節税できる計算です。
相続税を申告・納税しなかった場合のペナルティ

無申告加算税
無申告加算税は、正当な理由がないにもかかわらず期限までに申告を行わなかったときに課税されます。
無申告加算税で課税される税金額は以下の通りです。
|
なお、追加納付した税金額が50万円を超える場合は、超える部分に対して20%が課税されます。
延滞税
延滞税は、期限を過ぎてから相続税を納付した場合に課税される税金です。
納付期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じた金額が自動的に課税されます。
なお、期限内の申告も怠っていた場合は、無申告加算税と延滞税の両方が課せられるため注意が必要です。
重加算税
重加算税は、相続財産を意図的に隠したり偽ったりした場合に課税されます。
重加算税で課税される税金額は以下の通りです。
|
相続税の申告を行う際の3つの注意点

相続財産が基礎控除額の範囲内であれば、基本的に相続税の申告は不要です。
しかし、万が一相続財産の計算を間違えていれば、延滞税や加算税などが課せられる事態になりかねません。
そのような事態を避けるための注意点を解説します。
財産の見落とし
見落としがちな財産を含めて、相続財産は徹底的に洗い出しましょう。
特に以下のような財産は、見落とさないように注意が必要です。
|
精算課税制度を利用した
2,500万円までの生前贈与が非課税になる「相続時精算課税制度」を利用している場合も注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用している場合は、相続時に贈与財産の額を相続財産の額と合算して相続税額を計算する必要があります。
そのため、相続財産が基礎控除額の範囲内であっても、贈与額を合算したことにより基礎控除額を超えてしまえば、相続税を支払わなければなりません。
被相続人が亡くなる3年以内に贈与があった
財産を生前贈与した人が亡くなった場合は、死亡時からさかのぼって3年以内の贈与は相続財産とみなされます。
たとえば、親が亡くなる前の3年間に毎年200万円ずつ子どもに生前贈与していたとすれば、「200万円×3年分=600万円」を相続財産に加算しなければなりません。
3年以内の贈与分を加算することで、基礎控除額の範囲を超えることもあるため注意しましょう。
なお、令和6年4月1日以降に贈与された財産は、加算対象の期間が以下に変更されています。
| 相続開始日 | 加算対象の期間 |
| 令和6年1月1日~令和8年12月31日 | 相続開始前3年間 |
| 令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日~相続開始日 |
| 令和13年1月1日~ | 相続開始前7年間 |
相続税に関するご不安は林商会へ
相続税の手続きや計算は複雑なものが多いうえ、間違った状態で申告してしまうとペナルティを負うリスクもあるので慎重に進める必要があります。
そうはいっても、相続は何度も経験するものではないため、インターネットの情報だけを頼りにご自身で進めることに不安を感じる方も多いでしょう。
そんなときは、株式会社林商会にお任せください。
林商会では税理士や弁護士、司法書士による相続相談を受け付けております。
他にも、相続診断士や終活アドバイザーも在籍しており、ライフエンディングをトータル的にサポートすることが可能です。
まずは無料相談・お問い合わせからお気軽にご相談ください。
まとめ
相続税の規定は非常に複雑ですが、きちんと理解して控除や特例を活用すれば上手に節税できます。
また、余分な税金を支払うことのないように、相続財産を正しく把握して期限内に申告・納税を行いましょう。