新しい供養の形として注目されている手元供養。
文字通り、故人の遺骨や遺灰を手元において供養するもので、管理の手間や金銭的負担が少ないことから選ぶ人が増えています。
また昔ながらの仏壇とはまた違った、インテリアに馴染むデザイン性を重視した仏具が多いことも、人気を後押しする要因となっています。
本記事では、手元供養と仏壇・ミニ仏壇の違いや手元供養品の種類を詳しく解説します。
手元供養とは?

手元供養とは、故人の「遺骨」を対象とした供養の方法です。
ミニ骨壷に入れた遺骨をステージ台などに祀ったり、アクセサリーにして身につけたりして供養をします。
自宅などに遺骨を保管する手元供養は、新しい供養の方法として注目されています。
手元供養での遺骨の供養方法
手元供養を考える際、事前に決めておきたいのが遺骨の供養方法です。
すべてを自宅などで保管する「全骨保管」にするか、お墓や寺院に納骨した遺骨の一部を持ち帰って保管する「分骨保管」にするかをあらかじめ話し合っておくとよいでしょう。
すべての遺骨を自宅保管する「全骨保管」
遺骨のすべてを自宅などに置く全骨を希望する場合、収納方法や骨壷をどうするか決めておく必要があります。
手元供養用に販売されている商品は、ミニ骨壷などと呼ばれ、お墓に納骨される骨壷のサイズと比較すると小さいものが多く、全骨保管には不向きです。
そのため、複数の骨壷を購入して小分けにするか、粉骨して遺骨の体積を減らしてから納めるか、あらかじめ決めて事前に準備しておきましょう。
遺骨の一部を自宅保管する「分骨保管」
遺骨の一部を分骨して手元に残したい場合、事前に親族間で話し合っておく必要があります。
ご自身が遺骨の所有者である場合を除き、承諾なしに分骨はできないので注意しましょう。
遺骨の所有者や親族に了承を得てから、遺骨をどれくらい手元に残すかなどの詳細を決めていきましょう。
手元供養と仏壇・ミニ仏壇の違い
手元供養と仏壇・ミニ仏壇の違いは、以下の通りです。
| 手元供養 | 故人の遺骨を対象とした供養の方法で、供養の形式に決まりがない |
| 仏壇 | ご本尊やお位牌を対象とした供養の方法で、宗派によって仏具の飾り方が異なる |
| ミニ仏壇 | 通常の仏壇をコンパクトにしたもので、手元供養向きのものもある |
手元供養のメリット

手元供養には主に4つのメリットがあります。
|
それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう!
お墓が必要ない
手元供養の多くはお墓を必要としないスタイルです。
具体的には、遺骨を自宅のインテリアと調和するような骨壺に納めたり、アクセサリーに遺灰をほんの少しだけ納めて持ち歩いたり加工したりといった方法で供養します。
遺骨は、全骨保管する方、一部を手元に保管し残りを寺院やお墓に納める方など、その方法はさまざまです。
お墓と手元供養の両方で供養するといった方法を選択することも可能です。
お墓までの距離を気にする必要がない
お墓が遠方にある場合、行くだけで数日必要になることもあります。
そのため、大型連休で帰省したタイミングでお墓参りをされる方も多いのではないでしょうか。
このように、頻繁にお参りに行くのが難しい場合、掃除や手入れが十分にできず、大切なお墓が荒れてしまう可能性もあります。
手元供養の場合はお墓が不要なため、距離や時間などを気にすることなくいつでもお手入れができ故人を偲ぶことができます。
費用面での負担が少ない
新しくお墓を建てる場合、寺院の永代使用料や墓石の工事費用などが発生します。
墓石の種類や寺院によって値段は変わりますが、少なくとも100万円以上の出費と考えておくといいでしょう。
その一方で、手元供養を選択した場合、経済状況や予算に合わせて比較的自由に費用を決めることができます。
また、お墓の管理費などの維持費も必要ないため、家族に費用面で負担をかけたくない方にもおすすめです。
ただし、遺骨を一部のみ手元に置いてお墓と併用している場合、お墓の維持費などはかかります。
伝統にこだわらず故人を身近に感じることができる
手元供養を選ぶ最大のメリットは、より故人を身近に感じられることではないでしょうか。
遺骨を身近で管理・保管できるため、いつでも故人を偲ぶことができます。
特に、ネックレスやキーホルダーなどアクセサリーにする方法を用いると、大切な故人をより近くに感じられ、そばにいてくれているような温かな気持ちになるでしょう。
手元供養品の種類<6選>

手元供養を行うための仏具はさまざまで、部屋のインテリアに合うようなおしゃれなデザインのものなど幅広く販売されています。
ここでは、手元供養に使われる仏具を紹介します。
ミニ骨壺
ミニ骨壷は、遺骨や遺灰の一部を中に納めて保管するための骨壺で、従来のサイズより小さいのが特徴です。
デザインはベーシックなものから洋風のものまで幅広く、素材も陶器、金属、ガラス、革など種類が豊富なため、自宅のインテリアに合わせて選ぶことが可能です。
大きさは2〜3寸ほどの手のひらサイズが一般的で、最近では有田焼や南部鉄器などのミニ骨壺も販売されています。
ペンダント・ブローチ
手元供養の品として人気なのが、ペンダントやブローチといったアクセサリー型の仏具です。
アクセサリー型の仏具は2種類あり、どちらも一見仏具とはわからないようなおしゃれなデザインです。
中に空いている小さな空洞に遺骨や遺灰を入れて持ち歩くタイプと、遺骨を人工の宝石や樹脂などに加工するタイプがあります。
身につけて持ち歩くことができるので、より故人を身近に感じたい方におすすめです。
ミニ仏壇
遺骨や遺影を仏壇のように飾りたい方は、ミニ仏壇がおすすめです。
木製やガラス製など素材やデザインの種類が豊富で、部屋のインテリアや置く場所の大きさに合わせて選ぶことができます。
また、箱型ではなくステージタイプもあります。
オブジェ
オブジェタイプの仏具は、中に遺骨や遺灰を保管できるものと、遺骨を加工するものがあります。
納骨タイプには仏像やお地蔵さまを模したもの、遺骨を加工するタイプはガラス加工の水晶玉やセラミックの陶器プレートといった商品が人気を集めています。
また、クリスタル製の位牌やフォトスタンドなど遺骨を入れないタイプのオブジェも作ることが可能です。
迷ったときは手元供養のセット購入がおすすめ
手元供養の仏具で迷った際、セットで購入するのがおすすめです。
後で足りないと思って買い足すよりも、必要なものが最低限揃ったセットを購入しておくと安心です。
ここでは、おすすめの手元供養セットをいくつか紹介します。
ナチュラルな雰囲気のミニ仏壇セット

未来創想のミニ仏壇セットは、木ならではのくもりを感じられるやさしいデザインが特徴です。
写真立て、花立て、ろうそく、火立て、お線香、香炉、香炉灰がセットになっており、初めて仏壇を置く方でも安心して使い始められます。
どんなインテリアに馴染むおしゃれなセット

ナルミボーンチャイナの手元供養セットで敷台、壺台、蝋燭立、花瓶、香炉、皿の5点になっています。
美しいデザインでどこに置いても目を引き、繊細でやわらかな色合いが特別な祈りの空間を作り出してくれます。
手元供養にかかる費用
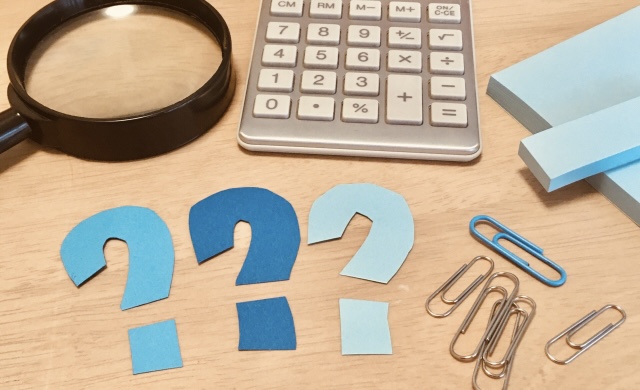
手元供養そのものに必ずかかる費用はありませんが、供養の方法次第で費用は大きく変わるので事前に確認しておく必要があります。
| ・遺骨の粉骨費用 ・加工費用 ・手元供養品購入費用 ・分骨費用 |
ここでは、手元供養に必要なこれらの費用について詳しく解説します。
遺骨の粉骨費用
遺骨の粉骨を業者に依頼する場合、粉骨費用がかかります。
粉骨作業に抵抗がなければ自身で行なっても問題ありませんが、素人が綺麗に粉骨するのは難しく抵抗がある方も多いため、専門の業者に依頼するのがおすすめです。
遺骨の状態や粉骨方法によっても料金は変わりますが、3万円前後が一般的な費用相場とされています。
加工費用
遺骨を加工して手元供養する場合、加工するものや素材で大きく費用は変わります。
シルバー素材であれば数百円〜と安価なものもありますが、真珠であれば30万円程度、麗石は10〜15万円程度など素材によって大きな差があるため、予算に合わせて事前に決めておくといいでしょう。
人工宝石の代表「遺骨ダイヤモンド」に加工したい場合、大きさやカット方法によって異なりますが、0.2カラットでも45万円程度、1カラットとなると200万円前後とかなり高額な費用がかかります。
手元供養品購入費用
手元供養品として購入するミニ骨壺は、安価なもので数千円~あります。
素材やデザインに凝ったものだと数万〜数十万円のものまであるため、あらかじめ予算を決めておくと迷わずに選ぶことができます。
デザインだけでなく、強度や密閉できるかなど、機能も重視して選ぶようにしましょう。
分骨費用
分骨する場合、分骨証明書の発行費用がかかります。
分骨証明書は分骨に必要なのではなく、分骨を他の場所に納骨する際に必要な書類です。
手元に遺骨があるときは必要のない書類ですが、さまざまな事情で遺骨をどこかへ納めなければならなくなった場合に必要となるため、あらかじめ収得しておくのがおすすめです。
分骨証明書の発行費用は1通数百円程度で発行できますが、納骨後の発行の場合、墓石を動かす費用や閉眼供養、開眼供養などでそれぞれ数万円がかかります。
一部を散骨する・納骨する場合
遺骨の一部を散骨・納骨したい場合も方法によって費用は大きく変わります。
一部を散骨したい場合
散骨は火葬を行なった後の遺骨を粉骨にして海や山などに撒くのが一般的ですが、散骨自体に費用がかかるわけではなく、散骨する手段によって費用が発生します。
素人判断で散骨をしてしまうと後々トラブルにもなりかねないため、専門の業者に依頼するのが無難でしょう。
散骨は「海洋散骨」「樹木葬」が主流で、最近では「宇宙葬」などといった新しい散骨方法も注目を集めています。
海洋散骨は、単独で散骨したい場合は20~30万円程度、他の方との合同で散骨する場合は10万円前後、業者にお任せする場合は5万円前後の費用が目安です。
樹木葬の費用相場は50万円程度で、植える場所によりますが、年間1〜2万円程度の管理費などが必要となる場合もあります。
一部を納骨する場合
一部を納骨する際の基本的な費用は、墓誌への彫刻料が3万~5万円、納骨作業費が5,000円〜、お供えものが5,000円前後、合わせて5万円ほどを目安にしておくとよいでしょう。
手元供養の注意点

遺骨を自宅などに保管できて故人を身近に感じられる手元供養ですが、行う際に気をつけるべきこともいくつかあります。
注意点を詳しく見ていきましょう。
家族親族の承諾はとれているか?
手元供養にすると決定する前に、必ず家族や親族に相談しましょう。
手元供養は新しい供養の方法であるため、家族の理解を得られなかったり反対されたりする場合もあります。
まずは、手元供養をしたいという意向を伝えることが大切です。
家族や親族に理解してもらうことでトラブル防止につながるでしょう。
費用や手間がゼロではない
手元供養はお墓に比べて手間や維持費用がきらないのは確かですが、ゼロというわけでもありません。
手元供養とはいえ、さまざまな費用がかかります。
方法によっては一般的な供養と同じくらい手間がかかることもあるでしょう。
お墓のように継承できない
手元供養にした場合、お墓のように継承できないことや自分で遺骨を管理できなくなったときどうするか、などといった将来のことも考えておかなければいけません。
お墓に遺骨がある場合と違い、手元供養の遺骨は自由に埋葬したり処分したりできないため、何かあった際にどのように対処するのかを事前に話し合っておきましょう。
まとめ
手元供養は、宗教や宗派に関係なく誰にでも行うことができる新しい供養の形です。
従来の考え方や宗教にとらわれない手元供養は、より故人を身近に感じることができます。
手元供養のメリット・デメリットを十分に理解したうえで、ご自身が納得できる供養の方法を選択しましょう。
仏壇に関するお悩みやお困りごとがあれば、終活のトータルサポートを行う林商会へお気軽にご相談ください。




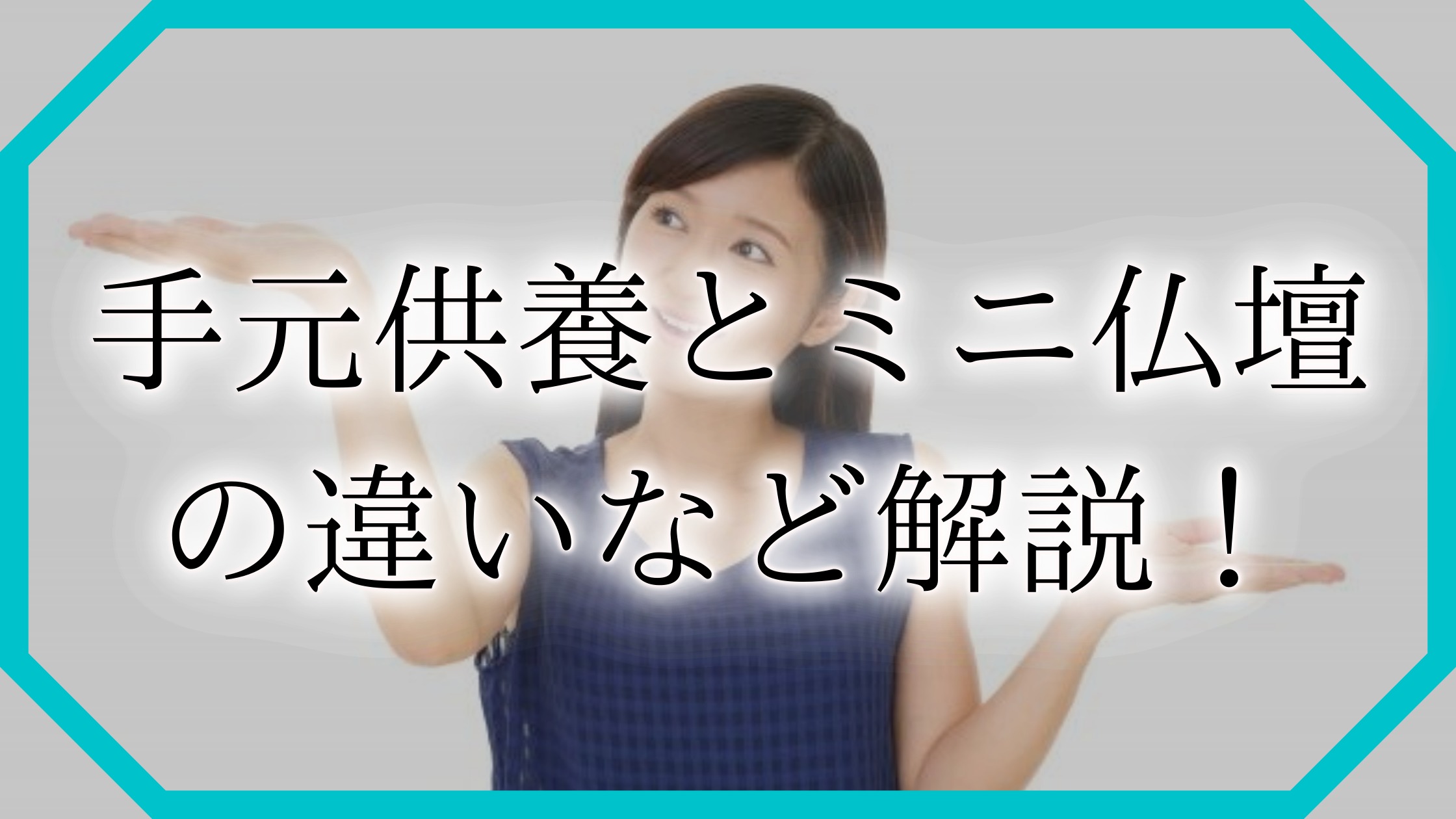

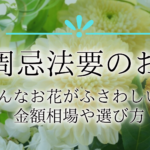



 アイキャッチ-485x273.jpg)









