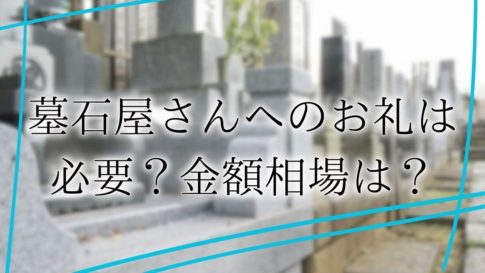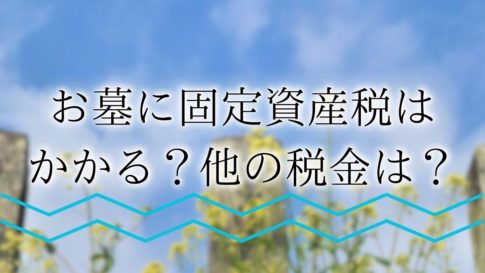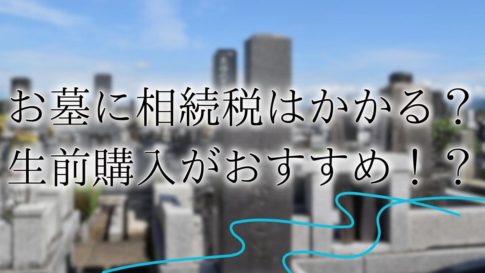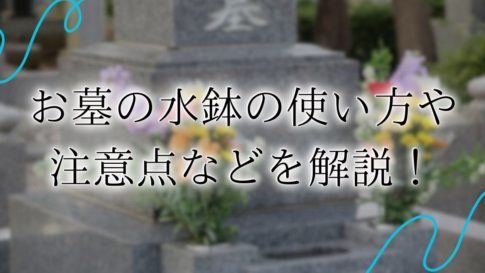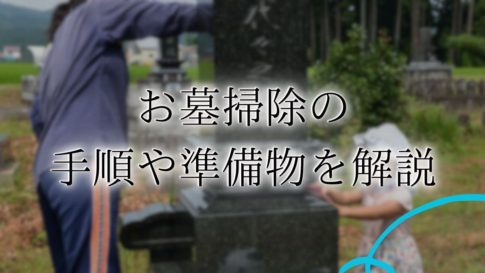お墓に砂利を敷きたいけれど、「良くない」という話を聞いて悩んでいませんか?
確かに良くない点もありますが、お墓に砂利を敷くことは、よりお手入れが楽で綺麗な景観が保てるというメリットもあります。
本記事では、お墓に砂利を敷くメリット・デメリットのほか、お墓や好みに合わせた砂利を敷くために役立つ情報を解説しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
【メリット】お墓に砂利を敷いても良い!3つの効果とは

近年、お墓周りの美観を意識して敷地に砂利を敷く方も増えています。
結論から言うと、お墓に砂利を敷くのは、綺麗な状態を保ちやすく安全面でも有効なのでおすすめです。
具体的には下記3つの効果があります。
防草対策ができる
お墓に砂利を敷くと、雑草の種が地面にたどり着きにくくなるので、防草対策が見込めます。
お墓周辺の美観を保ちつつも、除草作業の頻度を減らせるでしょう。
ただし、砂利単体では完全な防草対策とはならないため、他の方法を併せて行いましょう。
砂利以外の防草対策は、後述する「【併用OK】砂利以外の除草方法」の章で詳しく紹介します。
景観が綺麗になる
砂利を敷くことにより、お墓の景観が改善されます。
お墓周りを明るく清潔感のある状態に保ちたい場合は、白い砂利を敷くと良いでしょう。
一方で、黒い砂利を選ぶと高級感やシックな雰囲気を演出できます。
さらに、砂利が敷いてあると水はけが良くなり、雨や雨上がりの日でもお墓周りがぬかるみにくくなるでしょう。
泥掃除の手間が省けるうえに、お参りに来る人の靴を汚さないのも嬉しいポイントです。
侵入者対策ができる
お墓に砂利が敷いてあると、侵入者に対するセキュリティ効果も期待できます。
夜間など暗闇の中でも、侵入者が砂利を踏む音がすることでその存在に気付けるからです。
また、砂利の存在自体が侵入者への抑止力にもなりえます。
【デメリット】お墓に砂利を敷く際の注意点とは

砂利敷きが「良くない」といわれる3つの理由も紹介します。
掃き掃除ができなくなる
砂利の表面は不規則な形状をしており、ホウキなどでの掃き掃除が困難になります。
お墓周りに溜まった落ち葉やゴミなどを一斉に掃きたい場合には、砂利が邪魔になるかもしれません。
砂利に苔が生える可能性がある
砂利の表面は湿気を含みやすく、日陰や湿度の高い場所では、時間の経過とともに苔が生える恐れがあります。
苔が発生するとお墓周辺の清潔感が失われ景観も損ねるため、苔が生えにくい環境づくりや砂利の交換が欠かせません。
業者依頼や購入に費用がかかる
お墓に砂利を敷くには一定の費用がかかります。
特に業者に依頼する場合は、砂利の種類や敷地の広さ、作業内容などによって費用が異なるため、見積もりを取ることが大切です。
費用だけでなく品質や信頼性も重要なので、適切なコストと品質のバランスを考えながら計画を立てましょう。
お墓に敷ける砂利の種類

実際に使われているお墓の砂利はいくつかの種類に分類されます。
それぞれの特徴や価格帯をみていきましょう。
①砕石
砕石(さいせき)は、大きな岩石をクラッシャー(粉砕機)で小さく割った石です。
丸みを帯びた一般的な砂利とは異なり、鋭く角張っており不規則な形状をしているのが特徴で、お墓の砂利として使われる場合の大きさは6分程度となっています。
「分(ぶ)」とは、日本伝統の寸法規格で、1分が直径約3mmなので、6分はおよそ1.8mmです。
砕石は庭石のアクセントとしてもよく使用され、独特の雰囲気を加えることができます。
清涼感や爽やかさを演出できる青味がかった「青砕石」と、上品で優雅な印象を与える大理石でできた「白砕石」の2種類が有名です。
| 1kgあたりの販売価格 | 100~200円程度 |
②砂利
お墓を扱う業界では、1~2分(約5mm前後)ほどの小粒で丸みのある石を砂利と呼びます。
砂利は、豊富な色彩が特徴で、単色やミックスといったバリエーションがあり、好みに合わせて選ぶことができるでしょう。
また、砂利は小粒であることから、歩いたときの音や踏み心地が良いという特徴もあります。
| 1kgあたりの販売価格 | 50~150円程度 |
③玉砂利
玉砂利は、砂利よりも大きいサイズで天然の鉱石を加工したものです。
丸みを帯びた形状と、滑らかな表面に光沢があるのが特徴で、上品な印象を与えられるでしょう。
| 1kgあたりの販売価格 | 50~150円程度 |
また、玉砂利は、色や産地によって下記4種類に分類されます。
五色玉砂利
淡路島の五色が浜で産出される玉砂利は、五色玉砂利と呼ばれています。
鮮やかな赤や黒、白の三色がミックスされているのが特徴です。
全体的に色のバランスが取れており高級感があります。
白玉砂利
白玉砂利は、白の石灰岩の原石を砕き加工したものです。
和・洋どちらのタイプのお墓にも合い、明るい雰囲気や清潔感、神聖さが感じられます。
黒玉砂利(黒那智)
グレーがかった黒色の黒玉砂利は、もともと和歌山県の那智地方で産出されていたことから黒那智とも呼ばれています。
ただし、現在では外国産の石が主流になっているようです。
シックで落ち着いた雰囲気があり、墓石を引き立てる効果もあります。
緑玉砂利(大磯)
緑色を基調とした緑玉砂利は、昔から観賞魚用水槽の底砂としてもよく使用されているポピュラーな石です。
お墓の砂利の中でも、上品な雰囲気を醸し出したいときにおすすめの玉砂利です。
砂利を敷くのにかかる費用相場

砂利を敷くための費用は、業者に依頼する場合と自分で購入する場合で異なります。
それぞれの費用相場は下記の通りです。
業者に依頼する場合
お墓の砂利敷きを業者に依頼したい場合、まずはお寺や霊園で指定されている施工業者があるかを確認します。
指定業者がない場合は、石材店など複数の業者で見積りを取り、比較・検討してから依頼しましょう。
砂利敷きの施工費用の相場は、1m²につき1,500〜3,000円ほどで、別途、搬入費用や砂利石代が発生します。
また、下地としてモルタル(セメント)貼りをする場合は、1m²につき1〜2万円程度が相場となるため予算に入れておくことが必要です。
なお、施工業者によっては、清掃代行や入れ替え時の砂利の除去などをオプションでつけられるケースもあるので、必要に応じて利用してください。
自分で購入する場合
砂利は下記のようなお店で購入できます。
|
ホームセンターなどでは、1袋20kgで販売されていることが多く、相場は1,000~2,000円ほどです。
最近ではインターネットでも購入できますが、掲載画像と実物が異なる場合があります。
砂利の色や質感をきちんと確かめたい場合は、店舗に足を運びましょう。
お墓に砂利を敷く方法

ここでは、業者に依頼せず自分でお墓に砂利を敷く方法を紹介します。
1.砂利の必要量を算出する
まずは、必要な砂利の量を算出しましょう。
適切な量を計算することで、予算管理や砂利の手配がスムーズに行えます。
【計算式】
必要量を算出するには、下記の計算式を使います。
| 面積(m²)× 厚み(cm)× 20=必要な砂利の量(kg) |
上記の「面積」は砂利を敷きたい場所の広さ、「厚み」は砂利の層の厚み、「20」は1m²に必要な砂利の重さを表します。
なお、砂利の厚みに決まりごとはありませんが、一般的には3~10cmが目安です。
砂利の種類やお墓の土、周囲の状況に合わせて厚みを考えましょう。
具体的な例として、面積が1m²で砂利の厚みを3cmとすると、必要量は下記のように求められます。
| 1m² × 3cm × 20 = 60㎏ |
この場合、必要な砂利の量は3袋(60kg)です。
2.雑草を除去する
砂利を敷く場所の土を5cm以上掘り起こし、雑草を根ごと取り除きます。
深く掘るほど防草効果が高まるので、雑草の生えている状況を確認しながら行なってください。
3.地面をならす
掘り起こした後は、投入する砂利の分だけ土を取り除きます。
さらに、スコップや平らな板などを使って地面を平らに整えましょう。
ここで丁寧にならしておくと砂利の偏りが減り、綺麗に仕上げられます。
4.砂利を敷き詰める
地面をならせたら、外柵の高さに合わせて砂利を均等に広げます。
お墓の敷地全体に平らに敷き詰められたら完成です。
【併用OK】砂利以外の除草方法

砂利を敷くと雑草は生えにくくなりますが、下記のいずれかを併用すればより防草効果が高まります。
①防草シート
防草シートは、地面に直接敷いて光を遮断するので、地中に根や種が残っていても、光合成を阻害し雑草を生えにくくします。
除草剤などが使えない場合に便利なアイテムですが、経年劣化するため定期的な取り替えが必要です。
②モルタル貼り
砂利を敷く部分を、セメントと水、砂を混ぜ合わせたモルタルで固めると雑草は殆ど生えません。
防草効果は高いですが、表面を固めてしまうことから、雨が降ると砂利が流れ出る点には注意が必要です。
また、宗派や地域によっては、お墓の土を固めるのは良くないとする考え方もあるので、事前に確認しましょう。
③防草マサ
防草マサは、ろう石、砂、および固化材を主成分とした防草土です。
外観は通常の土に似ていますが、表面が固まるため雑草が生えるのを抑える効果があります。
また、固まると水を通しにくくなり、雨水などで表面に苔や水アカが発生するケースもあるので、それぞれの商品の特性を理解したうえで利用しましょう。
④ストーンレジン
ストーンレジンは、天然石と樹脂を組み合わせて作られる舗装材で、庭や玄関回り、広場などでも利用されています。
ストーンレジンの特徴は、透水性をもつため苔や水アカの心配が少ないことです。
ただし、樹脂で固められるため一般的な土や砂利とは異なった風合いがあり、しっくりこないと感じる方もいるかもしれません。
【ケース別】砂利を敷いた後のお手入れ方法

砂利を敷いた後は、お墓の美しさを維持するための定期的なお手入れが必要です。
下記では、砂利を敷いた後のケース別のお手入れ方法について解説します。
砂利が少なくなった場合は?
屋外に敷かれている砂利は雨風に晒されるため、時間が経つにつれて次第に数が減っていきます。
また、防草シートなどを使わず土の上にそのまま敷いてある場合は、中にどんどん埋まって(砂利の沈み込み)しまい、少なくなったと感じることもあるでしょう。
もし砂利の目減りが気になるようなら、少なくなった箇所に砂利を補充しましょう。
ただし、砂利の減少ペースがあまりにも早いようなら原因を解消することも大切です。
状況に応じて防草シートの利用やモルタル貼りを検討してください。
砂利に苔が生えた場合は?
湿度や日照条件によっては砂利の表面に苔が生えることがあり、特に湿度の高い場所では注意が必要です。
少量の苔であれば、水を張ったバケツに砂利を入れ、歯ブラシやブラシで丁寧にこすることで取り除けます。
しかし、大量の苔が発生している場合は完全に除去するのが難しいため、砂利を入れ替えるのが一般的です。
砂利に苔が生えていると足元が滑りやすく、墓石にも繁殖する可能性があるので早めの対処を心がけましょう。
砂利を捨てたい場合は?
お墓の砂利を処分する場合は、墓地の管理者に相談し、規約や作法に準じた方法で行いましょう。
砂利を撤去する際は、塩や海水でお清めを行なってから移動させ、移動後に再度お清めをするのがマナーです。
お墓の石や砂利は原則持って帰ってはいけないため、自宅で再利用するのはおすすめできません。
しかし、どうしても必要という場合は、撤去時と同様のお清めを行なってください。
まとめ

お墓の砂利敷きは、防草対策や侵入者対策など多くのメリットが期待でき、おすすめできる施策です。
ただし、掃除の難しさや苔の生えやすさなど踏まえておくべきデメリットもあります。
お墓に砂利を敷く際は、砂利の種類や費用、お手入れ方法などを考慮して、お墓の環境や好みに合わせたものを選びましょう。




.jpg)


 アイキャッチ-150x150.jpg)